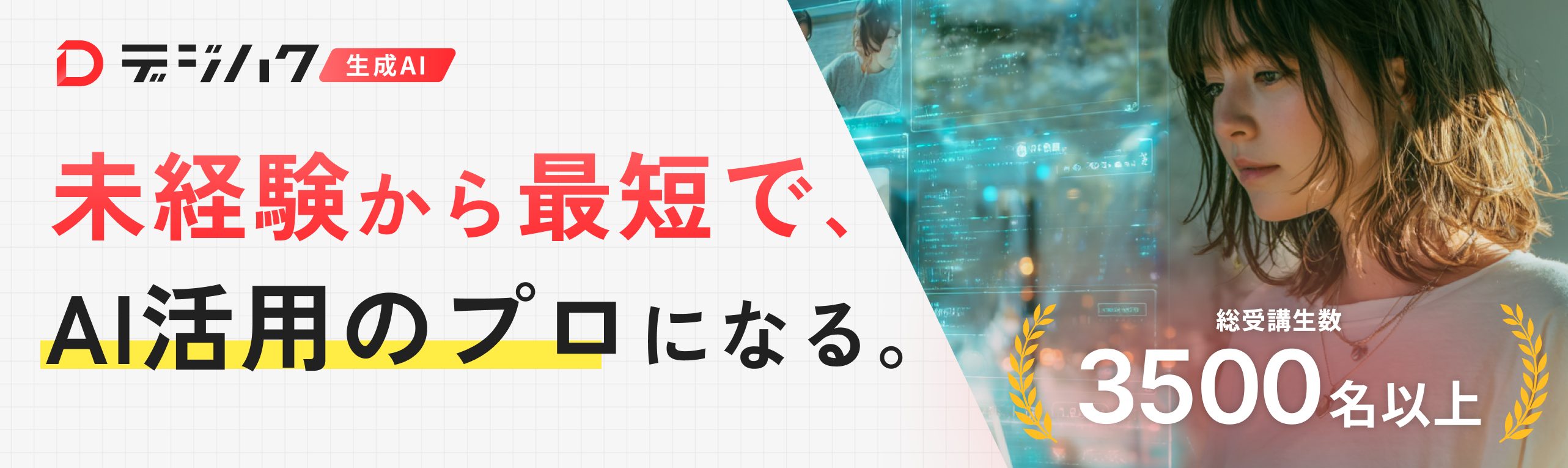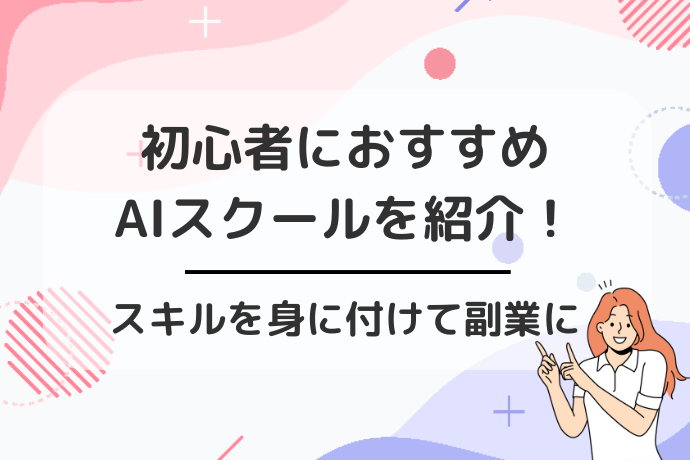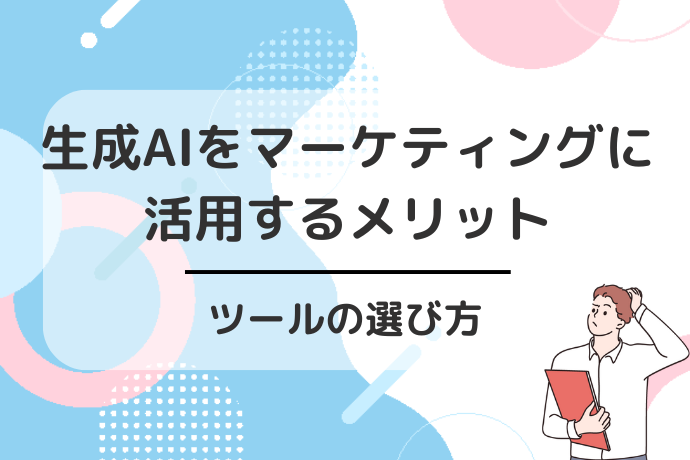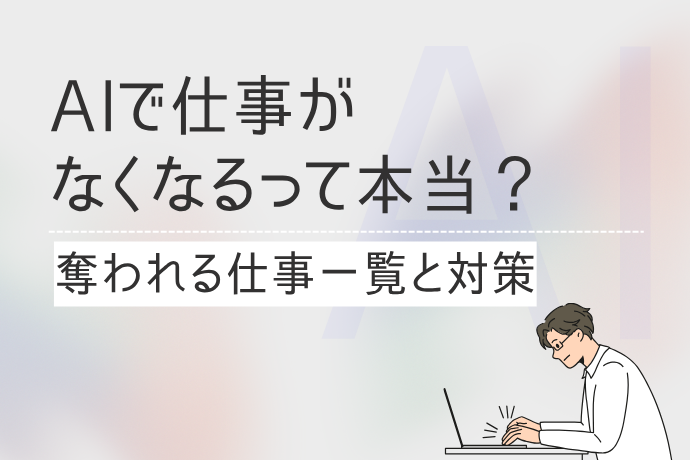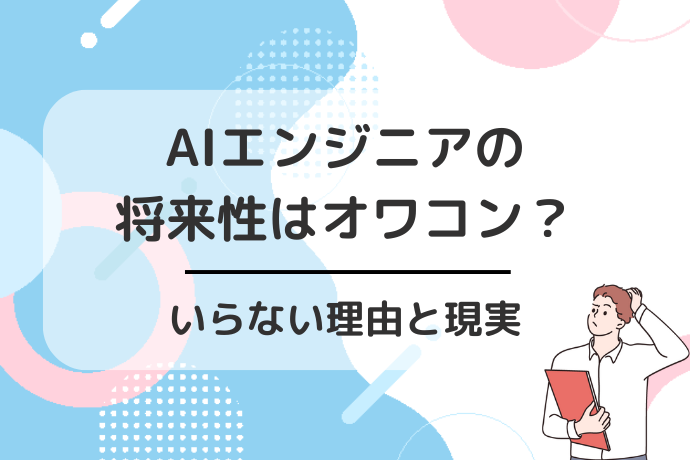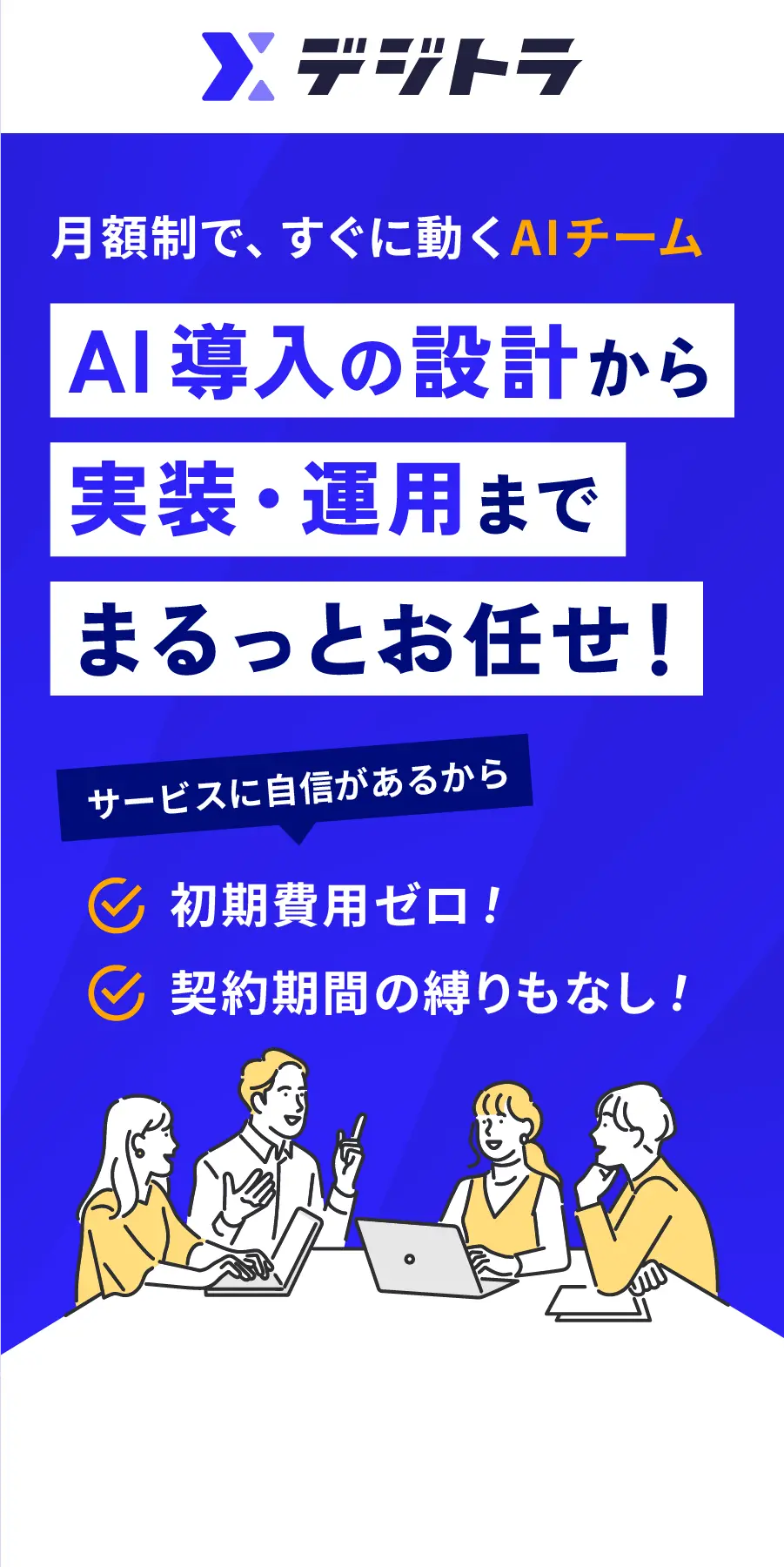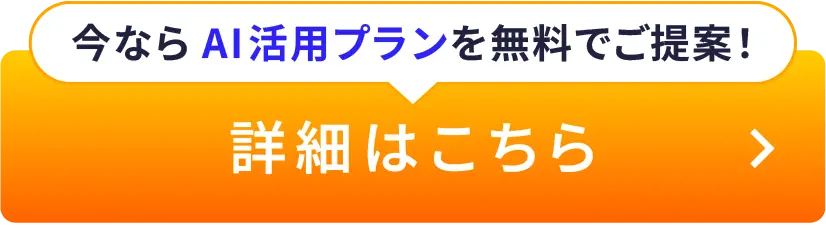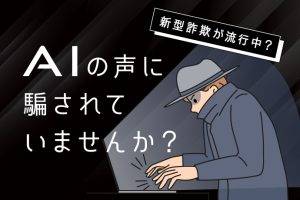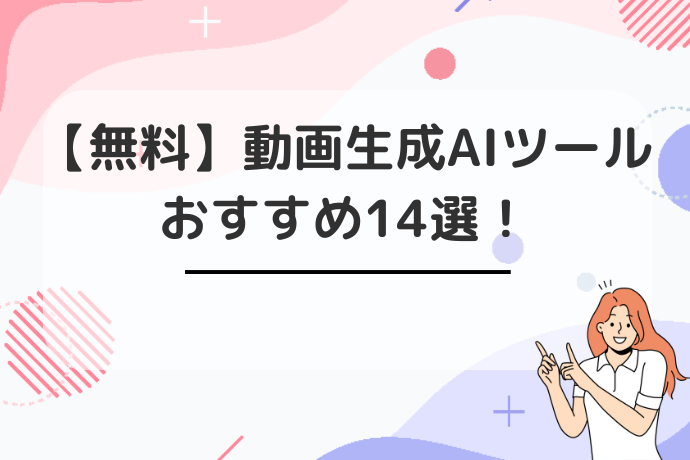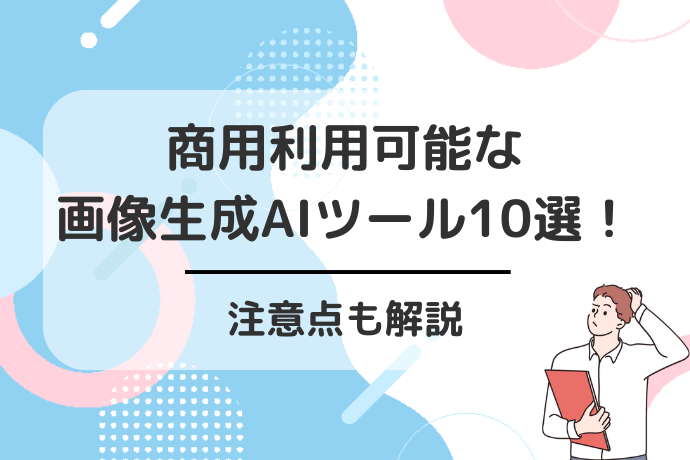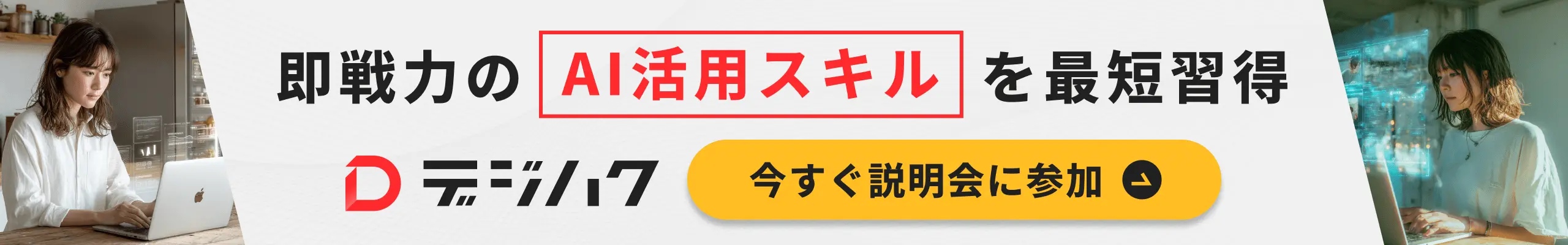単純作業から高度な分析、そしてクリエイティブな仕事までAIを活用することで働き方が大きく変わりつつあります。
特にバックオフィスや営業、カスタマーサポートなど、幅広い業務でAIの導入が進み、時間やコストの削減に役立っています。
この記事では、具体的にどのような業務がAIで効率化できるのか、活用事例やおすすめツールの選び方までわかりやすく解説します。
なぜ今、生成AIが業務効率化に欠かせないのか?
生成AIが業務効率化に欠かせない理由は、作業スピードと精度を大幅に向上させられる点にあります。
従来は文章作成やデザイン、データ分析などに多くの時間がかかりましたが、生成AIを活用すれば短時間で質の高い成果物を生み出すことが可能です。
さらに、AIは単なる自動化にとどまらず、人間にはないアイデアや表現を提案できるため、クリエイティブな業務の幅も広がります。
テレワークや多様な働き方が進む現代では、限られた時間で成果を出す必要があるため、生成AIを活用することで効率化と創造性の両立が実現し、組織全体の生産性向上につながります。
AI活用で効率化できる具体的な業務
AIは今やビジネスのあらゆる現場で導入されており、多くの業務を効率化しています。
人が時間をかけて行ってきたルーティン作業や大量のデータ処理を自動化し、ミスを減らしながらスピーディーに仕事を進められるのが大きなメリットです。
ここでは、特に効果が期待できる主な業務分野を詳しく紹介します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

バックオフィス業務・管理業務
経理や人事、総務などのバックオフィスは、日々のデータ入力や書類作成、勤怠管理など定型的な作業が多く、時間も手間もかかります。
AIが対応可能なのは下記のような業務です。
- 請求書の自動読み取りや振り分け
- 給与計算や社会保険手続きのサポート
- 社員情報の管理
これによりヒューマンエラーが減り、業務の正確さが向上。

担当者は単純作業から解放され、より戦略的な企画や業務改善に注力できるようになります。
営業・マーケティング業務
営業やマーケティングの現場では、顧客データや過去の取引履歴をAIが解析し、購買意欲の高い顧客を抽出したり、最適なアプローチ方法を提案したりします。
さらに、売上予測や市場動向の分析もAIがリアルタイムで行い、効率的な営業戦略をサポート。
広告配信の最適化や効果測定も自動化できるため、無駄な広告費を削減しながらターゲットに響くコンテンツを届けられます。
こうした支援で、営業スタッフは成果を上げやすくなります。
カスタマーサービス・サポート業務
お客様からの問い合わせ対応は、24時間体制が望ましく、多くの企業で負担となっています。
AIチャットボットや自動応答システムは、よくある質問に即答できるだけでなく、問い合わせ内容を分類し、難しい問題は人間の担当者にスムーズに引き継ぐことが可能。これにより顧客満足度が向上し、スタッフの負担も軽減されます。

AIは大量の会話データを分析し、顧客のニーズや不満点を把握することで、サービス改善にも役立っています。
開発・製造・研究
製造業の現場ではAIが製品検査を自動で行い、不良品の発見率を高めています。
加えて、機械の異常を検知し故障を未然に防ぐ予知保全もAIの得意分野。
これによりダウンタイムが減り、生産効率がアップします。
研究分野では、大量の実験データをAIが高速で解析しこれまで見落とされていたパターンや新しい知見を見つける支援をします。
結果として研究開発のスピードが大幅に向上し、新製品や技術の早期実用化につながります。
ChatGPT/生成AIを活用した業務効率化術
近年、ChatGPTのような生成AIはさまざまな業務の効率化に役立っています。
単なる質問応答だけでなく、アイデア出しや文章作成、データ分析の補助まで幅広く活用できるのが特徴です。
ここでは具体的に、どんな業務で生成AIが効果的かをご紹介します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

資料作成のアイデア出しと構成案作成
資料作成の際、何を伝えればいいか悩んだり、構成をどう組み立てればいいか迷った経験はありませんか?
生成AIにキーワードやテーマを入力すると、わかりやすいポイントやセクション案を提案してくれます。
これにより、資料の骨子がすぐにできて、作業がグッと早くなります。
例えば、会議用のプレゼン資料や企画書の構成案を一瞬で作れるので、忙しいビジネスパーソンに大好評です。
メールの返信文、ビジネス文書の生成
毎日のメール返信や報告書作成も、生成AIが助けてくれます。
例えば
- 顧客からの問い合わせに対する丁寧な返信文
- 社内向けの簡潔な報告書の文章をAIが作成
必要な情報を入れて指示するだけで、ビジネスにふさわしい文章が手に入ります。
これによって、文章作成にかかる時間が大幅に減り、他の重要な仕事に集中できます。
データ要約と分析の補助
大量の資料や報告書を読むのは時間がかかりますよね。
生成AIは長文を短く要約したり、重要なポイントを抜き出すのが得意です。
また、数値データの分析結果をわかりやすい文章にまとめてくれることも。

これにより、膨大な情報を効率的に把握でき、意思決定をスピーディーに行えます。
アイディア出し
新しい企画やプロジェクトのアイデアを考えるのは楽しい反面、悩むことも多いもの。
そんなときに生成AIを使えば、キーワードやテーマに基づいて多彩なアイデアを次々と提案してくれます。
ブレインストーミングの相手として活用すれば、思いもよらない斬新な発想が生まれることもあります。
プログラミングコードの生成
プログラマーの間でも生成AIは注目されています。
簡単なコードの作成や、特定の機能を実装するためのサンプルコードをAIに頼むことが可能です。
エラー解決のヒントをもらったり、コードの効率化を相談したりもできます。
プログラミング初心者にとっても、学習のサポートツールとして使いやすいのが魅力です。
生成AIで業務効率化できるツール10選!
仕事の効率をぐっと上げてくれる生成AIツールは、いま多くの分野で活用されています。
特に「文章作成」「画像制作」「動画編集」の3つのジャンルに分けて代表的なツールを紹介します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

文章作成・編集ツール
| ツール名 | 特徴・用途 |
|---|---|
| ChatGPT | 自然な会話や文章作成が得意。幅広い用途に対応。 |
| Gemini | Googleの最新AI。高性能で多様な質問や文章作成が可能。 |
| Microsoft Copilot | Officeと連携し、ビジネス文書やメール作成を効率化。 |
| Perplexity | 質問応答やリサーチに特化。情報整理に便利。 |
ChatGPT
ChatGPTはOpenAIが開発した会話型AIで、自然な文章作成や会話のやりとりが得意です。
ユーザーの質問に対してわかりやすく回答したり、ブログ記事やメール文の作成、アイデア出しなど幅広い用途に使えます。
日本語にも対応しており、個人利用はもちろん、ビジネスシーンでの文書作成やカスタマーサポートの自動化など、多様な活用が可能です。

APIを使えば自社システムに組み込むこともでき、拡張性が高いのも魅力です。
Gemini
GeminiはGoogleが開発した最新の言語モデルで、検索技術と高度な文章生成を組み合わせたAIです。
膨大な情報を効率よく検索しながら、正確で専門的な文章を作り出せるのが強みです。
研究やリサーチに向いており、複雑な質問にも詳しく答えられるため、マーケティング資料や技術文書の作成に適しています。
まだ開発段階の部分もありますが、将来的に幅広いビジネス分野での活躍が期待されています。
Microsoft Copilot
Microsoft CopilotはMicrosoft 365(Word、Excel、Outlookなど)と連携し、ビジネス文書の作成やデータ処理を効率化するAIツールです。
例えば
- Wordでの文章作成支援
- Excelでの複雑なデータ分析の自動化
- メールの返信文の提案
など、日々の業務負担を軽減します。
企業向けの製品で、セキュリティ面も充実しているため安心して利用できる点も特徴です。
特にMicrosoft製品を中心に仕事をしている企業には最適です。
Perplexity
Perplexityは質問に対して即座に回答を返すタイプのAIツールで、ウェブ検索とAIの機能を融合させています。
調べ物やリサーチの効率化に特化しており、複数の情報源からの回答をまとめて提示できるのが強みです。
使い方もシンプルで、知りたいことを自然な言葉で入力するだけで迅速に回答が得られます。

情報収集やマーケット調査、学習の補助として活用されており、初心者からプロまで幅広く使われています。
画像生成AIツール
| ツール名 | 特徴・用途 |
|---|---|
| Canva | 誰でも使いやすいオンラインデザインツール。AI機能搭載。 |
| DALL·E 2 | テキストから高品質な画像やイラストを生成。 |
| Midjourney | 芸術的でリアルな画像生成に強み。クリエイターに人気。 |
Canva
Canvaは直感的な操作でデザインができるオンラインツールで、最近AIを活用した画像生成機能が追加されました。
テンプレートや素材が豊富で、初心者でも簡単にSNS用の画像やチラシ、プレゼン資料のビジュアルを作成できます。
AI機能では、キーワードを入力するとオリジナルの画像を自動生成したり、写真の補正や編集もスムーズにできます。
無料プランでも使いやすく、幅広いユーザーに支持されています。
DALL·E 2
DALL·E 2はOpenAIが開発した高性能な画像生成AIで、テキストの説明からリアルでクリエイティブな画像を作り出せるのが特徴です。
細かいニュアンスや抽象的なアイデアもビジュアル化できるため、広告やアート制作、ゲームデザインなどクリエイティブな現場で活躍します。
色彩や構図も多彩で、オリジナリティの高い画像を簡単に生成可能。

API連携も可能なので、自社サービスへの組み込みもできます。
Midjourney
Midjourneyはアーティスティックで独特な雰囲気の画像を作成できる画像生成AIです。
クリエイターやデザイナーに人気で、ファンタジーやSF系のビジュアルを得意としています。
Discordを通じて操作するスタイルで、テキストプロンプトを入力するだけでイメージ通りの作品が出来上がります。
特に独創的な世界観を表現したい人におすすめで、商用利用も可能です。
動画生成AIツール
| ツール名 | 特徴・用途 |
|---|---|
| HeyGen | AIキャラクター動画作成が簡単。説明動画やプレゼンに活用可能。 |
| Runway Gen-2 | 高度な動画編集やAI自動編集・エフェクト機能を搭載。 |
| Vrew | 音声を自動テキスト化し、テロップ作成をスムーズに支援。 |
HeyGen(旧:Movio)
HeyGenは、テキストを入力するだけでAIアバターが喋る動画を自動生成できるツールです。
プレゼン動画や商品紹介、教育用コンテンツなどに最適で、ノンデザイナーでもプロっぽい動画を手軽に作れます。
数十種類のアバターと多言語対応の音声合成があり、グローバル向けの動画制作にも便利。
背景やアニメーションのカスタマイズも簡単です。
Runway Gen-2
Runway Gen-2は、動画の生成や編集をAIで行える高機能ツールです。
「テキスト to 動画」「画像 to 動画」「動画のスタイル変換」など幅広い機能を備えており、特にプロ仕様のビジュアルコンテンツ制作に適しています。
AIを使って映像の一部を修正・合成する機能もあり、CMやMV、映画のプリビズなどに活用されています。

動画編集経験がある人には特におすすめのツールです。
Vrew
Vrewは、AIを使って動画の字幕作成・編集ができるツールです。
YouTuberや企業の動画マーケティング担当者に人気で、動画を読み込むだけで自動的に音声を認識し、字幕を挿入してくれます。
テキスト編集感覚で字幕を修正できるので、スピーディに動画を仕上げたいときに便利。
UIがシンプルで、初心者でも扱いやすい点が魅力です。
【無料】生成AIを業務に活用するアイディア集
生成AIは、日々の業務を効率化するだけでなく、アイデアの整理やクリエイティブ作業のサポートにも役立ちます。
ここでは、無料で使える代表的な生成AIツールとその活用アイディアを紹介します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

ChatGPT:議事録の要約、ブレインストーミングの壁打ち相手
ChatGPTは、会議の議事録を自動で要約したり、アイデア出しの際の壁打ち相手として活用できます。
複数の意見や情報を整理し、簡潔で分かりやすい文章にまとめられるため、日常の業務効率を高めるだけでなく思考の整理にも役立ちます。
Google Gemini:スプレッドシートの関数作成、メールの草稿作成
Google Geminiは、スプレッドシートでの複雑な関数作成やデータ整理をサポートします。
また、メールや報告書の草稿を自動生成することもでき、ルーチンワークの負担を大幅に減らすことが可能です。
特に日々の定型作業を効率化したいビジネスパーソンに適しています。
Midjourney:SNS投稿用の画像生成、企画書のイメージ画像作成
Midjourneyは、SNS投稿用の画像や企画書のイメージ図をAIが生成してくれるツールです。
デザインの専門知識がなくても高品質なビジュアルを作成できるため、マーケティングやプレゼン資料の制作に役立ちます。
短時間で複数案を作れる点も大きなメリットです。
Notion AI:ToDoリストの自動作成、日報のテンプレート生成
Notion AIは、業務管理を効率化するための便利なツールです。
ToDoリストを自動で作成したり、日報のテンプレートを生成することで、日々のタスク管理や報告作業をスムーズに進めることができます。
チームでの情報共有や進捗管理にも活用可能です。
業務効率化AIツールの選び方 7つのポイント
AIツールの選定で最も大切なのは、「どんな課題を、どのように解決したいか」が明確であることです。
市場には多くの優れたAIツールが存在しますが、自社に合っていなければ逆に非効率になる可能性もあります。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

1. 解決したい課題と導入目的を明確にする
業務効率化AIツールを導入する際にまず行うべきことは、自社がどのような課題を抱えていて、その課題をAIでどう解決したいのかを明確にすることです。
たとえば、「毎日大量のメール対応に時間を取られている」といった課題がある場合は、自然言語処理に強いAIチャットツールの導入を検討できますし「営業資料の作成に多くの工数がかかっている」というケースでは、生成AIを活用して資料作成を効率化する目的が考えられます。
このように、具体的な課題と目的をセットで洗い出しておくことが、適切なツール選定の出発点となります。
2. 搭載されているAI機能の種類と精度を確認する
AIツールにはさまざまな機能が搭載されており
たとえば
- テキスト生成
- 画像認識
- 音声認識
- データ予測
など、それぞれに得意分野があります。
そのため、自社の業務に必要な機能が備わっているかを見極めることが重要です。
また、単に機能の有無だけでなく、実際の使用においてどれほどの精度を持っているかも確認すべきポイントです。

精度が低いAIを導入してしまうと、かえって人の手間が増えたり、誤った判断に繋がる恐れもあるため、無料トライアルやデモなどで実際の使用感を確かめるのが望ましいでしょう。
3. 既存システムとの連携性を重視する
AIツールを業務にスムーズに取り入れるためには、現在使用している業務システムとの連携性が高いかどうかも非常に重要です。
たとえば、すでに使っているチャットツールやスプレッドシート、クラウドストレージと連携できることで、データの移行や業務フローの変化を最小限に抑えられます。
またAPI連携やWebhook対応の有無、データのインポート・エクスポートの柔軟性などもチェックしておきたいポイントです。
ツール単体の性能だけでなく、全体の業務プロセスの中で自然に組み込めるかという視点で判断することが求められます。
4. 導入・運用コストと費用対効果を比較する
AIツールの導入には、初期費用や月額利用料、追加機能の課金などさまざまなコストがかかります。
しかし重要なのは、単に価格の高低ではなくそれによって得られる効果、すなわち費用対効果をしっかり比較することです。
たとえば、1ヶ月に10時間の作業を削減できるツールであれば、人件費に換算してどの程度のコスト削減になるのか、売上への貢献度はあるのかなどを具体的に試算することが必要です。

短期的なコストだけでなく、長期的に見た運用の持続性やスケーラビリティ(拡張性)も含めて評価することが、失敗しない導入につながります。
5. 操作性とサポート体制を確認する
AIツールの導入後に現場でスムーズに活用されるかどうかは、ユーザーインターフェースのわかりやすさやサポート体制の充実度にかかっています。
直感的に操作できるデザインであるか、専門知識がなくても使いこなせる工夫がされているかといった点は、特にITに不慣れなスタッフが多い職場では重要です。
また、導入時のサポートだけでなく、運用中のトラブルに迅速に対応してくれるかどうか、日本語でのサポートが用意されているかなど、安心して使い続けられる体制が整っているかも確認しておきましょう。
6. セキュリティとデータプライバシーの対策状況
AIツールの多くは業務データや顧客情報を扱うため、セキュリティとデータ保護に関する対策がしっかりされているかは非常に重要です。
たとえば、通信や保存時のデータが暗号化されているか、ツール提供元が信頼できる企業であるか、個人情報保護法(日本国内であればPPCガイドライン)やGDPRなど国際基準に準拠しているかなどをチェックする必要があります。

情報漏えいや不正アクセスのリスクを最小限に抑えるためにも、自社のセキュリティポリシーと照らし合わせたうえでの判断が求められます。
7. 実績と将来性を評価する
最後に、導入を検討しているAIツールの実績や開発企業の将来性についても評価しておくことが大切です。
- 多くの企業での導入実績があるか
- ユーザーからの評価が高いか
- 定期的にアップデートが行われているか
などといった点は、安心して長期的に利用できるかどうかの判断材料になります。
また、開発企業が今後どのようなロードマップを掲げているのか、新機能の追加予定なども確認することで、ツールの成長性や継続性を見極めることができます。
AI活用ツールで業務効率化した企業の事例
AIツールを導入したことで、実際に業務効率化に成功した企業の事例を見てみましょう。
大企業を中心に、さまざまな部門でAIの活用が進んでおり、成果も数字として現れています。
以下では、具体的にどのようなAI活用が行われたのか、企業ごとの取り組みをご紹介します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

三菱UFJ銀行:月22万時間分の労働時間削減を試算
三菱UFJ銀行は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とAIチャットボットを活用して、全社的な業務効率化を進めています。
特に、口座開設や振込などに関する定型業務や、お客様からの問い合わせ対応を自動化することで、月あたり22万時間相当の労働時間を削減できると見積もられています。RPAにより手作業での入力作業が不要になり、人的ミスも大幅に減少しました。

これにより、現場スタッフは顧客対応や提案業務など、より価値の高い仕事に集中できるようになっています。
みずほフィナンシャルグループ:AI-OCRで事務処理の時間を大幅短縮
みずほフィナンシャルグループでは、AI-OCRと機械学習を活用し、手書きや印刷された書類の読み取り・デジタル化を自動化。
これまで人手で行っていた申込書や契約書の確認作業が、AIによって瞬時に処理されるようになり、大量の事務作業を短時間で処理できるようになりました。
特に支店業務やバックオフィスの省力化に効果を発揮しており、ミスの削減とスピード向上の両立を実現しています。
ユニクロ(ファーストリテイリング):AIによる需要予測と在庫管理
ファーストリテイリングは、販売データや気象データ、SNSのトレンド情報をもとに、AIによる需要予測モデルを構築。
それにより、どの店舗にどの商品をどの程度配荷するべきかといった在庫戦略がより正確に行えるようになりました。
この結果、店舗での品切れや在庫過多のリスクが軽減され、販売機会の最大化と在庫コストの最適化を同時に達成しています。

商品の企画サイクルも短縮され、市場の変化に迅速に対応できる体制が整いました。
DINOS CORPORATION:生成AIでLP制作時間を最大8割削減
通販事業を展開するDINOSでは、マーケティングやECサイト運営において、ChatGPTなどの生成AIを活用し、ランディングページ(LP)の作成業務を大幅に効率化しています。
従来はマーケターが1ページごとに構成やコピーを考えていましたが、現在はAIがベースとなる案を即座に提示し、それを元に微調整するだけで済むようになりました。
これにより、LP制作にかかる時間が最大80%削減され、より多くのテスト施策やコンテンツ改善にリソースを回せるようになっています。
セブン‐イレブン・ジャパン:トレンド予測で商品開発スピードを加速
セブン-イレブンでは、SNSやレビューサイトなどから収集した膨大な消費者の声をAIで解析し、いま求められている味や成分、パッケージデザインを把握。
その情報をもとに、商品開発チームが即座に商品企画を進める体制が整っています。
これまで1〜2ヶ月かかっていた市場調査〜商品開発のサイクルが短縮され「トレンドに乗った商品」をタイムリーにリリースできるようになりました。

話題性と売上の両方を兼ね備えた商品が続々と生まれています。
星野リゾート:多言語AIチャットで宿泊予約対応を効率化
星野リゾートでは、宿泊予約時の問い合わせや、館内案内に関する質問対応に、多言語対応のAIチャットボットを導入しています。
これにより、フロント業務の負担が軽減されるだけでなく、外国人観光客への対応もスムーズに行えるようになりました。
また、AIは24時間稼働しており、深夜や休日でも一定の対応が可能。
人手不足が問題となる観光業界において、非常に効果的な効率化施策となっています。
パナソニック コネクト株式会社:AIアシスタントで資料作成や議事録を支援
パナソニック コネクトでは、社内業務の一環として、AIアシスタント(生成AI)を導入。
日報や議事録の自動作成、会議資料の構成案作成などをAIが支援し、社員の事務的作業の負担を軽減しています。
実際に、報告書作成の時間が半減するなどの成果があり、ホワイトカラー職の生産性が大幅に向上。
今後も業務範囲を広げてAI活用を推進する予定です。
業務効率化AIに関するよくある質問


医療や介護、クリエイティブな仕事などはAIに代わりにくい分野です。
これからはAIを使いこなせる人材が求められます。


文章作成の時間を大幅に短縮できるため、業務効率がアップします。
ただし、内容の最終チェックは人が行う必要があります。


次に、データの整理と正確な管理が重要です。
また、社内でAI活用の理解を深め、小さな範囲で試験的に導入するのが成功のポイントです。


対策としては、アクセス権限の管理や利用ルールの徹底、信頼できるツールを選ぶことが大切です。
機密情報は安易にAIに入力しないなどの注意も必要です。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

まとめ
AIを使った業務効率化は今や多くの企業で実践されており、大幅な時間短縮やコスト削減につながっています。
導入の際は、目的や課題を明確にし適したツールを選ぶことが成功の鍵です。
また、セキュリティ対策や社内の理解も欠かせません。
AIをうまく活用すれば、業務の質を高めながら働き方も変えていけるでしょう。

これからのビジネスには、AIを味方にした効率的な働き方がますます求められています。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ


 で
で