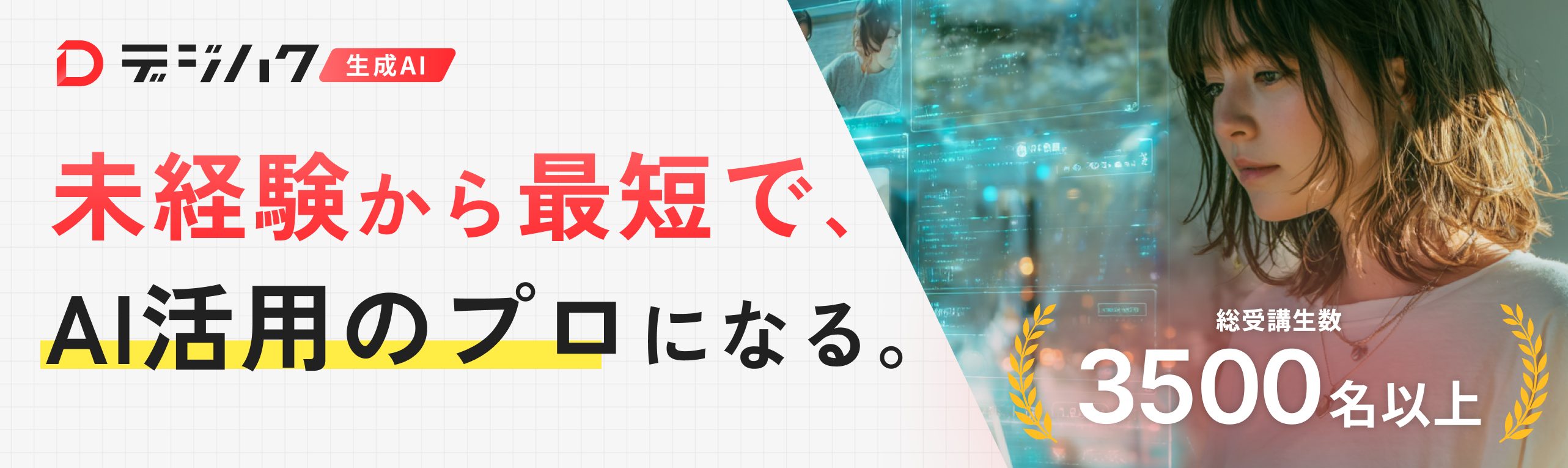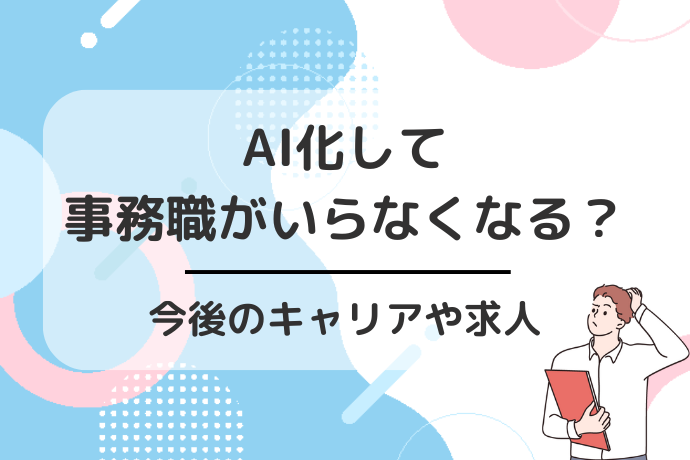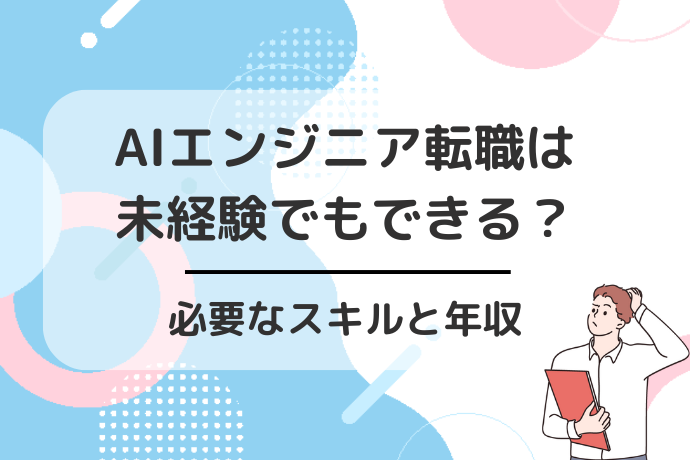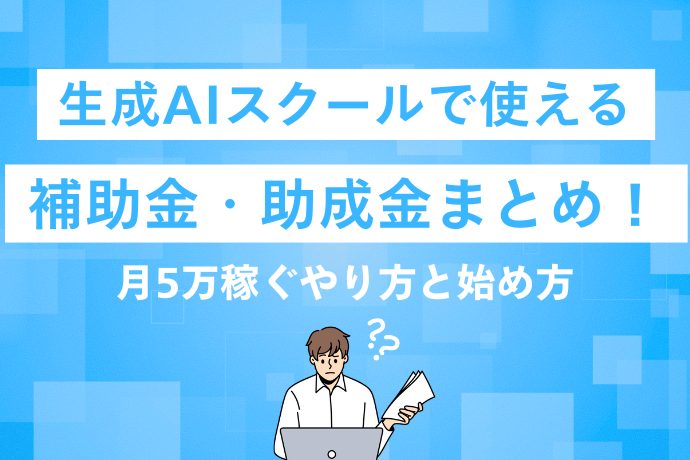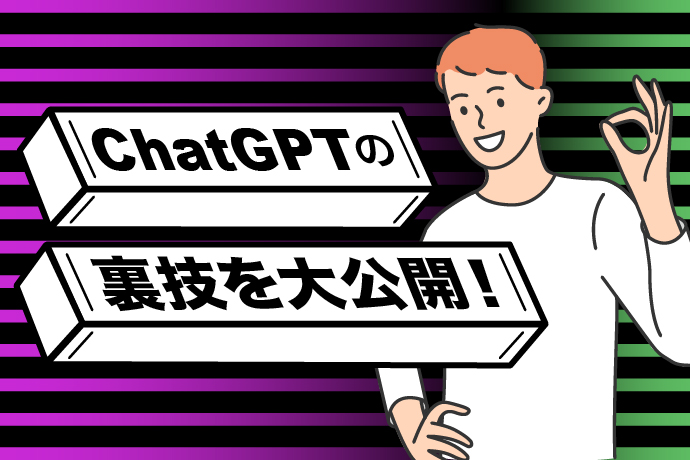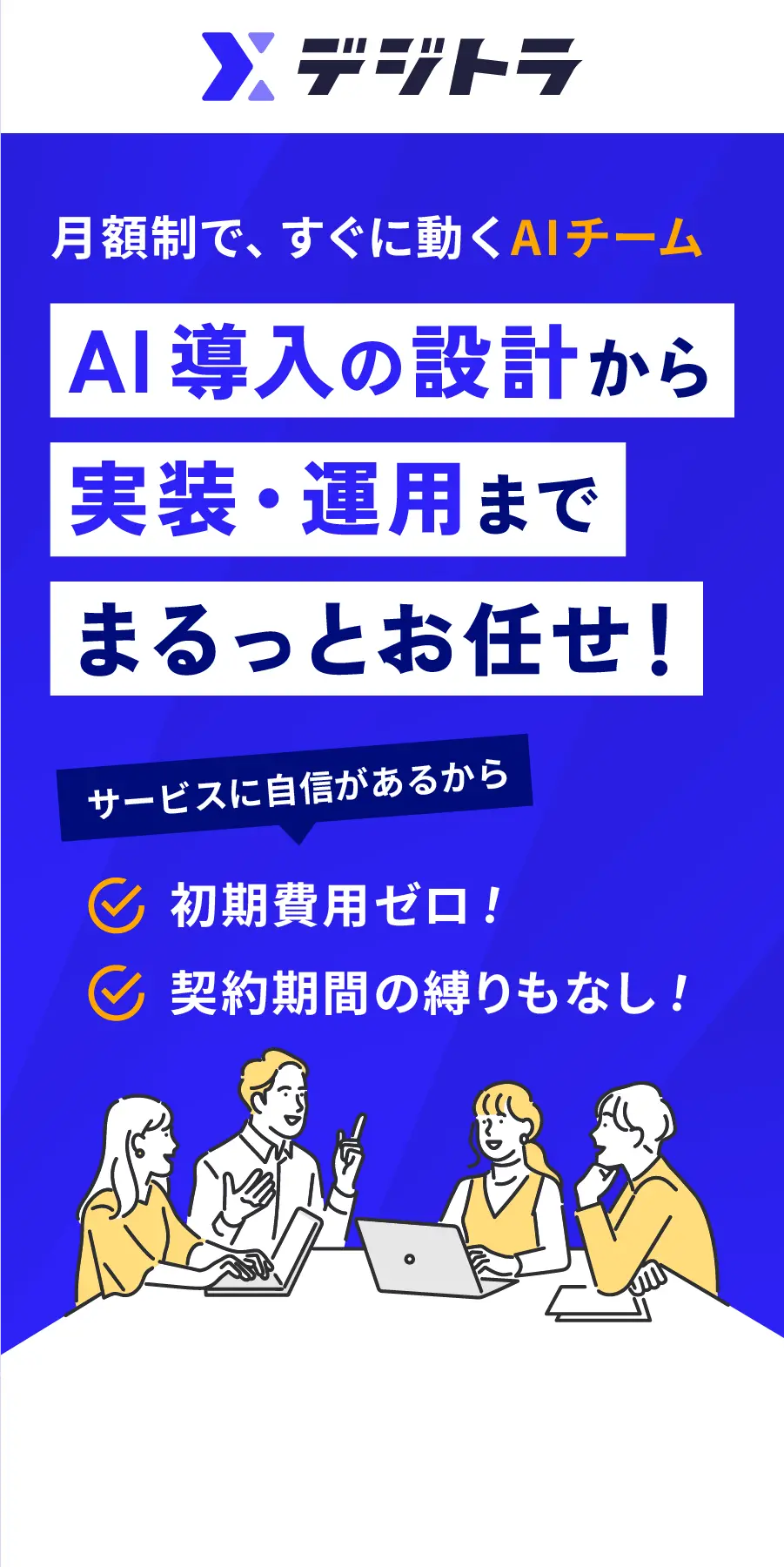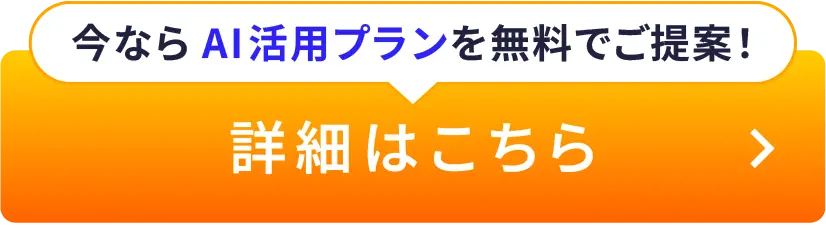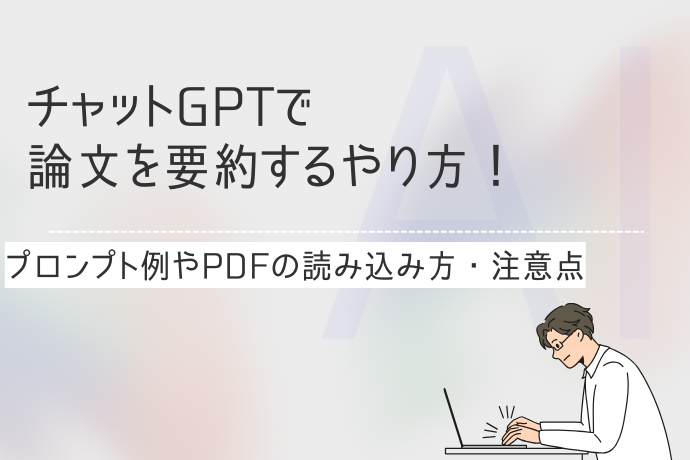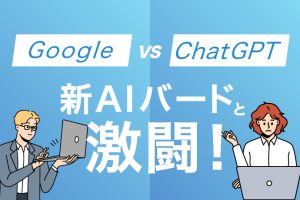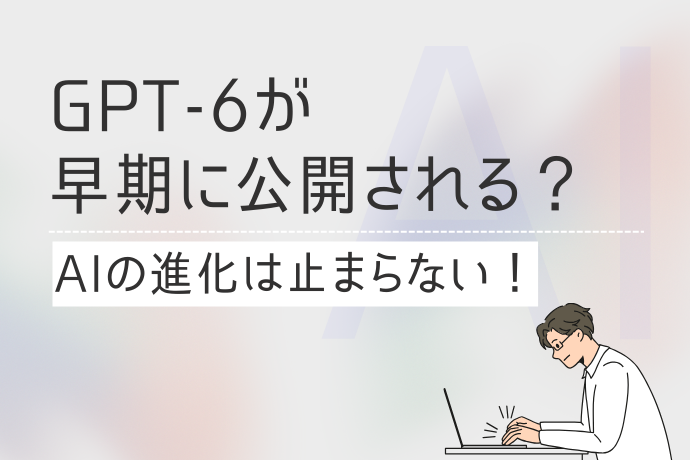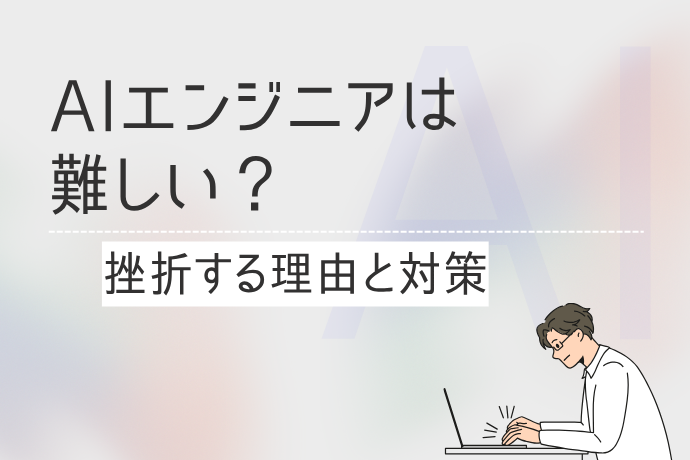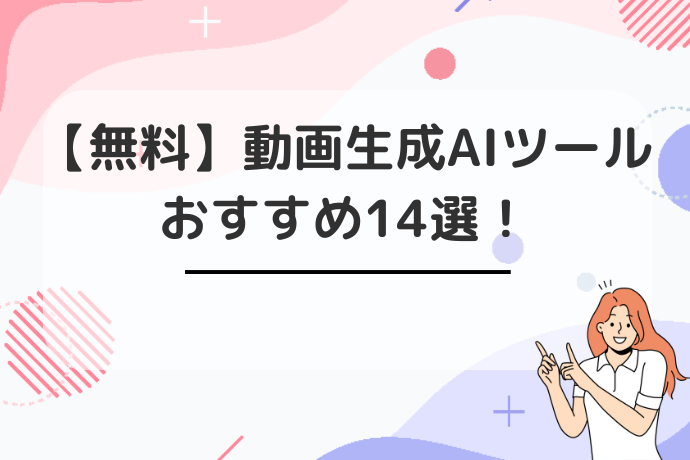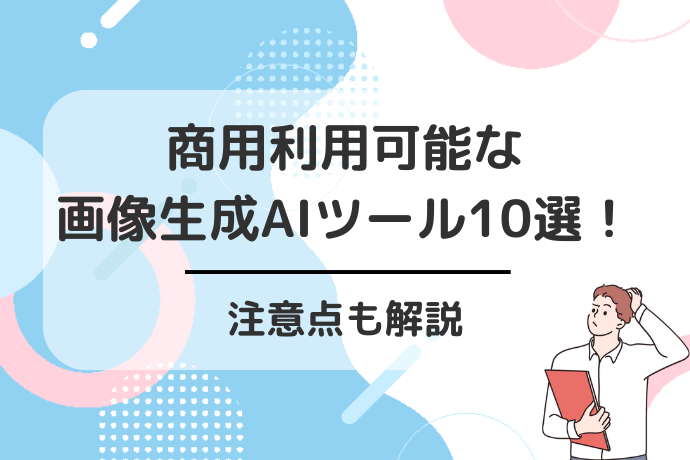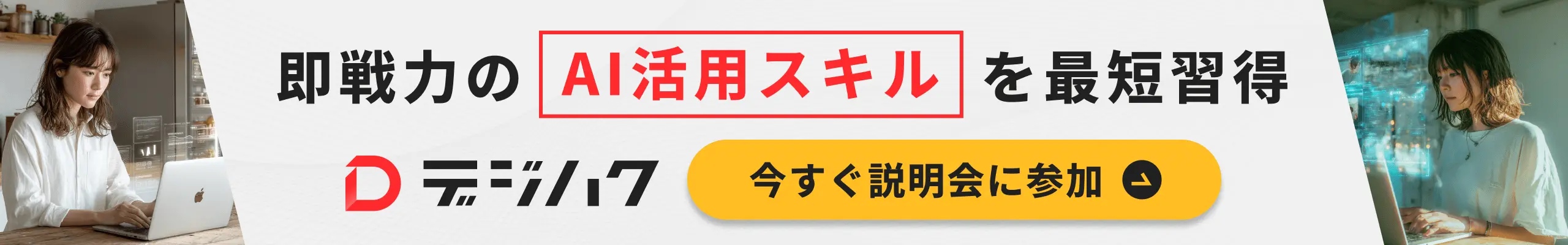書類作成やデータ入力などを日常的にこなす事務職は、AIに代替されやすい職種として話題に上ることが多いです。
しかし実際のところ、すべての事務職がなくなるわけではありません。
むしろ、AIを味方につけることで仕事の幅が広がり、より価値の高い業務に専念できる可能性もあるのです。
本記事では、AIの得意なことや、将来的に代替される可能性の高い仕事、そしてAI時代でも活躍できる事務職のスキルや働き方について解説します。
AI時代に事務職はなくなるのか?AIができること
結論として、事務職は「なくなる」のではなく「変化する」というのが正確な答えです。
とくに事務職のような定型的な業務においては、AIの導入が進みやすい分野といえるでしょう。
AIが得意とするのは、「パターン化された作業」「大量のデータ処理」「高速な情報検索」などです。
たとえば
- データ入力
- 請求書の発行
- スケジュール管理
- メールの自動返信
- 会議の議事録作成
などといった業務は、AIによって効率化・自動化が進んでいます。
最近では、生成AIによって文書作成や翻訳といった知的作業までも自動でこなせるようになりつつあります。

事務職のすべてがAIに奪われるわけではありませんが「繰り返し型の作業」や「ルール化しやすい業務」は、今後AIが担う割合が大きくなることは間違いありません。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

事務職が「AIに奪われる」と言われる3つの理由
事務職がAIに代替されやすいと言われるのには、明確な理由があります。
その理由を理解することで、自分の業務のどこにリスクがあるのかを把握できます。
ここでは、3つの主な理由を解説します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

ルーティンワーク・定型業務が多い
事務職の業務の多くは、決まった手順を繰り返すルーティンワークです。
- 毎日同じフォーマットで書類を作成する
- 決まったルールに従ってデータを入力する。
- マニュアル通りに処理を進める
こうした作業は、一度ルールを設定すれば、AIが人間よりも速く正確に処理できます。
AIは疲れを知らず、ミスもしません。
企業にとっては、人件費削減とヒューマンエラー防止の両方が実現できるため、自動化のメリットは大きいのです。
データ入力・処理はAIの得意分野
AIが最も得意とするのは、大量のデータを高速かつ正確に処理することです。
例えば、1,000件の請求書データを入力する作業を考えてみましょう。
人間なら何時間もかかり、入力ミスのリスクもあります。
しかし、AI-OCR(光学文字認識)を使えば、数分で正確にデータ化できます。
事務職の業務には、このようなデータ処理が多く含まれています。
- 売上データの集計
- 顧客情報の入力・更新
- 在庫数の管理
- 経費の計算・精算
これらはすべて、AIが人間を上回るパフォーマンスを発揮できる領域です。
RPA・業務自動化ツールの普及
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の普及が、事務職への影響を加速させています。
RPAとは、パソコン上の定型作業を自動化するソフトウェアロボットのことです。
人間がマウスやキーボードで行う操作を記録し、自動で再現してくれます。
具体的には、以下のような業務を自動化できます。
- システム間のデータ転記
- 定型メールの送信
- レポートの自動作成
- 勤怠データの集計
RPAは、プログラミングの知識がなくても導入できるため、多くの企業で採用が進んでいます。
事務職がこれまで手作業で行っていた業務が、次々と自動化されているのが現状です。
AIに代替される可能性が高い事務業務10選一覧
ここからは、具体的にどのような事務業務がAIに代替される可能性が高いのかを解説します。
自分の業務がどれくらい影響を受けるか、チェックしてみてください。
ただし、これらの業務が「完全になくなる」のではなく、「自動化により人手が不要になる」と理解しましょう。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

データ入力・転記作業
最も代替されやすいのが、データ入力や転記作業です。
- 紙の書類をExcelに入力する
- あるシステムから別のシステムにデータを移す
といった作業は、AIとRPAの組み合わせで完全に自動化できます。
むしろ、人間がやるよりもミスが減り、処理速度も上がります。
請求書・伝票処理
請求書の受領から仕訳、支払い処理までの一連の流れは、AIで大幅に効率化されています。
AI-OCRが請求書の内容を自動で読み取り、会計システムに連携する。
このような仕組みを導入している企業はすでに多く、経理事務の業務量は確実に減少しています。
経費精算業務
経費精算も、自動化が進んでいる分野です。
領収書をスマホで撮影するだけで
- 金額や日付を自動認識。
- 交通費はICカードの履歴から自動取得
- 上司への申請から承認までオンラインで完結
このようなシステムが普及し、経費精算を担当する事務員の仕事は減少傾向にあります。
定型書類の作成(契約書・稟議書など)
契約書や稟議書など、フォーマットが決まっている書類の作成も自動化が可能です。
テンプレートに必要事項を入力すれば、AIが体裁を整えて書類を生成。
さらに、生成AIを使えば、文章の下書きまで自動で作成できるようになりました。
ファイリング・書類管理
紙の書類をファイリングし、管理する業務は、ペーパーレス化の流れで急速に減少しています。
書類は電子化され、クラウド上で管理。
検索機能を使えば、必要な書類を瞬時に見つけられます。
物理的なファイリング作業は、もはや不要になりつつあります。
電話・メールの一次対応
定型的な問い合わせへの対応は、AIチャットボットや自動音声応答で代替されています。
「営業時間は何時ですか?」「商品の在庫はありますか?」といった質問は、AIが24時間対応。
事務職は、AIでは対応できない複雑な問い合わせのみを担当する形に変わりつつあります。
スケジュール調整・会議室予約
会議の日程調整や会議室の予約も、自動化が進んでいる業務です。
- 参加者の空き時間を自動で検索し、最適な日時を提案
- 会議室の空き状況を確認し、自動で予約
こうした作業は、すでに多くの企業でシステム化されています。
在庫管理・発注業務
在庫の管理と発注業務は、AIによる自動化の恩恵を大きく受けている分野です。
AIが過去の販売データを分析し、適正在庫を予測。

在庫が基準値を下回ると自動で発注をかける、人間が在庫を数えて発注書を作成するという作業は減少しています。
給与計算・勤怠管理
給与計算や勤怠管理は、クラウドシステムの普及で大幅に効率化されました。
- 従業員がスマホで打刻し、残業時間を自動集計
- 給与計算も、設定したルールに基づいて自動で処理
人間の手作業が必要な部分は、ほとんどなくなっています。
レポート・集計資料の作成
定型的なレポートや集計資料の作成も、自動化が可能です。
売上データを集計し、グラフ化してレポートを作成。
この一連の流れを、AIとExcelマクロの組み合わせで自動処理できます。
毎週・毎月同じレポートを手作業で作る必要はなくなりつつあります。
AI時代でも残り続ける事務業務8選一覧
AIに代替されにくい事務業務も、確実に存在します。
これらの業務は、人間特有のスキルが求められるため、AI時代でも価値を持ち続けます。
自分の業務がこれらに該当するか確認し、強みとして伸ばしていきましょう。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

社内外との調整・折衝業務
複数の関係者の利害を調整し、合意を形成する業務は、AIには難しい領域です。
部署間で意見が対立している場面を想像してみてください。
相手の立場を理解し、妥協点を探り、全員が納得できる落としどころを見つける。
こうした「人間関係の調整」は、AIには真似できません。
イレギュラー対応・トラブル処理
予想外の事態に対応する能力は、人間の強みです。
AIは過去のデータに基づいてパターン化された対応はできますが、初めて遭遇する問題には対処できません。
「マニュアルにない」状況で、臨機応変に最善の判断を下せるのは人間だけです。
来客対応・接遇
来客へのおもてなしや接遇は、人間ならではの業務です。
- 相手の表情や雰囲気を読み取り、適切な対応をする
- VIPには特別な配慮をし、急いでいる方にはスピーディーに対応する

こうした細やかな気配りは、AIには難しいのが現状です。
経営判断に関わる資料作成・分析
単なるデータ集計ではなく、経営判断に影響を与える資料作成は、人間の知見が必要です。
- データの背景にある意味を解釈し、経営陣に分かりやすく伝える
- 「このデータは何を示しているのか」「どのような打ち手が必要か」を考える
データを「情報」に変換する作業は、人間の役割です。
社員のサポート・相談対応
社員からの相談に乗り、サポートする業務は、共感力が求められます。
「仕事の進め方で悩んでいる」「人間関係がうまくいかない」といった相談は、AIでは対応できません。
相手の気持ちに寄り添い、一緒に解決策を考える姿勢が大切です。
AIツールの運用・管理
皮肉なことに、AIを導入するほど「AIを管理する人間」が必要になります。
- AIツールの設定
- エラー対応
- 結果のチェック
- 改善提案
これらは人間が担う役割であり、むしろAI時代に需要が高まる業務といえます。
業務改善・効率化の提案
現状の業務を分析し、改善策を提案する能力は、人間の強みです。
- 「この作業は無駄ではないか」「もっと効率的なやり方はないか」と考える
- 具体的な改善案を立案し、実行に移す
AIは指示されたことを実行しますが、「何を改善すべきか」を自分で考えることはできません。
部署間の橋渡し・情報共有
異なる部署の間に立ち、情報の橋渡しをする役割は、コミュニケーション能力が求められます。
- 営業部門と製造部門の板挟みになりながら、双方の要望を調整する
- 経営陣の意向を現場に伝え、現場の声を経営陣に届ける

[sc name="ai-cta"][/sc]
AI導入で事務職の求人は減るの?
AIの導入が進むことで、事務職の求人は確かに一部で減少傾向にあります。
とくに、単純作業が中心だった従来型の事務職ポジションは自動化の影響を受けやすくなっています。
たとえば、バックオフィス業務の多くをAIで処理できるようになれば、企業は人件費を抑えつつ業務を回せるようになるため「人手を減らしても問題がない」と判断するケースが増えるのです。
しかし「すべての事務職が不要になる」というわけではありません。
むしろ、AIをうまく活用できる人材や、業務フローの改善に関与できる事務スタッフへのニーズは高まっています。
今後は「AIに置き換えられる事務職」と「AIを使いこなす事務職」に二極化していくと考えられます。

求人全体の数は減少するかもしれませんが、その分「価値あるスキルを持つ事務職」に対する需要は着実に伸びていくでしょう。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

事務職がAIを活用する方法
AIは「一部の専門職だけが使うもの」ではなく、今や一般的な事務職にとっても身近な存在となりつつあります。
特に最近では、簡単に使えるAIツールが数多く登場し、日々の業務を効率化するための強力な味方になっています。
たとえば、以下のような活用方法があります。
- 文書作成補助:ChatGPTなどの生成AIを使えば、定型文や案内文を素早く作成可能です。
- データ整理・分析:スプレッドシートと連携して、数値の傾向を自動でまとめたり、グラフ化したりできます。
- スケジュール調整:AIがメールのやり取りをもとに、候補日程を提案してくれるツールもあります。
- 議事録の自動作成:会議の録音をもとに文字起こしし、議事録を自動生成するアプリも便利です。
このように、AIをうまく使えば「時間のかかる作業」にかける手間を大幅に削減でき、より重要な仕事に集中することが可能になります。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

事務職がAIツールを「使いこなす」とはどういうこと?
AIツールを「使いこなす」とは、単にボタンを押して結果を得ることではありません。
重要なのは「どの場面でAIを使えば効果的か」を判断し「よりよい結果を得るために工夫する力」を持つことです。
たとえば、ChatGPTに「会議のお礼メールを作って」と依頼するだけでなく
- 「社外向けで丁寧に」
- 「上司に確認済みの内容を含めて」
など、適切な指示(プロンプト)を出せるかどうかが成果を大きく左右します。
また、AIが出力した結果をそのまま使うのではなく、内容をチェック・修正する力も必要です。
AIの出力には誤りや不適切な表現が含まれる場合もあるため、人の目による最終確認が欠かせません。

つまり「使いこなす」とは、AIに任せる部分と自分で判断すべき部分を見極めながら、業務の質とスピードを同時に高めていく力を持つことなのです。
AI時代に事務職として生き残るための5つのスキル
AI時代でも必要とされる事務職になるためには、戦略的にスキルを磨く必要があります。
ここでは、特に重要な5つのスキルを解説します。
これらのスキルを身につければ、AIに仕事を奪われるどころか、むしろ市場価値が高まります。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

コミュニケーション能力(AIが最も苦手な領域)
コミュニケーション能力は、AI時代に最も価値が高まるスキルです。
AIは言葉の裏を読んだり、相手の気持ちを察したりすることができません。
「空気を読む」「察する」「配慮する」といった日本的なコミュニケーションは、人間にしかできない領域です。
具体的には、以下のような能力を磨きましょう。
- 相手の立場に立って物事を考える力
- 複雑な内容を分かりやすく伝える力
- 異なる意見を調整し、合意を形成する力
- 信頼関係を築き、維持する力
臨機応変な対応力・問題解決能力
予期せぬ事態に柔軟に対応する力は、人間の強みです。
AIは過去のデータに基づいてパターン認識を行いますが、新しい状況には対応できません。
「マニュアルにない」「前例がない」という場面で、最善の判断を下せる人材は重宝されます。
日頃から「なぜこうなっているのか」「もし〇〇だったらどうするか」と考える習慣をつけましょう。
AIツールを使いこなすITリテラシー
「AIに仕事を奪われる側」ではなく、「AIを使いこなす側」になることが重要です。
ChatGPTをはじめとする生成AIは、正しく使えば業務効率を大幅に向上させます。
AIツールを活用できる事務職と、活用できない事務職では、生産性に大きな差が生まれます。
以下のようなスキルを身につけましょう。
- 生成AI(ChatGPT、Copilotなど)の活用
- Excel関数・マクロの活用
- RPAツールの基本操作
- クラウドサービスの活用
業務改善・効率化を提案する力
現状の業務を分析し、改善策を提案できる人材は、AI時代に需要が高まります。
「この作業は本当に必要か」「もっと効率的なやり方はないか」と常に考える。 そして、具体的な改善案を上司に提案し、実行に移す。
受け身で指示を待つだけの事務職は淘汰されますが、自ら考えて動ける事務職は、組織にとって欠かせない存在になります。

これは、現場の視点を持った提案力とも言えるでしょう。
専門性(経理・人事・法務など)
特定の分野で専門性を持つことで、AIに代替されにくくなります。
一般事務よりも、経理、人事、法務、貿易事務などの専門事務の方が、AIに代替されにくい傾向があります。
なぜなら、専門知識がなければAIの出した結果が正しいかどうかを判断できないからです。
以下のような資格取得も検討してみましょう。
- 貿易実務検定(貿易事務)
- 日商簿記(経理・会計)
- 社会保険労務士(人事・労務)
- 宅地建物取引士(不動産事務)
事務職がAIスキルを学ぶメリット
事務職の業務といえば、書類作成やデータ入力、スケジュール管理などのルーチンワークが中心という印象が強いかもしれません。
しかし、AIが進化した今、事務職の方がAIスキルを学ぶことには大きなメリットがあります。
ただの「便利な道具」として使うだけでなく、スキルとしてAIを身につけることでキャリアにも収入にも良い影響が期待できます。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

業務の効率化・生産性アップ
AIスキルを持つことで、日々のルーチンワークを自動化できるようになります。
たとえば、定型文のメール返信やExcelでのデータ集計なども、AIやマクロを活用すれば短時間で完了できます。
単純作業にかける時間を減らし、本来の業務や人とのやり取りに集中できるようになるのは大きなメリットです。
「AIを使える人材」として社内評価が上がる
AIツールを活用できる人材は、社内での評価も高まりやすくなります。
特に、他の社員がAIを使いこなせていない職場であれば、ちょっとした自動化や効率化の提案だけでも「頼りにされる存在」になれます。
昇進や異動のチャンスにもつながる可能性があります。
転職やキャリアチェンジに強くなる
AIスキルを持っていると、事務職の中でも「ITリテラシーが高い人材」として市場価値が上がります。
近年は「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を進める企業が増えているため、AIやデータ活用に強い人材への需要は右肩上がりです。

転職活動でも有利になり、より待遇の良い職場へのステップアップが期待できます。
単なる事務作業からの脱却ができる
AIスキルを身につけることで「言われたことをこなすだけ」の事務職から脱却し、より主体的に業務に関わることができます。
たとえば、業務改善の提案をしたり、社内でAIツールの使い方を教える立場になったりとよりクリエイティブで価値ある仕事ができるようになります。
将来の不安を減らせる
「AIに仕事を奪われるのでは?」という不安を抱えている方も多いかもしれません。
しかし、AIスキルを持つことでその不安を解消し「AIと一緒に働ける人材」へと進化できます。

変化の激しい時代だからこそ、知識を身につけておくことで自分のキャリアを自分で守る力になります。
生成AIを使いこなす指示出しスキル
生成AI(ChatGPTやCopilotなど)をうまく活用するには「何をどう指示するか」が非常に重要です。
曖昧な命令では意図通りの結果を得ることが難しくなるため、目的を明確にし必要な情報や前提条件をわかりやすく伝える力=「プロンプトスキル(指示出しスキル)」が求められます。
これは事務職だけでなく、あらゆる職種での生産性に直結する能力です。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

データ分析スキル
生成AIやAIツールを使う上で、データを読み解く力は欠かせません。
例えば売上データやアンケート結果をAIに分析させても、結果を正しく理解し、判断材料にできなければ意味がありません。
統計の基礎知識やExcelでのデータ処理スキルを身につけることで、AIが出力した情報の価値を最大限に活かせます。
コミュニケーション能力・協調性
AIはあくまで「ツール」であり、業務は最終的に人と人との連携で成り立っています。
AIを導入する際には、チームメンバーや他部署と連携しながら使い方を共有したり、課題を一緒に解決する必要があります。
AI活用を促進するには、社内での協調や説明能力も非常に重要です。
AIで解決すべき課題を見つける
AIは万能ではなく、「何をAIに任せるべきか」「どの業務を自動化すべきか」という判断が求められます。
そのためには、日々の業務において「これはもっと効率化できそう」「この作業は時間がかかっている」といった視点を持ち、課題を発見する力が必要です。

AIの導入そのものよりも、「どのように使うか」が成果を左右します。
企画力・提案力
AIを活用して成果を出すには、既存のやり方にとらわれず、新しい方法を考え出す力=企画力が必要です。
また、AI導入や活用アイデアを上司やチームに提案する場面も増えていきます。
その際には「なぜこのAIを使うのか」「どんな効果があるのか」をロジカルに説明できる提案力も重要です。
非定型業務への対応力・クリエイティブ思考
AIは定型的な作業は得意ですが、イレギュラーな対応や発想を要する場面はまだ人間にしかできません。
たとえば、顧客とのやり取りで微妙なニュアンスを読み取ったり、新たな企画を立てたりするような非定型業務では、人間の柔軟な思考が求められます。

生成AIを使いながらも「人にしかできないこと」に強みを持つことが、今後ますます重要になります。
事務職がAIを学ぶなら何から始める? 学習ロードマップ
AIと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、事務職でも基礎から順を追って学べば、実務に役立つAIスキルを無理なく習得できます。
ここでは、まったくの初心者がAI活用できるようになるまでの学習ステップを紹介します。
AIや生成AIの基本を知る
ChatGPTやGoogle Geminiなどの生成AIを触ってみるだけでも十分です。
「AIって実際にこんなことができるんだ」という体験から始めることで、学ぶ目的がはっきりしてきます。
業務で使えるAIツールを試す
最近では、Microsoft CopilotやNotion AI、Google WorkspaceのAIアシストなど、実務にすぐ活かせるサービスが豊富にあります。
AIを活かすための「指示出し(プロンプト)」を学ぶ
業務で実用的に使うためには、「どう質問するか」「どういう目的で使うか」といったプロンプト設計のスキルがカギになります。
PythonなどAIの裏側を学んでみる
簡単なコードを書いてみることで、AIの仕組みや動作がより深く理解でき、より高度な活用ができるようになります。
自分の業務にどう活かせるか考える
業務の中で時間がかかっている作業、ルーチンになっている作業を洗い出し「ここはAIで効率化できそうだな」と思える部分を見つけていきます。
このように、まずは「触ってみる」ことから始めて、徐々に応用・自動化へとステップアップするのが事務職にとって現実的かつ効果的なAI学習の道のりです。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

事務職でAIを導入する際の注意点やデメリット
AIを導入することで業務効率が大幅に向上する一方で、導入にはいくつかの注意点や課題もあります。
特に事務職では、日々の業務との兼ね合いや組織全体の理解・協力が不可欠です。
以下に、導入時に考慮すべき代表的なポイントを詳しく解説します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

初期コストと運用コストがかかる
AI導入には、導入時の初期費用だけでなく継続的に発生する運用コストも無視できません。
たとえば、AIツールやプラットフォームを導入する場合、有料ライセンスやクラウド利用料が発生します。
また、ツールを社内に適切に定着させるために、マニュアル整備や社員向けの研修も必要です。
一見便利そうなAIでも、無料で使える範囲には制限があることが多く、本格的に業務へ組み込むには一定の予算が求められます。
コスト対効果をきちんとシミュレーションした上で導入判断を行いましょう。
既存の業務工程を根本から見直す必要がある
AIを導入する際に陥りがちなのが「今の業務をそのままAIに置き換えようとする」ことです。
実際には、AIはあくまでツールであり、使い方次第で成果が大きく変わります。
例えば、書類作成やデータ入力をAIで効率化したい場合、従来のフローをそのまま維持するのではなく「どのタイミングでAIを使えば効果的か」「どこは人の手でやるべきか」を再設計する必要があります。
つまり、AI導入は単なるツールの追加ではなく「業務の再構築」なのです。

導入前には業務の棚卸しと見直しが欠かせません。
データの質と管理が重要
AIの判断や出力の精度は、もととなる「データの質」に大きく左右されます。
例えば、AIが顧客対応の履歴を分析してメールの返信を提案するような場面では、過去の対応履歴に誤字や偏りがあると、AIの出力にも影響が出てしまいます。
また、業務データの保管場所や管理ルールが曖昧な状態では、AIに正しい情報を渡すことが難しくなります。
これまで以上に「データの整備・管理能力」が求められる時代になります。
全社員に新たなスキルが求められる
AIを業務で活用するには、特定のエンジニアや担当者だけでなく、実際に日常業務で使う「現場の社員」全員が一定のAIリテラシーを持つことが必要です。
具体的には
- チャットボットへの適切なプロンプト入力
- データの読み取りと活用
- 出力された内容の評価・修正 など
AIを使いこなすには、最低限のITリテラシーや業務に沿った判断力が求められます。

逆に言えば、AI活用を成功させる鍵は社員一人ひとりの「使う力」にかかっているともいえます。
AIは万能ではないことを理解しておく
AIは非常に優れたツールですが、すべての仕事に対応できるわけではありません。
たとえば、感情を伴うコミュニケーションや複雑な状況判断、臨機応変な対応などは、まだまだ人間の判断が必要です。
また、AIは間違いを起こす可能性もあるため「常に正しい」と過信してしまうのは危険です。
AIを導入したからといってすべてを任せきりにせず、最終的なチェックや意思決定は人間が行うというバランスが求められます。
事務職がAIを味方につける!業務効率化の活用術
AIは敵ではなく、味方につけるべき存在です。
AIツールを活用すれば、面倒な作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できます。
ここでは、事務職がすぐに実践できるAI活用術を紹介します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

ChatGPTで文書作成・メール対応を効率化
ChatGPTは、文書作成の強力なパートナーになります。
例えば、以下のような使い方ができます。
- メールの下書き作成
- 議事録の要約
- 企画書のアイデア出し
- マニュアルの文章校正
- 敬語や表現のチェック
ゼロから文章を書く時間を大幅に短縮できます。
AIが作成した下書きを、人間がブラッシュアップするという使い方がおすすめです。
Excel×AIで集計・分析作業を自動化
Excelと生成AIを組み合わせれば、集計作業が劇的に効率化します。
「このデータをピボットテーブルで集計したい」とChatGPTに伝えれば、手順を教えてくれます。
複雑な関数も、「こういう計算がしたい」と説明すれば、最適な関数を提案してくれます。
また、Microsoft 365のCopilotを使えば、Excel上で直接AIの支援を受けられます。
RPAで定型業務を自動処理
RPAを活用すれば、毎日繰り返している定型業務を自動化できます。
例えば、以下のような作業が自動化の対象になります。
- 毎朝の売上データダウンロード
- 複数システム間のデータ転記
- 定型フォーマットへのデータ入力
- 定例レポートの作成・送信
最初の設定には時間がかかりますが、一度自動化すれば、毎日の作業時間を大幅に削減できます。
AI-OCRで紙書類のデータ化を効率化
AI-OCR(光学文字認識)を使えば、紙の書類を簡単にデータ化できます。
- 請求書
- 領収書
- 名刺
- 契約書
など、紙で届く書類をスキャンするだけで、テキストデータとして取り込めます。
手入力と比べて、作業時間は10分の1以下になることも珍しくありません。
AIチャットボットで社内問い合わせを削減
社内からの定型的な問い合わせは、AIチャットボットに任せましょう。
「有給休暇の申請方法は?」「経費精算の締め日はいつ?」といったよくある質問は、チャットボットが自動回答。
事務職は、AIでは対応できない複雑な問い合わせに集中できます。
問い合わせ対応の時間が減れば、より付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。
AI時代でも活躍できる事務職のキャリアパス
AI時代の事務職には、複数のキャリアパスがあります。
自分の強みや興味に合わせて、最適な方向性を選びましょう。
ここでは、代表的な4つのキャリアパスを紹介します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

専門事務職へのキャリアアップ(経理・人事・法務)
一般事務から専門事務へキャリアアップする道があります。
- 経理事務
- 人事事務
- 法務事務
- 貿易事務
など、専門知識が求められる分野は、AIに代替されにくい傾向があります。
専門性を持つことで、市場価値を高められます。
資格取得を通じて専門知識を身につけ、専門事務職へのキャリアアップを目指しましょう。
DX推進・業務改善担当へのキャリアチェンジ
事務の経験を活かして、DX推進や業務改善の担当者になる道もあります。
現場の業務を熟知している事務職は、「どこを自動化すべきか」「どんなツールが必要か」を判断できる立場にあります。
この知見を活かして、会社全体の業務効率化を推進する役割を担えます。
今、多くの企業がDX人材を求めています。
事務経験+ITスキルを持つ人材は、非常に重宝されます。
AIを活用したバックオフィスのスペシャリスト
AIツールを使いこなし、バックオフィス業務を効率化するスペシャリストになる道もあります。
AIの導入・運用・改善を担当し、組織全体の生産性向上に貢献する。
これは、AI時代に新しく生まれる役割であり、需要は今後も高まるでしょう。
事務スキルを活かした他職種への転職
事務職で培ったスキルは、他の職種でも活かせます。
- Webデザイナー・動画編集者:クリエイティブな仕事はAIに代替されにくい
- カスタマーサクセス:コミュニケーション能力を活かせる
- マーケティング:データ分析スキルを活かせる
- プロジェクトマネージャー:調整力を活かせる
事務職からのキャリアチェンジは、決して珍しいことではありません。
新しいスキルを身につければ、可能性は大きく広がります。
AI時代に必要なスキルを身につけるならデジハクがおすすめ
「AI時代に必要なスキルを身につけたい」「事務職から新しいキャリアを築きたい」という方には、デジハクでの学習をおすすめします。
デジハクは、未経験からでも実践的なスキルを習得できるオンラインスクールです。
ここでは、デジハクが事務職におすすめな理由を紹介します。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

デジハクが事務職におすすめな3つの理由
①未経験からでも安心して学べる
デジハクのカリキュラムは、完全未経験の方でも無理なく学べるように設計されています。
専門用語も分かりやすく解説し、ステップバイステップで進められるので「自分にできるか不安」という方でも安心です。
②実践的なスキルが身につく
座学だけでなく、実際に手を動かして学ぶ実践型のカリキュラムです。
学んだスキルをすぐに仕事に活かせるよう、実務を想定した課題に取り組みます。
事務職をしながらでも、隙間時間で効率的に学習できます。
③充実したサポート体制
学習中に分からないことがあっても、プロの講師にいつでも質問できます。
一人で悩まず、スムーズに学習を進められる環境が整っています。
挫折しにくい仕組みが、デジハクの強みです。
事務職から新しいキャリアを築いた受講生の声
実際にデジハクで学んだ事務職経験者からは、以下のような声が寄せられています。
- 「事務職をしながら動画編集を学び、副業で月5万円を稼げるようになりました」
- 「Webデザインのスキルを身につけて、制作会社への転職に成功しました」
- 「AIツールの活用法も学べて、本業の事務作業も効率化できました」
事務職の経験は、新しいキャリアを築く上でも必ず活きてきます。
今の仕事を続けながらスキルアップし、将来の選択肢を広げませんか?
無料説明会で自分に合った学習プランを相談
デジハクでは、無料説明会を開催しています。
「自分に合ったコースが分からない」「本当に続けられるか不安」という方も、まずは気軽にご相談ください。
専門のカウンセラーが、あなたの状況や目標に合わせた学習プランをご提案します。
AI時代を生き抜くための第一歩を、今日から踏み出しましょう。
AI事務職に関するよくある質問




AIツールは使いやすく、学ぶ意欲があれば問題ありません。






AIの文章を参考に、自分の言葉で書き直しましょう。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

まとめ
AIの進化により、事務職の働き方は大きく変わりつつあります。
単純な作業はAIに任せる一方で、AIを活用して効率を高めるスキルが求められています。
AI時代でも、人間ならではのコミュニケーション能力や問題解決力、企画力が重要です。
新しい技術を積極的に学び、変化に柔軟に対応することで、事務職としての価値を高めていけるでしょう。

AIを味方にしながら、これからの時代を生き抜く力を身につけていきましょう。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ


 で
で