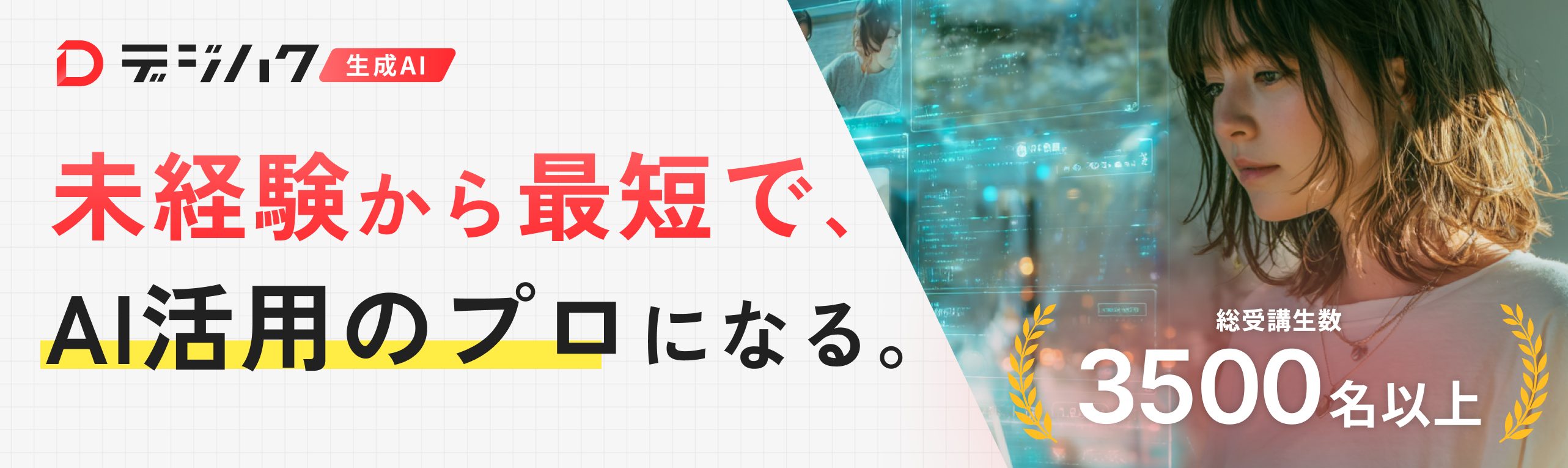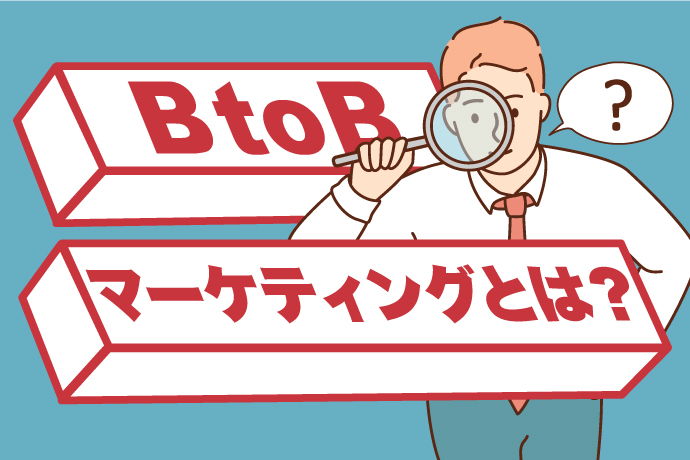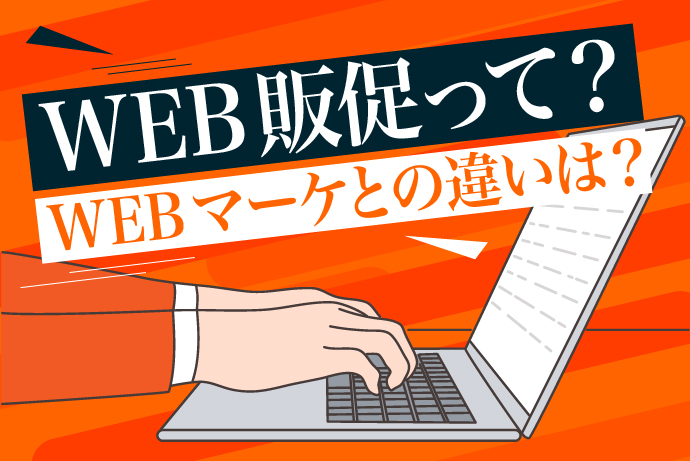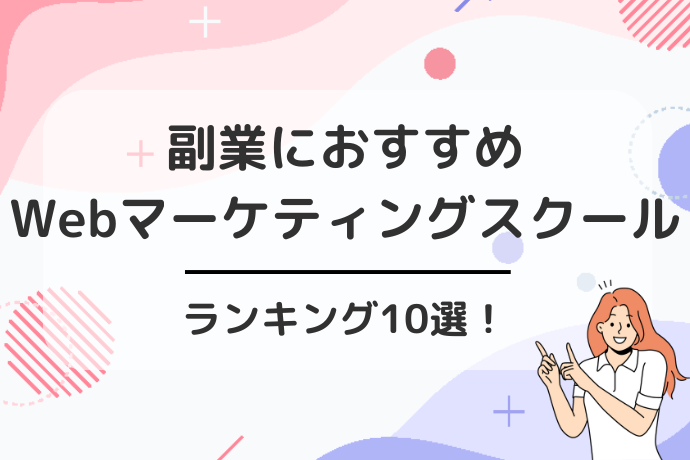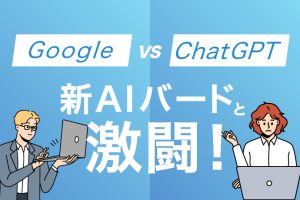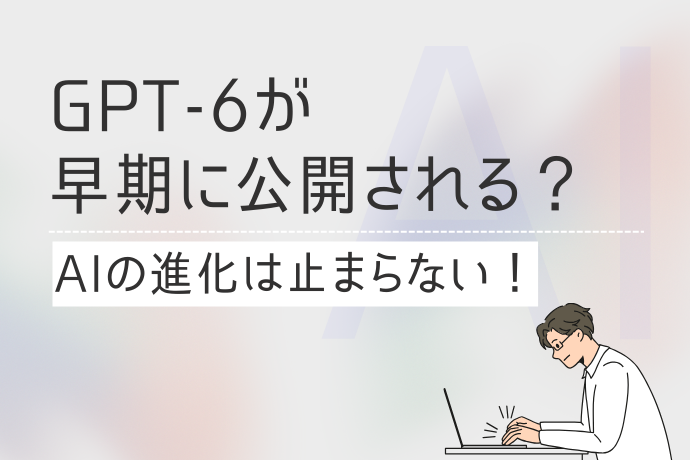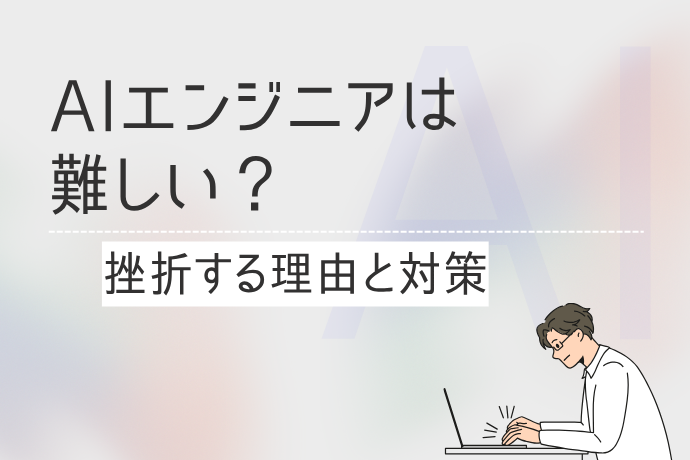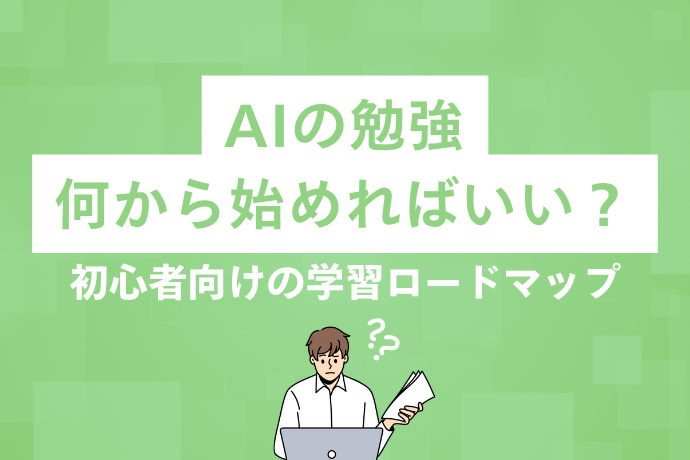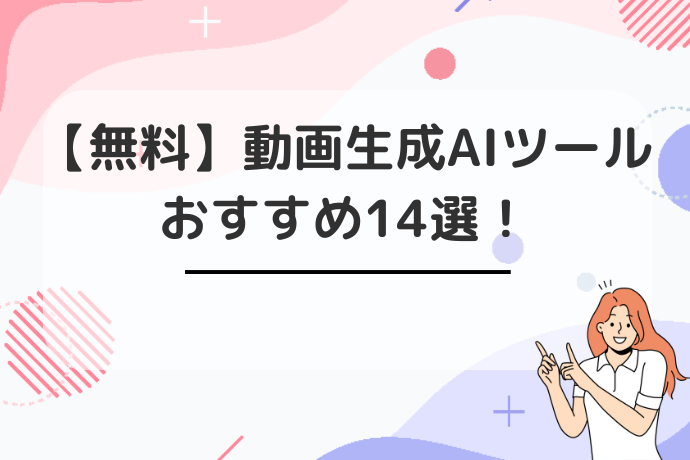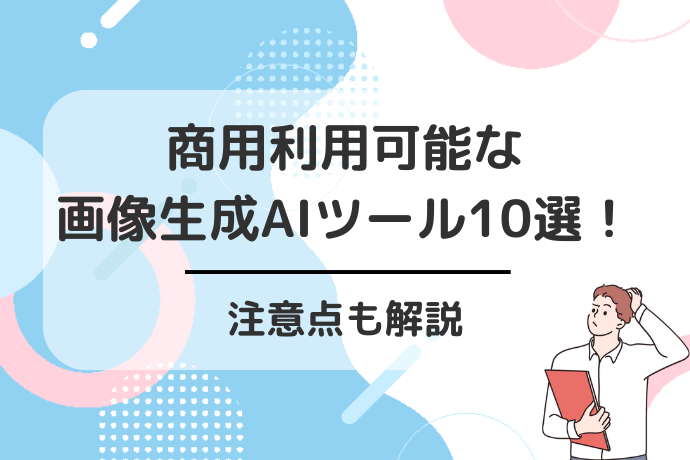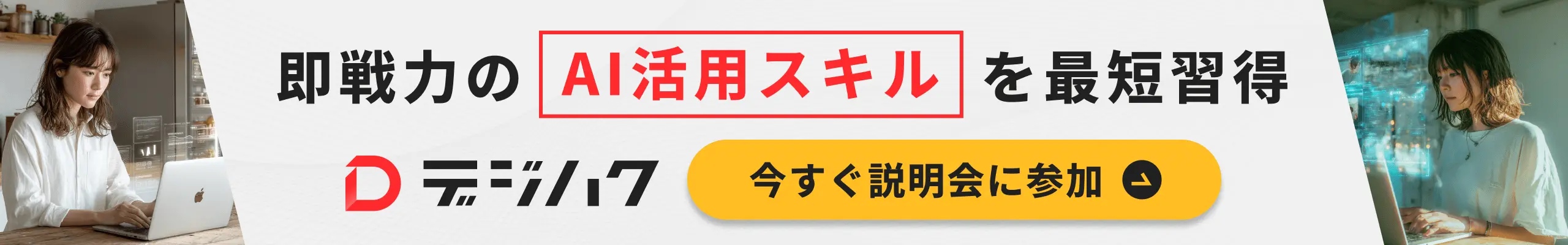この記事でわかること
- ファンマーケティングの手法
- ファンマーケティングの成功事例
- ファンマーケティングのメリット・デメリット
- ファンマーケティングに必要なツール
従来のマーケティングでは顧客獲得や新商品の開発が上手くいかなくなってきています。
インターネットの発展により顧客は商品やサービスを購入する際、複数のメディアで比較検討ができるようになったからです。
そこで生まれたのが「ファンマーケティング」です。
本記事ではファンマーケティングの基礎知識から成功させるためのコツを解説します。
ファンマーケティングを実践することで、売上や成約の成果につながるでしょう。
マーケティングが思い通りにいっていないと感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ファンマーケティングの基本定義

ファンマーケティングの意味や需要についてお話していきます。
ファンマーケティングとは
ファンマーケティングとは、強い信頼関係のある顧客をメインターゲットとした販売戦略のことです。
顧客に商品やサービスに対して共感や愛着を持ってもらい、応援する気持ちや熱意を購入意欲としたマーケティングです。
顧客が個人や企業のファンになる社会
従来のマーケティングでは、宣伝費をかけて不特定多数の顧客に商品やサービスを販売する手法が主流でした。
しかし近年では顧客がインターネットを通して自由に情報を集めたり、多くの企業で似たような商品が販売されたりしています。
そのため、顧客一人ひとりが商品やサービスの比較検討を自由に行えるようになりました。
ファンマーケティングの今後の市場価値とは
顧客が商品やサービスを購入する理由が「好きだから」のような趣味嗜好が重要視されるようになったため、ひとつの市場の独占が難しくなりました。
顧客が商品を購入するプロセスや動機が変わり、「広く浅く」のマーケティングではなく特定のファンに絞った「狭く深く」のマーケティングが主流になったことで、ファンマーケティングが注目されています。
ファンマーケティングのメリット3つ

ファンマーケティングを実践するにはいくつか理由があります。
ここでは、ファンマーケティングのメリットを3つ紹介します。
具体的には以下のとおりです。
- 広告費を抑えられる
- 効率よく売上が伸ばせる
- ユーザーニーズに沿ったPDCAが回せる
それぞれ見ていきましょう。
広告費を抑えられる
ファンマーケティングは広告費を抑えられます。
購入希望者は、商品やサービスの特徴を知るために情報を探しますが、購入前にチェックするのがSNSの口コミや評判です。
そして口コミや評判を書くのはファンです。

ファンは商品やサービスに愛着があるので、細かい感想や意見を書いてくれます。
ファンが書いた生の感想や意見を読んだ人が、購入に至るケースは珍しくありません。
以前までは企業は多額の広告費をかけて宣伝をしていましたが、現代ではファンが発信した感想や意見が広告となるのです。
効率よく売上が伸ばせる
ファンマーケティングは、効率よく売上を伸ばせる手法と言えます。
なぜなら「パレートの法則」を活用しているからです。
パレートの法則とはさまざまな国の所得配分は「人口の20%が世界の富の80%を所存している」という理論です。
ファンマーケティングはパレートの法則を応用し、売上の80%は20%の熱狂的な支持者に対して購入意欲を高める施策を行うことで安定した売上が見込まれると考えます。
一部の熱狂的なファンがリピーターを作れれば、長期的に売上のほとんどを占める存在となります。

リピーターとなるまではさまざまな施策を打ち出す必要がありますが、うまくいけば効率的に売上が伸ばせるでしょう。
顧客のニーズに沿ったPDCAが回せる
ファン化した顧客は商品やサービスに対して愛着を持っているため、的確な感想や意見を伝えてくれます。
熱意のある意見や感想は、顧客が今必要としているサービスやシステムの可能性が高い場合があります。
そのため、商品やサービスを改善する際に顧客ニーズに沿ったいいPDCAが回せるでしょう。
ファンマーケティングが上手くいくと、顧客が求めている商品やサービスに近づいていけるという好循環になります。
ファンマーケティングの注意点3つ

ファンマーケティングを実践する際の注意点は以下のとおりです。
- 炎上リスクがある
- 効果測定ができるまで時間がかかる
- 一部のファンだけの場にしないようにする
ファンマーケティングが失敗すると、大きな損失を得てしまうので気をつけましょう。
炎上リスクがある
ファンマーケティングは顧客と距離が近い分、炎上のリスクも抱えています。
SNSでの不適切な発言や、企業やブランドの不祥事がきっかけで「言っていることとやっていることが違う」と思われてしまい炎上につながります。
炎上のリスクを防ぐにはSNSへの投稿文や作成しているコンテンツは、複数の人間でチェックするのがおすすめです。
また発信するタイミングも重要です。

大きな事件や自然災害により、社会全体がネガティブな方向なときは気をつけましょう。
発信した内容が意図しない切り取られ方をさる場合があります。
炎上リスクも視野に入れながら、ファンマーケティングを展開しましょう。
効果測定ができるまで時間がかかる
ファンマーケティングには一定の時間がかかります。
顧客と信頼を積み重ねることで、商品やサービスの購入につながるからです。
ファンになる顧客を増やすには、何度もイベントを開催したりSNSのフォロワーを集めたりしなくてはいけません。
そのため、どの施策を行えば顧客が増えるのかの効果測定にも時間がかかります。

ファンマーケティングは、中長期的な視点で取り組まなくてはいけないのです。
一部のファンだけの場にしないようにする
ファンマーケティングは顧客と強い絆ができる一方で、初期からのファンが文化や雰囲気を作り上げていきます。
初期ファンが作り上げたコミュニティの状況によっては、新たなファンが入りづらいと感じてしまう場合もあるでしょう。
特定のファンだけの場にしないように、定期的に「入学式」や「新入生歓迎会」のようなイベントをオンラインでもオフラインでも行うと、新規ファンが馴染みやすい空気を作り出せます。
ファンマーケティングの成功する戦略

ここでは、ファンマーケティングを成功させる方法を3つ解説します。
- ファンの愛着や共感を確認する
- オンラインでのコミュニケーションを活発化する
- オフラインでのコミュニケーションを用意する
ファンマーケティングは、ファンとのコミュニケーションを活発にするのが成功の秘訣です。
ファンの愛着や共感を確認する
ファンマーケティングを実践する際は、はじめにファンを明確にしましょう。
ファンは価値観や理念に共感する方をメインターゲットとします。
ファンマーケティングでは商品やサービスに対する価値観や理念への共感が購買意欲につながるからです。
ファンのなかでもどのくらい商品やサービスを購入しているのかも確認する必要があります。

購入意欲と愛着や共感の両方を確認しましょう。
オンラインでのコミュニケーションを活発化する
SNSなどのオンラインのコミュニケーションを活発化させるのは重要です。
オンラインはその場にいなくてもコミュニケーションが取れるからです。
ファンとサービス提供者が定期的に接点を持ち続けることで熱量を維持できます。
またSNSは新規顧客となる潜在層も知れるツールです。
「いいね」や「リツイート」をしてくれている方は商品やサービスが気になっている可能性があります。

潜在層のニーズを探り、商品やサービスに反映していくことでブラッシュアップされていきます。
オフラインでのコミュニケーションを用意する
ファンミーティングやオフ会を開催してオフラインの場を提供することも忘れてはいけません。
リアルな場でのファン同士のコミュニケーションを促進させることで、コミュニティが活発化し既存顧客のリピート率が上がるでしょう。
またサービス提供者がファンと直接会話をすると、ブランドや製品に対する思いが聞けてファンの理解にもつながります。
ファンマーケティングでの成功事例

ファンマーケティングを活用して成功した事例を3つ、紹介します。
企業や個人で手法が異なっていますが、それぞれ成功しています。
どのような方法で実践したのか、見ていきましょう。
チロルチョコはオンラインミーティングを開催
お菓子界で不動の人気「チロルチョコ」
昔からの大人ファンが多く「チロラー」と呼ばれている方々もいます。
そこで実施したのは、ファンの方々とチロルチョコ株式会社の社員が交流する場を設けました。
ZOOMを使用したオンラインミーティングを開催し、チロルチョコへの愛を語り合う時間になったようです。
ファンの生の意見を聞くことで
- ファンを理解できる
- 今後の戦略に活かせる
- ファンを大切に思っていることが伝わる
上記のメリットがあり、社員の方々も楽しんで参加しながらファンの存在を再確認し、働く意欲にも繋がっていくことでしょう。
スターバックスはWebサイトでアイディア募集
スターバックスはファンマーケティングで多くのファンを獲得した代表的な事例です。
主にはSNSの活用を実施していました。
上記の投稿を活用して「新商品」や「期間限定商品」などを紹介していきました。

スターバックスの投稿をフォローワーがリツイートすることでさらに拡散に繋がり、実施した初日の売り上げが予想の3倍ほどになるケースもあったようです。
ファンマーケティングを可視化できるツール

ここではファンマーケティングを可視化するツールを2つ紹介します。
- YELLtum
- アンバサダープラットフォーム
ファンマーケティングを実践するうえでデータ収集は不可欠です。
意味のある施策を打つためにも、ぜひご利用ください。
YELLtum
『YELLtum(エールタム)』はスポーツチームなどが地域通貨(ファントークン)を提供できるアプリです。
YELLtumを発行することで、ファンの購買行動が可視化できます。
YELLtumを発行したスポーツチームは、ファンが地域のどの企業や店舗で購買したかがわかるのです。
そのため、具体的な対策を立てることが可能になりスポーツチームだけでなく地域全体の創生・活発化を進められます。
アンバサダープラットフォーム
『アンバサダープラットフォーム』はファンのSNSでの発信や活動を見える化できる分析ツールです。
アンバサダープラットフォームの強みはLINEと連携ができる点です。
ファンクラブやファンコミュニティの登録はLINEででき手間がかかりません。
ファン向けに発信したい情報はLINEで伝えられるので、伝達向上にも役立ちます。
また個別配信や一斉配信が選べるため、効率的に情報提供ができます。

ファンミーティングを本格的に実践したい方は、ぜひ導入してみてください。
ファンマーケティングに関するQ&A

ファンマーケティングに関するよくある質問に一つ一つお答えしていきます。
ファンマーケティングでアイドルを活用する方法がある?
アイドルを活用した「推し活マーケティング」を取り入れている企業が多くなってきました。
推し活(好きなアイドルやキャラクターを応援する活動)をする人が増えた中で
- コラボ商品を作る
- 商品購入特典としてキャラクターやアイドルグッズをプレゼント
- コラボイベントで写真スペースを設置
上記の方法で、企業の商品に興味を持つ機会を設けることで企業への集客に繋げるのです。
ファンマーケティングを支援するコミュニティとは?
同じ対象に関心・愛着を持つ人が集まるファンコミュニティは、企業への信頼や愛着をさらに深めることができます。
好き同士が情報交換することで連帯感を持つ機会となり、ファン活動もさらに活発になることが見込めます。
また、ファンがさらに企業のPRを拡散してくれることで
- 見込み顧客に対しても情報発信ができる
- リアルなレビューが聞けるため信憑性がある
など、新規の顧客を獲得することもできるでしょう。
スポーツでのファンマーケティングはどんなことをする?
スポーツを通じて商品をPR販売したり、集客することでマーケティングに繋げていく方法を用いています。
- SNSを活用したPR
- イベントPR
- スポンサーを集める
上記の方法を使うことでそのスポーツに興味のある多くの人に情報を届けることができるのです。
その方法を用いて
- コラボグッズの販売
- スポーツ選手期間限定イベント
などを実施していく中で、スポーツ選手の推し活にも繋がるため、課金してくれる人も多いでしょう。
ファンマーケティングとファンベースマーケティングの違いは何ですか?
それぞれのマーケティング方法としての違いは
- ファンマーケティング:ファンにお金を使ってもらう手法
- ファンベースマーケティング:ファンの声に耳を傾け商品に反映させる手法
企業が利益を得るためファンの課金を促すファンマーケティング手法とは違い、ファンの声をできるだけ商品やサービスに反映をさせることを心掛けることでファンからの課金をダイレクトに求めていく方法ではないのがファンベースマーケティングです。
ファンマーケティングにおすすめな本は?
ファンマーケティングを学ぶ際におすすめの本を紹介します。
- ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング Webマーケティングの成果を最大化する83の方法
- ファン・マーケティング―Web2.0時代のマーケティング戦略
- ファンに愛され、売れ続ける秘訣
まずは「Webマーケティングの完全解説マニュアル本」とも言える著者 木下勝寿さんの「ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング Webマーケティングの成果を最大化する83の方法」という本は、マーケティングの全てが書かれています。

基本的なマーケティングを確認した上でファンマーケティングについて、学んでいくのがおすすめです。
ファンマーケティングを実践して顧客満足度をあげよう

ファンマーケティングは上手くいけば、費用対効果の高い施策となります。
しかし効果が出るには一定の時間がかかるため、中長期的なスパンで取り組む必要があるでしょう。
商品やサービスの売上を上げることはもちろん大切ですが、ファンとの交流を楽しみながら成長していきたいと考えている方は、ぜひ挑戦してみてください。
この記事のまとめ
- ファンマーケティングは顧客と信頼や共感を生み購買意欲につなげる手法広告費が抑えられたり売上の見込みが立ちやすかったりするファンと距離が近い分、炎上のリスクを抱えているオンラインやオフラインでのコミュニケーションを活発化する必要がある

 で
で