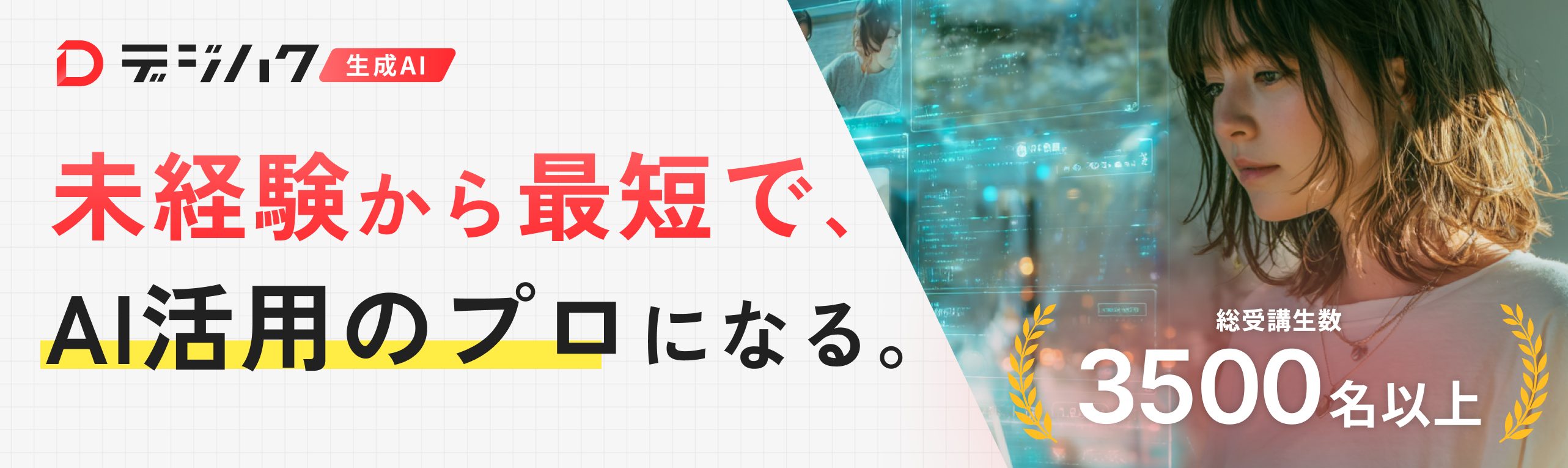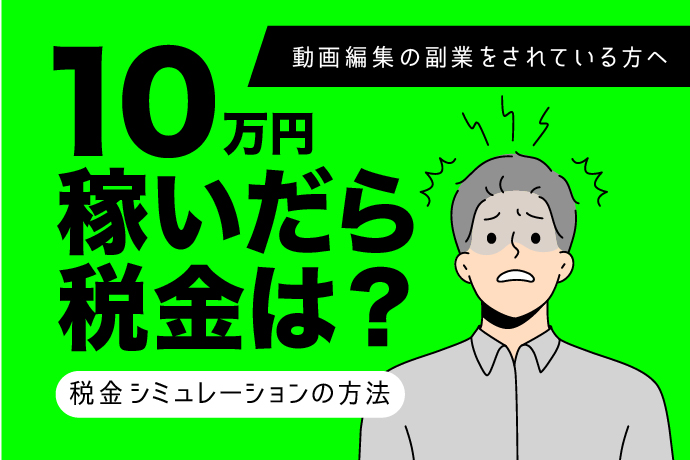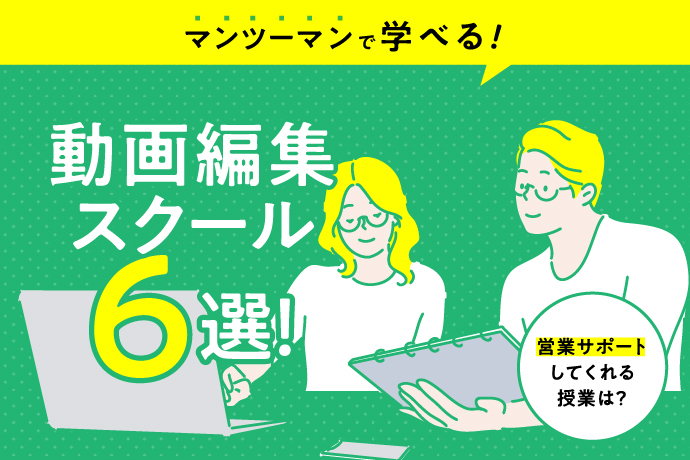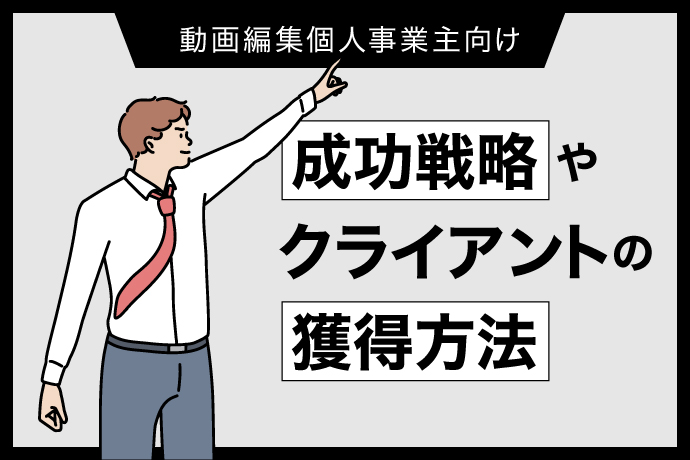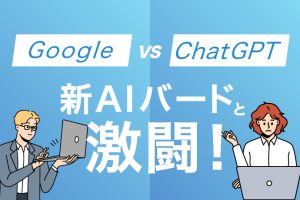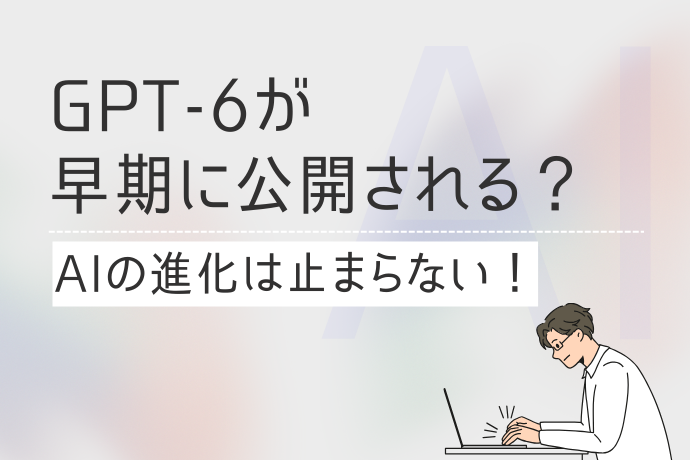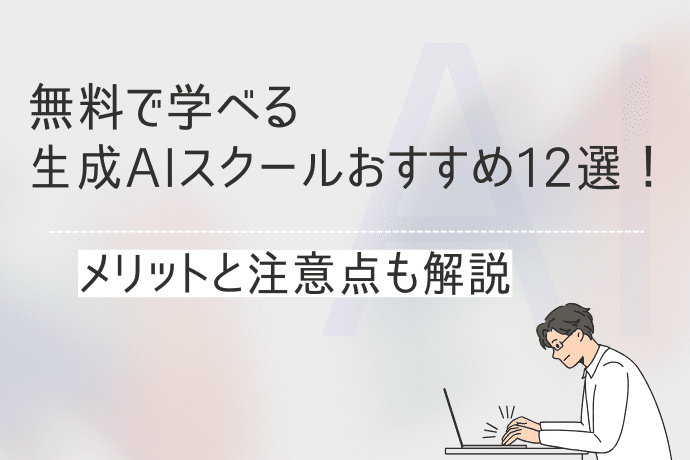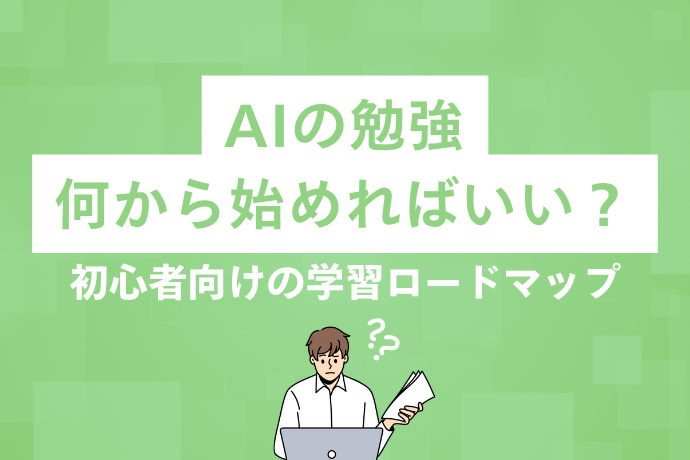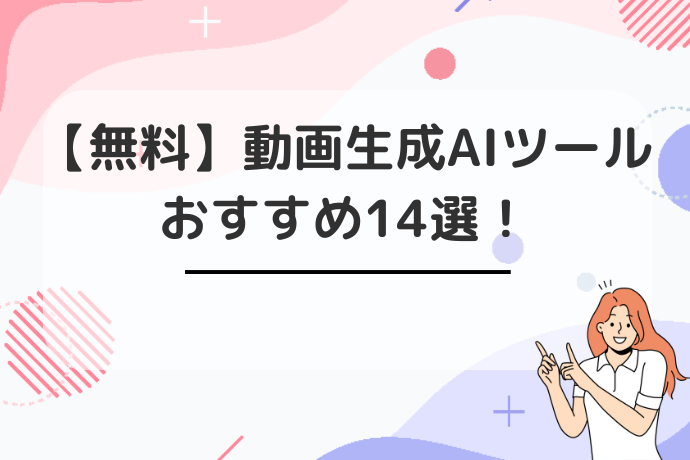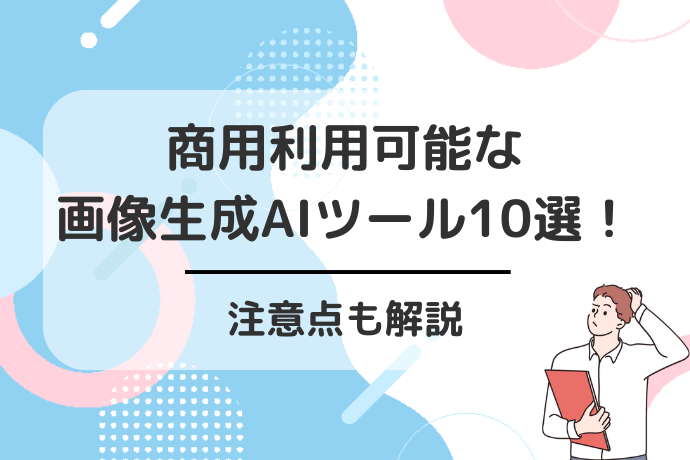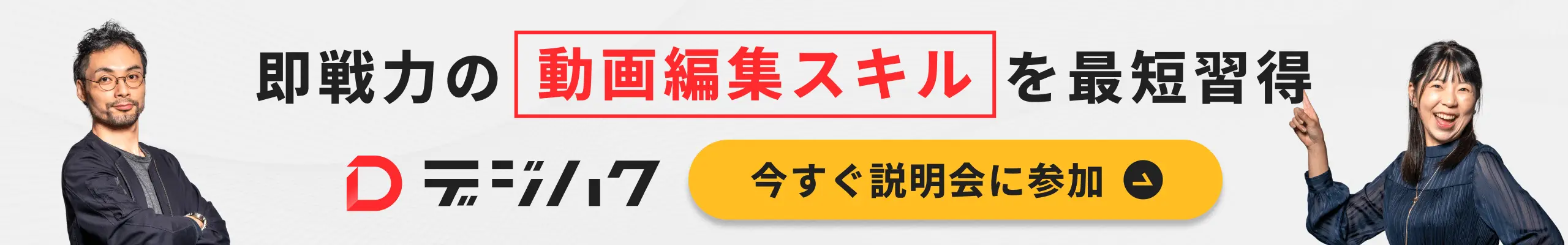この記事では、動画編集の副業で10万円を稼いだ際の税金計算を、具体的に解説します。
税金の負担を軽減しつつ、副業収入を最大限に活用するための有益な情報を得ることができます。
また、動画編集に特化した税金の計算方法や控除のポイントにも焦点を当てています。
動画編集の副業がどれほど稼げるのか。
様々な家庭状況や年収によって税金はどう変動するのか。
そして最も重要な、副業で得た収入に対する税金の対策と節約方法は何か。
副業の収入と税金の関係、10万円の収入を得るまでのプロセス、そしてその税金をどのように計算し、どのように申告すべきかについて詳しく説明します。
動画編集の副業で10万円稼いだ場合の税金計算
この記事で動画編集の副業における10万円の収益と、それに伴う税金の計算について詳しく解説いたします。
副業で自由な時間をつかって収入を増やす際、十分な知識を持って対応できるようにお話していきます。
動画編集の副業とは
動画編集は映像や音声、加工・編集などをし、視覚的に魅力的な作品を創り出す仕事です。
その技術を活かして副業として活動する人が増えています。
要は、得意なスキルを使って自宅で働き、収入を得る方法というわけです。

このような副業は映像制作会社やインフルエンサー、企業のプロモーションビデオ制作等、様々な需要が存在します。
また、YoutuberやTikTokerといったSNS活動にも利用されるため、近年その需要は増加傾向にあります。
仕事を受ける方法は
- クラウドソーシング
- フリーランスのプラットフォーム
などを活用するのが一般的です。
そして、仕事を完了し報酬を得ると、その収入が所得となり、税金の対象となります。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

10万円の収入を得るまでのプロセス
では、10万円の収入を得るまでのプロセスはどのようなものでしょうか。
まず、クライアントから仕事を依頼された際、その価格設定を決定しなければなりません。
この金額はあなたのスキルレベル、作業量、納期等によりますので一概には言えませんが、場合によっては1件で10万円を超えることもあります。
その後、契約後の作業となりますが、ここでは報酬を得るために必要な動画編集スキルを実際に作業に活かします。
作業終了後、クライアントに提出し、承認されたら報酬が支払われます。
これを繰り返して10万円を得ると、それがあなたの収入となります。
しかし、所得の一部を税金として納める義務がありますので、10万円を手にしたとしても全てが赤裸々な現金というわけではありません。
副業の収入と税金の関係
では、副業の収入と税金との関係について理解しておきましょう。
所得税法では、発生した収入が雑所得または事業所得とされ、その金額に応じて所得税が発生します。
副業の収入が年間20万円を超える場合、それが雑所得となります。
雑所得では、必要経費を差し引いた金額が課税所得となります。
そのため、仕事に必要な機材やソフトウェアの費用など、副業にかかった経費を控除することで税金を減らすことが可能です。
また、副業で得た収入が年間38万円を超えた場合、それは事業所得となります。

事業所得では、青色申告を選択することで、経費控除の限度額が650万円まで引き上げられるなどのメリットがあります。
10万円稼いだ場合の税額の概算方法
さて、副業で10万円稼いだ場合の税金計算についてですが、税金の計算は以下のようになります。
まず、所得税の税率は所得金額により異なりますが、10万円の収入であれば所得税は発生しません。
一方、住民税の計算は異なります。
住民税は前年度の所得に基づいて課されます。
副業で10万円の収入があった場合、所得が20万円を超えていないため、所得とは見なされず、住民税は発生しません。
ただし、年間の合計所得が103万円を超える場合、住民税が発生します。
そして所得金額に応じて税率が変わるので、所得金額と自分の住む市町村の条例を確認してから計算します。
確定申告の必要性
つぎに、確定申告について説明します。
副業で得た収入が20万円未満の場合、確定申告は必要ありません。
しかし、20万円以上である場合、確定申告をしなくてはなりません。
10万円はこの限度額未満ですが、本業の収入と合わせて年収が20万円を超える場合も確定申告が必要となります。

自宅に事務所を構える等、経費を差し引くことで税金を軽減できる場合も、確定申告をする必要が出てきます。
年間の総収入を把握する
最後に、年間の総収入をしっかりと把握することが重要です。
年間の収入が分かると、税金の計算や確定申告の準備が立てやすいからです。
副業の収入に応じて、年間の総収入が変わります。
そのため、しっかりと把握しておくことで、確定申告の手続きもスムーズに行えます。
副業の収入は、本業とは別に稼いでいる分なので、税金計算の際も注意が必要です。
所得税や住民税など、税金の種類とその計算方法を理解しておきましょう。
以上、動画編集の副業で月に10万円稼いだ場合の税金計算についてです。
具体的な収入と税金の関係、算出方法を知ることで、副業で収入を得た際の対応がより円滑に行えるはずです。
今後のあなたの副業ライフに役立ててください。
副業と税金
副業がブームとなりつつある現代、副業収入によって生じる税金問題は一層の注意を必要とします。
副業を始める際には、税金についての正確な知識が求められます。
この章では、副業で得た収入がどのように税金として計上され、それがどのように計算されるのか、また税金の手続きはどのように行うのかといった点を簡単に解説します。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

副業収入が税金の対象となる仕組み
副業で得た収入は、会社員の給与所得と同様に合計所得金額に含まれ、税金の対象となります。
給与以外の収入、つまり副業収入を計上するためには、個人事業主として開業届を出す必要があります。
個人事業主として開業届を出すのは難しくなく、無料で行えます。
また、開業届を提出すると、自分で計上した費用を必要経費として差し引く節税策をとることも可能になります。
これを「青色申告」といいます。
一方で、開業届を提出せずに給与と同じように所得を計上する「白色申告」もあります。
副業を始める際は、これら二つの選択肢を理解し、自分の取引や収入状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
副業収入にかかる税金の計算方法
副業収入にかかる税金の計算方法はまず、得た収入から必要経費を差し引いた所得金額を算出します。
所得金額に対して税率を適用し、その結果が支払うべき税金となります。
必要経費とは、収入を得るために必要だった費用のことを指します。

たとえば、副業でPCを新しく購入した場合、その費用は収入を得るための経費と認識され、税金から差し引くことができます。
ただし、青色申告と白色申告では計算方法が異なります。
青色申告を選んだ場合は、所得金額からさらに65万円を控除することが可能です。
一方、白色申告ではこの控除ができず、所得金額そのままが課税対象となります。
副業収入の税金計算は繁雑に感じるかもしれませんが、事前に必要な情報を用意しておけば最大のメリットを享受できます。
税金課税の手続き
副業収入の税金課税の手続きには、確定申告が必要となります。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間内に行わなければなりません。
確定申告のためには
- 年間の収入や支出
- 必要経費
などの詳細なデータを用意する必要があります。
また、青色申告を選んだ場合は青色申告承認申請書の提出が義務付けられています。

確定申告書の提出はe-Taxという国税庁のオンラインサービスを利用することで、自宅からでも手続きをすることができます。
これにより、時間や手間が省けるため、多忙な副業者にとっては時間の節約になります。
しかし、初めての確定申告は書類の種類や計算方法など複雑で、会社員であれば年末調整で給与所得の税金処理が完了してしまうため、特に手間を感じることでしょう。
そのような方は、税理士や行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
必要経費の計上や節税対策など、精度の高い申告をするためにも、疑問点は積極的に専門家に問い合わせてみてください。
こうした知識を身につけて、副業で得た収入に対する税金の正確な理解と適切な対凕を心掛けることが重要。
もし手続きを怠ったり誤った申告をしてしまうと、過少申告加算税などの重いペナルティが課される可能性もありますので、注意が必要です。
副業を始める前に、税金についての知識をしっかりと身につけ、自分自身を正しく守ることをおすすめします。
青色申告について、下記の記事に詳細が載っていますので気にある方はご確認ください!
税金計算の具体的な手順
人生において何事も知識があることは大切であり、その中で税金について理解を深め、自分で計算できるようになることはとても重要です。
必要以上に税金を納めていないか、減税措置を活用できているのか、自身で確認するためには税金計算の手順を理解することが不可欠です。
それでは具体的な手順を見ていきましょう。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

総収入の計算方法
税金計算の出発点となるのが、一年間の「総収入」の計算です。
総収入とは、基本的には自分が一年間に得た収入の合計になります。
勤めている会社からの
- 給与収入
- 自営業からの事業収入賃
- 貸物件からの家賃収入
- 株式や投資信託からの配当収入
など、すべての収入を合算します。
さらに、景品など「金銭以外の収入」も含まれますので注意が必要です。
ただし、全ての収入が総収入に含まれるわけではありません。

たとえば、授業料返還や医療費返還など、本来支払った額が戻ってくるケースでは、その返還金は収入とは見なされず、総収入には計上されません。
このように、自分が得た収入が税金の対象となるかどうかを把握することが大事です。
税率の確認
総収入が算出できたら次に考えるべきは税率です。
税率は総収入に対する税金の割合を示し、これに基づき税金の額が算出されます。
日本の所得税は、その所得金額により税率が変動する累進課税制度を採用しています。
所得金額が
- 一定以下の場合は5%
- 一定額を超えると10%
- 一定額をさらに超えると20%
といった形で税率が上がっていきます。
この税率表は毎年税制改正の影響を受けることもありますので、最新の情報を常にチェックすることが必要です。
税金の計算方法
総収入と税率がわかったら、次は税金の計算です。
具体的には、総収入に税率を掛けることで求められます。
ただし、税率は一定の範囲ごとに変わる累進課税制度を採用しているため、その範囲ごとに計算し、それぞれの税額を足し合わせる必要があります。
すなわち、一定額以下の部分には低い税率を、それを超えた部分には高い税率を適用し、各部分の税額を合計します。
この計算が終われば、自分が納めなければならない税金の額を知ることができます。
控除額の把握
税金を計算する際、考慮すべき大切な要素が「控除」です。
控除とは、税金の算出前に所得金額から差し引かれる金額のことで、これにより税金は軽減されます。
控除には様々な種類があり、例えば
- 基礎控除
- 扶養控除
- 給与所得控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
などがあります。
これらの控除はそれぞれ計算方法や把握すべきポイントがあります。
たとえば、扶養控除は扶養している家族の人数によって控除額が変わるため、その人数を正確に把握する必要があります。
控除額を正確に算出し、税金計算に活用することで、適切な額の税金を納めることが可能となります。
減税措置の利用
最後に、税金計算において忘れてはならないのが「減税措置」の利用です。
減税措置とは、所得税などの税負担を軽減するために設けられた制度のことです。
これらを活用することで、更なる節税を行うことが可能になります。

たとえば、住宅ローン減税や小規模企業共済控除などがあります。
これらは一定の条件を満たすことで利用できるため、自身の生活状況や事業内容により適用可能な減税措置を把握し、積極的に活用することが重要です。
下記のような
- 自己の収入
- 税率
- 控除額
- 減税措置
などを考慮に入れることで、正確な税金の計算を行うことができます。
税金は社会の公共サービスを支える大切な負担でもあるため、自己の責任において適切な額を納めることが求められます。
これらの手順を理解することで、正しい税金の知識を身につけることができるでしょう。
税金シミュレーションの方法
税金計算は複雑で手間がかかると感じることも少なくないでしょう。
しかし、手元に必要な情報が揃っていれば、手軽にシミュレーションできる方法が存在します。
適切な税金計算によって、予期しない税負担を避け、賢く節税できる余地を見つけ出すことが可能です。
ここからは、税金シミュレーションを行うための手順やポイントについて紐解いていきます。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

必要な情報の整理
税金計算を始めるにあたり、まずは必要な情報を整理しましょう。
具体的には
- 算出する税金の種類:所得税、消費税、固定資産税など
- 税額に影響を与える要素:年収、扶養家族数、税額控除、経費など
などが挙げられます。
これらの情報は、税金計算の精度を高め、不必要な手間を省くために重要です。
情報収集を行うためには、以下のような資料が役立ちます。
- 給与明細や所得証明書:自己や配偶者の給与情報や配当情報などを取得できる
- 証券会社や銀行の口座明細:利息や配当などの収入を確認することができる
また、税務署や市区町村が発行する書類も利用可能です。
これらの資料を利用して、必要な情報を整理しましょう。
税金シミュレーションツールの利用
現在では、必要な情報を整理できたら次は税金シミュレーションツールを利用することをお勧めします。
これらのツールはインターネット上で提供されており、使い方も簡単で便利です。
例えば
- 給与所得の額
- 扶養家族数
- 社会保険料
などの情報を入力するだけで、所得税や住民税を算出できます。
また、一部のシミュレーションツールでは、節税対策まで案内してくれます。
注意点としては、これらのツールが結果を正確に計算するためには、適切な情報が必要です。

最新の税制情報に基づいて更新されているツールを選択しましょう。
税制は年々変化するため、古い情報に基づく計算では適切な結果が得られない可能性があります。
これらを踏まえて適切なツールを利用することが、正確な税金シミュレーションの鍵となります。
項目別の税金額の算出
税金シミュレーションツールを利用した後は、項目別の税金額を算出します。
税金は大きく分けて2つの部分に集約できます。
- 課税所得を求めるための給与所得等の計算
- 税額を算出するための税率の適用
給与所得等の計算では、給与から必要経費を差し引いた額が課税所得となります。
また、税率の適用では、所得税は課税所得に対する税率を適用し、更に住民税も給与所得等に対する税率を適用し算出します。
これらの計算を行った後、全体の税額を求めます。
税金は多岐に渡る項目が存在しますが、まずは自身がどの項目に該当するのかを知ることが重要です。
そして、該当項目の税率や計算方法を把握しましょう。
税金計算は煩雑な作業に感じるかもしれませんが、一歩一歩項目を紐解きながら進めていけば、確実に理解を深めることができます。
節税のポイント
適切な税金計算を行い、節税対策を立てるためには、具体的な方法が求められます。
これには、法律が許す範囲での収入の管理、また節税に影響を与える項目を理解し活用することが必要となります。
例えば、所得控除や税額控除といった項目は税金を減少させる役割を果たす項目です。
経費の範囲を理解し、必要経費をしっかり控除することで、課税所得を減らすことが可能。
具体的な状況に応じて、生命保険料控除や住宅ローン控除など、利用可能な控除項目を見つけ出しましょう。
経営者の場合、経費を増やしつつも経済活動を阻害しないバランスの取り方が重要です。
また、相続税対策においては
- 遺言
- 信託
- 生前贈与
などと手段を用いて財産を適切に管理することが求められます。
これらのポイントを把握し、自分に合った節税策を検討することで、税金の負担を軽減することが可能です。
なお、専門的な知識が必要となる場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しましょう。
副業の税金計算事例:動画編集
動画編集はスキルがあれば場所を問わずに作業ができ、主業がありながらも活動を行うのに適した副業の一つです。
しかしこのような副業からの収入がある場合、しっかりと税金計算を考えていかないと自己報告義務を怠ったとして罰せられる可能性もあります。
ここからは、具体的な動画編集副業における税金の計算例をあげ、またそれを節税するための事例、さらに年収や家庭状況による税金の変動について詳しく解説していきます。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

動画編集の副業収入の具体的な税金計算
動画編集を副業として行っている場合、基本的には個人事業主としての所得税を納付すべき対象となります。
例えば、フリーランスとして30万円の収入を得たと仮定してみましょう。
素晴らしいスキルを持つあなたが動画編集をしていたところ、一定の顧客から収入が総額で30万円。
まず所得税は、一年間の収入から必要経費を引いた金額(課税所得)が65万円以下の場合、所得税はかかりません。
それ以上の場合は5%以上の税率が適用されます。
また、所得税以外に住民税も納める必要があります。
経費には種々の項目があります。
動画編集に必要な下記のもの
- PC
- ソフトウェア
- ヘッドホン
- マイク
- 撮影器材
などの費用も経費と認められます。
これらの領収書をしっかりと保存し、帳簿に記録しておくことが重要です。
高価な機材を使っている場合、経費を証明できれば、節税のための大きなメリットとなることは間違いありません。
次に下記の費用も経費に含めることができます。
- 交通費
- 通信費
- 必要な書籍の購入費用
また、自宅をオフィスとして使用している場合、家賃や光熱費も経費として計算できます。
しかし、気をつけたいのは家賃を経費とする場合、部屋の何%を事業に使っているかという明確な証拠が必要です。

住宅ローンの利息は経費になりませんので注意が必要です。
節税の事例
税金を無駄に払わないためには、動画編集の副業にかかる経費をうまく活用する事が大切です。
例えば、動画編集のための教育を受けるためのコース料金は、自己啓発費として計上が可能。
実際の事例として、一定のスキルを得るために高額な通信教育を受けた場合でも、その費用は全額経費とすることができます。

Youtubeのチャンネルにアップロードする動画撮影において飲食料金が発生した場合も、接待交際費として計上が可能。
これにより、飲食代のうち接待交際費として認められる50%は経費として計上可能となります。
さらに、PCやカメラなどの道具を新たに購入した場合、その費用をすぐに経費とするのではなく、一定の期間で償却することで、節税効果が見込めます。
これらはすべて、動画編集という副業ならではの節税策と言えるでしょう。
年収や家庭状況による税金の変動
副業を始める方にとって重要な点の一つが、年収や家庭状況によって税金が変動することです。
副業から得る収入は、本業の年収と合算され、その総年収により税率が決定します。
例えば、本業の年収が1,000万円で、副業(動画編集)から収入が30万円あった場合、所得税はその合計である1,030万円から計算されます。
また、家庭状況により基礎控除の金額も変動します。

例えば扶養家族がいる場合、控除額が増えます。
学生でアルバイトとして動画編集の仕事を行っていて、親に扶養されていれば、親のほうでその収入を控除することができます。
以上のように、動画編集という副業における税金の計算は、一見複雑に思えるかもしれませんが、しっかりと必要な情報を整理し、適切な知識と対策を持つことで、確実に節税を果たすことが可能であると言えるでしょう。
適切な税金対策は、あなたの副業生活をより充実させ、安心して活動できる環境を作り出すための大切な要素だと理解することが重要です。
副業における税金の節約テクニック
副業を始めると、収入が増えた喜びと同時に税金の問題もやってきます。
なんとなく払っていたり、あまり深く考えずに納税していませんか?
実は、副業者が知らず知らずのうちに税金を無駄に払いすぎていることが多いのです。
そこで提唱するのが、副業者向けの税金節約テクニックです。
具体的な控除の活用方法や収入計画の立て方、確定申告の専門家の活用など、ひとつひとつ丁寧に解説します。
税金に詳しくない方でも安心して読み進められる内容となっていますので、ぜひ最後までご一読ください。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

控除を最大限利用する
副業における税金節約の手段の一つに、「控除」が挙げられます。
副業者が知っておくべき控除には、特に経費控除や所得控除があります。
経費控除は、副業に必要な経費を計算に含め、税金の支払い額を減らす制度。
具体的には
- パソコン
- 文房具の購入費用
- 通信費
- レンタルオフィスの利用費
- 商標登録費用
などが該当します。
これらは全て副業者の経費として計上でき、経費とした金額は所得から引かれます。
所得控除とは、一定の所得金額までは非課税とする制度で、基礎控除や配偶者控除などがあります。
ただし、これらの控除を最大限に活用するためには、適切な記録が必要です。

レシートは必ず保管し、経費とするものとそうでないものを分けて管理しましょう。
年間の収入計画を立てる
税金節約におけるもう一つのテクニックは、きちんとした年間の収入計画を立てることです。
税金は年間の収入金額により税率が変化するため、その年の収入見込みによっては、副業で得た収入が想定外の税金になってしまうこともあります。
そこで役立つのが収入計画です。
収入計画を立てることによって、税金の負担を軽減し、最大限所得を得ることが可能になります。
さらに、計画的に収入を得ることで、想定以上の収入があった場合には、その分を社会保険料に振り分けるといった対策も取れます。
収入計画は、税金だけでなく、副業の運営全体の効率化にも繋がる重要な要素といえるでしょう。
確定申告の専門家を活用する
確定申告は、一人で行うには難易度が高く、手続きを間違えると余計な税金を払うことにもなりかねません。
そこでおすすめなのが、専門家の力を借りることです。
税理士や会計士などの専門家は、税金の最新情報を把握しており、適切なアドバイスを提供してくれます。
また、専門家のアドバイスによって、自身が知らなかった控除項目を見つけられることもあります。
専門家は確定申告の手続き自体を代行してくれることもあるため、自分で確定申告を処理する時間や手間を削減できるメリットもあります。

ただし、専門家に依頼する費用も考慮する必要があります。
その費用が控除できる税金よりも高くならないよう、副業の規模や収入を見極めて選ぶ必要があります。
税金の延納制度について理解する
副業者にとって知っておきたいのが、税金の延納制度です。
副業者は一定の額を超えた収入があると、所得税はもちろん、住民税や健康保険料などの支払義務が発生します。
しかし、急な大きな支出は、副業者のキャッシュフローを圧迫し、経済状態を悪化させる可能性があります。
そんな時に活用できるのが、税金の延納制度です。
税金の延納制度は
- 所得が急に増えてしまった場合
- 経済状態が厳しい場合
などに使える制度で、税金の支払いを一時的に猶予できます。
ただし、この制度を利用する際は、利息が発生する点や延納期間の長さなどをしっかりと理解した上で使用することをおすすめします。
無闇に利用すれば、いずれ返済の日が来ます。
その時に支払えなければ、大きな負担となりかねません。
税金の問題は、副業という新たな収入源を得たからこそ直面するものです。
税金節約は、気持ち良く副業を続けるための大切なポイントです。
適切な節税策を知ることで、より副業を有意義なものにしましょう。
動画編集の副業で10万円稼ぐ税金に関するよくある質問
動画編集の副業で10万円稼いだら税金についての質問に対して、一つ一つお答えしていきます。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

YouTubeの収益でも税金は払うの?
YouTubeの動画編集やチャンネル運営を通じて収益化した場合、その収益はあくまで所得ですので、税金の対象になります。
- 動画投稿が副業として行われている場合
- 学生がチャネル運営により収益を得ている場合
上記の場合にも、一定の金額以上の収益があれば所得税の申告が必要となります。
そのため、「税金払ってない」といった状況を続けていると、税務署から申告および納税の催告があり、最終的には罰則が課せられる可能性があります。
具体的には、年間で所得が20万円以上になった場合、翌年の確定申告期間内に申告することが求められます。
また、副業であれ、YouTube動画編集であれ、10万円稼ぐ方法としてYouTubeが選ばれたとしても、収益部分は確定申告の対象となります。
税金の申告と納税は、社会の一員としての義務です。
ですから、YouTubeの収益についても正しく申告し、適切な税金を納めることが求められます。
ひとつ忘れてはならないのは、YouTube収益の申告漏れがあると「ばれる」可能性があります。
これはYouTube動画編集やチャンネル運営を通じて所得を得ている全ての人々、例えば学生の方々にも当てはまることです。
まとめると、YouTubeによる収益化は所得として税金の対象となるため、正しい申告と納税が求められます。
罰則を避けるためにも、しっかりとした管理を心がけましょう。
どの程度編集すれば10万円稼げるのかを知りたい
SEOライティングの片鱗を掴むには
- 記事の長さ
- 品質
- 依頼主の予算
など、様々な要素を考慮する必要があります。
一般的なSEO記事は、1000語あたり1万円から3万円の範囲で報酬が設定されています。
10万円を稼ぐためには、たとえば、1万円の料金設定であれば約10本の記事を編集あるいは作成することになります。
しかし、重要なポイントが一つあります。
それはSEOライティングにおける編集作業の質です。編集作業は単に文章を整えるだけではなく
- 適切なキーワードの選択
- 検索エンジンへの最適化
- ユーザーへの価値提供
といった観点も大切となります。
つまり、質の高い記事を繰り返し提供できることが、プロのSEOライターとして報酬を得る上で重要となります。
文章の編集にどの程度の時間と労力をかけ、それがいかにSEO効果をもたらし、報酬としてどの程度の額を見込めることができるか。
さらにそれから税金を差し引いた金額が自己の所得となるかを見極めることが求められるのです。

これがプロのSEOライターとして10万円稼ぐという目標に向けた一筋の道といえるでしょう。
副業で20万稼いだ税金いくら?
副業収入の税金は、年間の合算所得によって変わります。
合算所得とは、給与所得と副業等の所得を合わせた金額のことを指し、これにより税率が決まります。
年収200万円未満なら税率は5%、200万円以上は所得により10%から最大45%まで上昇します。
続きまして、副業で稼いだ収入が20万円を超えると、一部が税金として引かれます。
その具体的な金額は、あなたの年間収入と現在の税率によりますので、計算方法を知ることが重要です。
一見、難しく思えますが、各地の税務署やネット上でも情報提供がありますので、参考にして計算してみましょう。
動画編集の副業で10万円稼げるようになりたい
実際、動画編集の技術を活かした副業は、稼ぎが見込める一方でスキルが必要となる職種です。
初めての方も安心するためには、動画編集スキルを磨くことが大切です。
ネット上には無料で学べる動画編集の教材が溢れています。
これらを活用し、基本操作を身に付けることから始めましょう。
スキルを磨いたら、次は副業としての動画編集の活動を始めることです。
自分の物作りが好きであれば、個人のクライアントを探し、1件あたりの報酬で収益を立てていく手もあります。
ウェブサイト制作などであれば下記のことが可能になります。
- メインの広告代理店から依頼を受ける
- 企業や店舗の動画制作に携わる
最初は小さな仕事から始めると良いでしょう。
実績が積み重なるにつれて、高額な案件や大きなプロジェクトも受けられるようになります。
創造性と技術力を活かせば、月に10万円を稼ぐことも夢ではありません。

ただし、仕事を受ける量が増えると、納期管理やコミュニケーションにも気を配る必要が出てきます。
ハードルが高いと感じる方もいるかもしれませんが、仕事の進行管理に役立つツールも多数あります。
これらを利用すると、スムーズに仕事を進められるでしょう。
副業で動画編集を行う場合、一人で全てをこなすのではなく、タスクの分担やデリゲートも視野に入れて計画を立てることが大切です。
一緒に働ける仲間を見つけるか、外注を活用するのも一案です。
動画編集の副業で月に10万円稼ぐためには
- スキル習得
- 依頼先の確保
- 効率的な作業
上記のことが秘訣になります。
チャレンジを続けることで、じきに目標達成が見えてくるはずです。
10万円の副業収入に対する税務署への申告方法を知りたい
年間の副業収入として10万円を得た場合、その収入に対する税金の申告は基本的に必要ありません。
しかし、給与収入との合算で総所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
確定申告をするためには
- 収入や支出の証明書を集める(副業の種類によっては領収書や契約書が該当する)
- 必要に応じて源泉徴収票も準備する
- 税務署から「確定申告書A」や「所得税計算書」などの書類を入手する
- これらを詳しく記入する
- 他の書類と合わせて税務署に提出する
税金の計算は、収入から必要経費を差し引いた金額に税率を適用することで求められます。
総所得がその年の非課税限度額を超えた場合、その超えた分に税金が課されます。
無料で使える自動計算できる税金額の算出ツールが知りたい
自動計算できる税金額の算出ツールを2つ紹介します。
- タックスドクター
- マイナンバーカード税計算
それぞれについて、お話していきます。
タックスドクター
一つ目にピックアップするのは「タックスドクター」です。
所得税や住民税など、幅広い種類の税金を自動で計算することが可能。
複雑な手続きも不要で、基本情報を入力するだけで瞬時に税金額が提示され、税金計算の手間を減らすことができる利点があります。
マイナンバーカード税計算
もう一つおすすめしたいのが「マイナンバーカード税計算」です。
こちらは、国税庁が運営する公式のツールで、マイナンバーカードを読み取ることで自動的に税金額を計算してくれます。
正確さを求める方に向けて、誤算の心配の少ないツールとなっています。
他にも、スマートフォンアプリ「税理士が作った確定申告」も注目のツールです。
専門家の監修を受けたツールなので、安心感があります。
さらに、専門的な知識がなくても使いやすいデザインとなっているため、初心者の方でも便利に使用することができます。
これらのツールはすべて無料で利用できます。
税金計算に手間を取られがちな方、手間を減らしたい方はぜひ利用してみてください。
正確で快適な税金計算を実現可能とします。
源泉徴収、確定申告の必要性といった税金の知識を学んで副業で安心して稼ぎ出しましょう!
副業である動画編集で得た10万円の税金計算について解説しました。
税金の対策と節約方法など、初心者でも理解できるように説明しています。
Webを活用することで、税金計算がより簡単に。
電子請求書やクレジットカード給与所得控除を活用することで、節税が可能です。
また、クラウドソーシングなど解説した販売方法も活用してみると良いでしょう。
副業について考える際、不安に思うかもしれない税金問題について、具体的な手順や計算方法、さらに節税テクニックにも触れてきました。
今回の内容を活用することで、ライティングの副業だけでなく、制作や起業といった新たな挑戦にも役立てられます。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ


 で
で