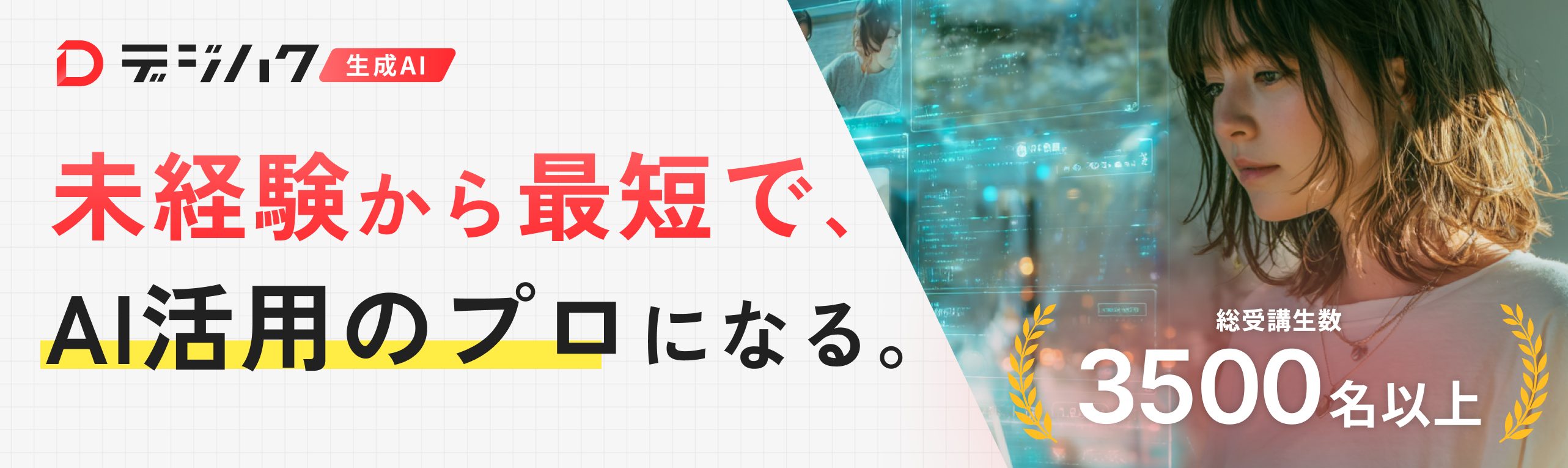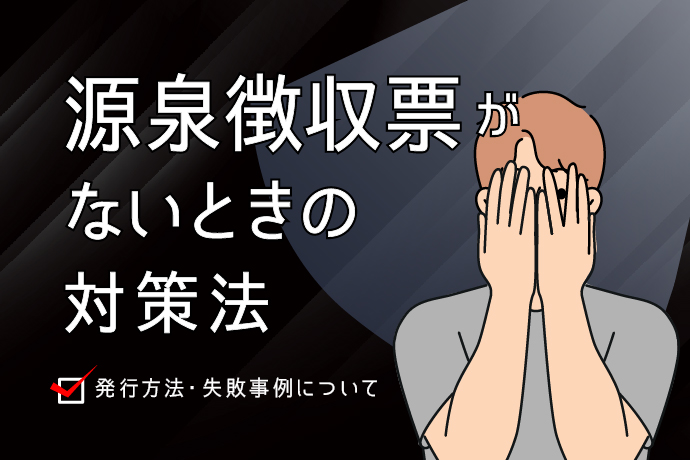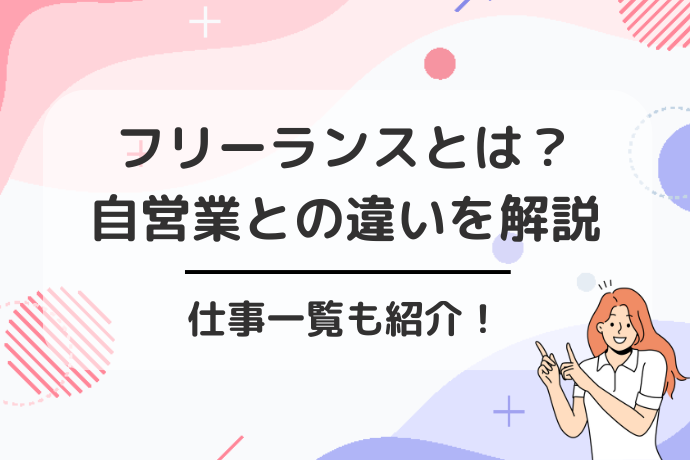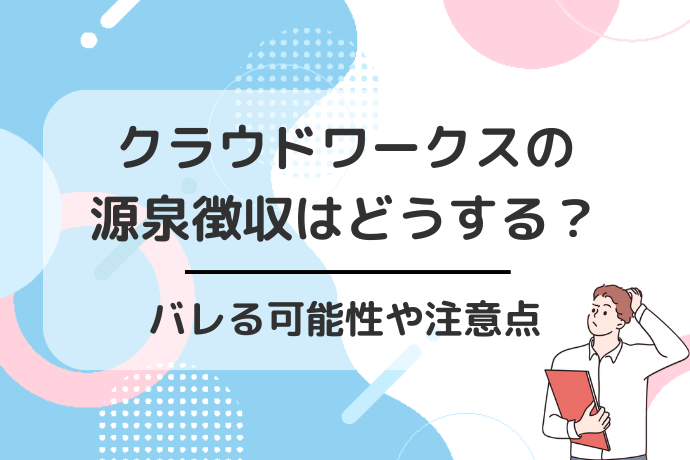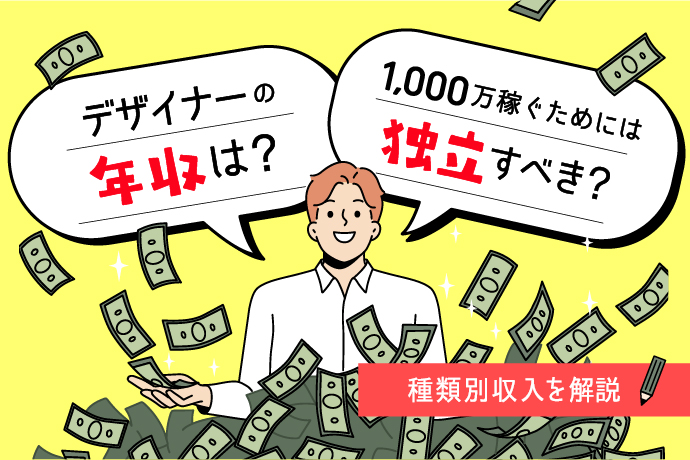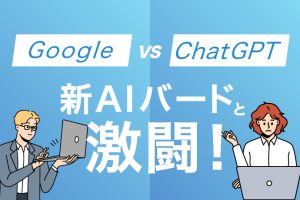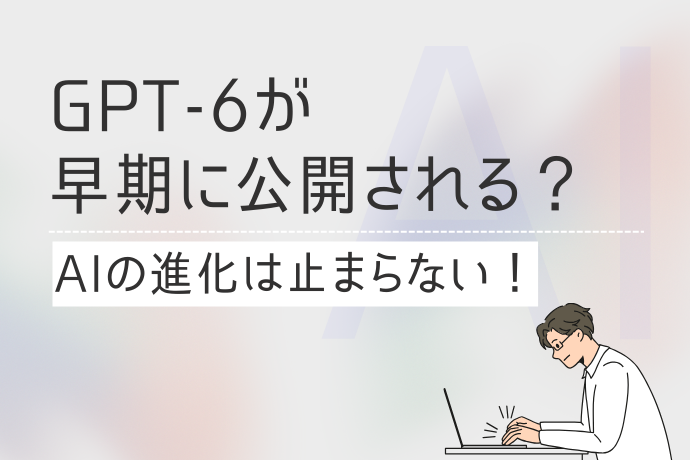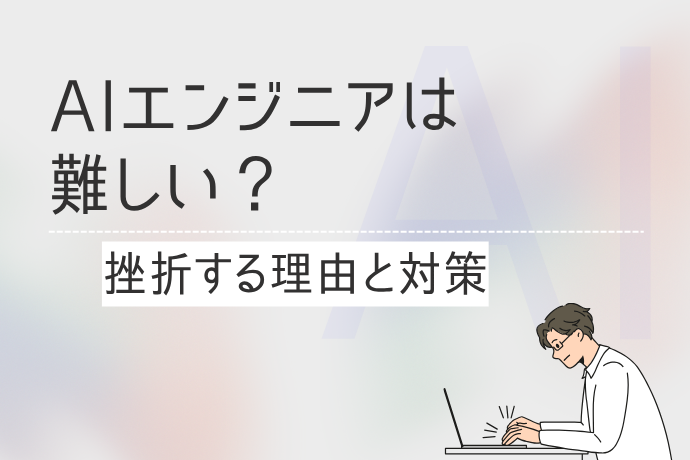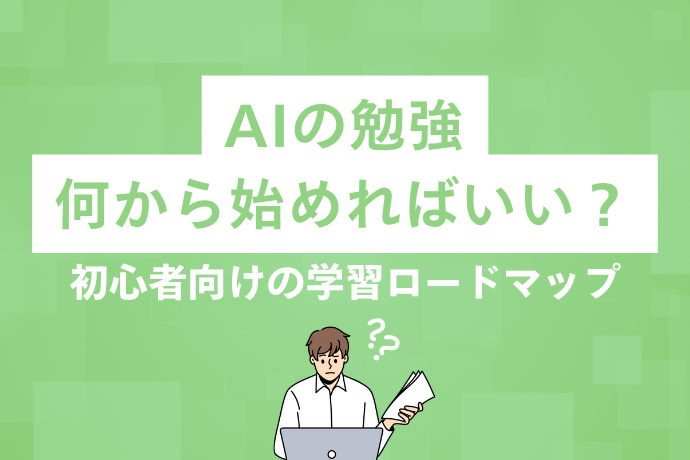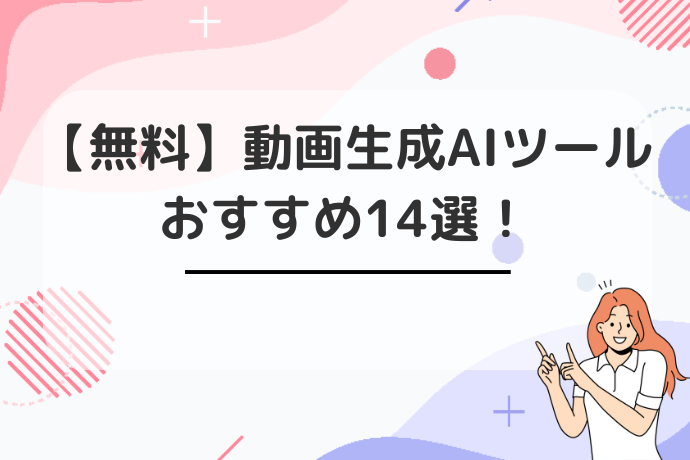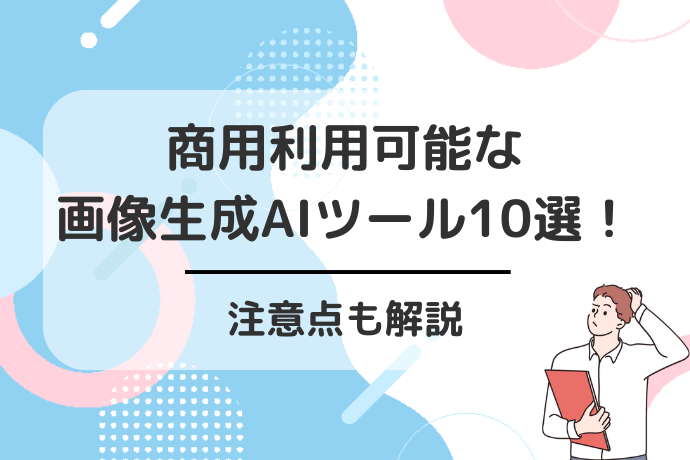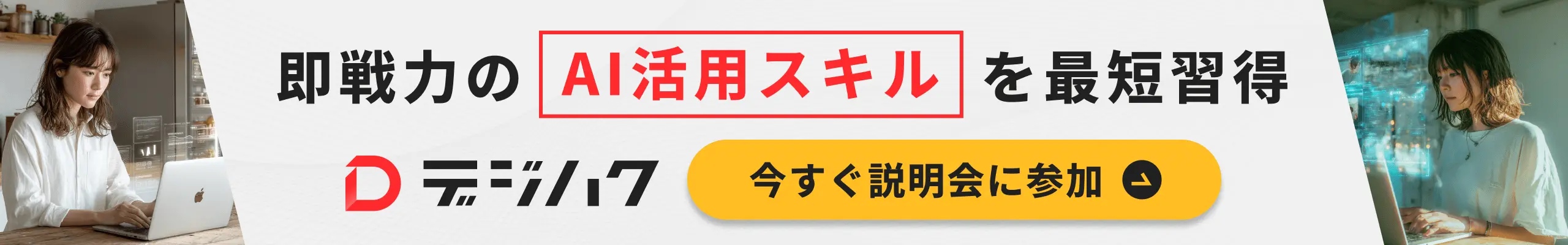「源泉徴収票なし」この状況に頭を悩ませているサラリーマンの副業者やフリーランスの皆さん、副業の所得申告はどう進めていけばいいのでしょうか。
また、副業での確定申告においては、源泉徴収票の必要性を理解し正しい提出方法や手続きを把握することが重要です。
本記事では、そんな副業者が確定申告ガイドや税金計算に置いて遭遇する、源泉徴収票に関する問題を解説します。
もし源泉徴収票の記載内容に誤報告があった場合、どういった手続きを行えばよいのか。
税金や税務署に関連するトラブルを未然に防ぐための具体的な対策法も紹介します。
副業での源泉徴収票がない状況の理解

副業が増える現在、給与所得以外からの収入が年々増加しています。
その一方で、複数の副業を持つ方が増えるにつれ、税理士や経理部門が源泉徴収票を発行しないという事例が見受けられます。
源泉徴収票はお金を受け取る際に発行する事が多いものの、副業での収入に関する税金の計算や申告に関わる重要な書類でもあります。
そこで、今回は副業者が源泉徴収票を持つ意味や、源泉徴収票が発行されない場合の税務上の影響を詳しく解説します。
源泉徴収票とは何か
源泉徴収票とは、給料など所得を得た時に発行される書類で、所得源となる金額とその源泉となる会社や組織が一年間に支払った所得税などを記載したものです。
これは給与所得者に対して毎月一定の税金を会社が立て替えて納めていて、その証明書であります。
この証明書を確定申告の際に税務署に提出することで、所得控除や扶養控除などが計算され、適切な税額が求められます。
また、年末調整の際にも役立ちます。
年末調整とは
年末に会社が行う所得税の精算で、年度内の所得や所得控除額を基にして、一年間に納めるべき税金の額を確定します。
既に納めている所得税と比較し、不足分を徴収または過多分を還付する手続きを指します。
源泉徴収票はいつもらえるものなのか?
源泉徴収票は、基本的に毎年1月末までに雇用主(会社)から従業員に交付されるものです。
途中で退職した場合でも、会社は退職時にその年の分の源泉徴収票を発行する義務があります。
もし退職後にすぐに受け取っていない場合でも、会社に連絡をすれば郵送などで対応してもらえるのが通常です。
なお、源泉徴収票は確定申告や住宅ローンの手続き、保育園の申請などさまざまな場面で必要になる大切な書類なので、受け取ったらしっかり保管しておくことが大切です。
紙で渡される場合もあれば、最近ではPDFなどの電子データで交付されるケースも増えています。
副業者が源泉徴収票を持つ意義
副業者が源泉徴収票を持つ意義について触れてみましょう。
例えば、会社員が副業を行いその収入が20万円を超えた場合、源泉徴収票が発行されます。
この源泉徴収票に記載された収入や所得税等の情報を確定申告に使用します。
これにより正確な税額が算出され、必要な税金が納付されます。

確定申告は税金を正しく納めるための重要な手続きであり、所得税法に基づいて行われます。
副業の収入がある場合、特に自分で確定申告する必要があることは、税金を正確に納めるために知っておくべき重要な情報です。
副業での源泉徴収票が発行されないケース
副業で源泉徴収票が発行されないケースも存在します。
例えば、副業先が個人事業主である場合や、副業の収入が年間20万円を下回る場合などです。
個人事業主から受け取った収入は原則として源泉徴収の対象外とされています。
よって、そのような副業をする場合、源泉徴収票が発行されずに給付を受けることがあります。
また、年間収入が20万円を下回るとその収入は所得税の対象とならず、源泉徴収も発生しないため源泉徴収票が発行されないといったケースがあります。
源泉徴収票が発行されない理由
源泉徴収票が発行されない理由について解説します。
- 副業先が個人である場合や家族である場合
- 副業先が個人事業主である場合
- 副業の年間収入が20万円を下回る場合
など、副業者に源泉徴収の義務がない場合、源泉徴収票は発行されません。
これは、所得税の課税基準が年間総所得20万円以上と定められているためです。

年間20万円以下の所得については、所得税の対象外となるため、源泉徴収や源泉徴収票の発行は原則行われません。
源泉徴収票がない場合の税務上の影響
最後に、源泉徴収票がない場合の税務上の影響について解説していきます。
源泉徴収票がない場合でも、所得が発生したことを確定申告書に記入し、税務署へ提出する義務があります。
年間の総収入が20万円を超えた場合、特にその必要があります。
所得があったにも関わらず申告しなかった場合、遅延納付加算税や重加算税が課される可能性があるため注意が必要です。

個人事業主から収入を得た場合や副業で収入を得た場合でも、その収入は雑所得として申告します。
そのため、源泉徴収票がない場合でも、正確に所得を申告し、税金を納付することが重要。
確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日までとなっていますので、しっかりと準備をしておくことが求められます。
源泉徴収票がない状況の対処法

源泉徴収票は税金計算の際に欠かせない年収を証明する各種決算書の一部です。
しかし給与明細が主に発行されている場合やフリーランスなどで副業を持っている場合など、自身が対策をしっかりと練らなければならない場面があるかもしれません。
源泉徴収票がない事に気づいたら、落ち着いて以下の手段を試してみてください。
源泉徴収票を発行してもらうための交渉方法
源泉徴収票の発行を依頼しようと思ったが、なかなか上手くいかないという場合もあるかもしれません。
そのような場合の交渉テクニックとしては
- 相手に対して自分の状況を具体的に説明する
- 源泉徴収票の発行を依頼する
という方法があります。
例えば、「自分がフリーランスで活動しており、確定申告のために源泉徴収票が必要である」と具体的に伝えると良いでしょう。
これにより、相手が理解しやすくなる可能性があります。
また、源泉徴収票の発行を依頼する際には、相手の負担を減らす工夫も重要になります。

具体的には、「直接受け取りに行く」「必要な情報はすべてメールで送る」などといった提案を行い、相手の手間を省くようにしましょう。
相手の負担が少なければ、源泉徴収票を発行してくれる可能性が高まります。
源泉徴収票が発行されない場合の代替ローン
源泉徴収票がない場合でも対処法はあります。代替ローンという方法が考えられます。
これは、金融機関が提示した資料を代わりに提出することで、源泉徴収票がない状態でも個人事業主やフリーランスの方がローンを組むことを可能にします。
例えば
- 確定申告書や個人事業の収入を証明する書類
- 銀行口座の通帳コピー
などが必要となることが多いです。
自分の収入を証明し、信用力を示すためにはこれらの書類が不可欠です。
しかし、これらの書類を揃えるためには時間がかかる場合があります。
また、金融機関によって求められる書類は異なるため、具体的には何が必要か調査する必要があります。
そのため、時間に余裕を持って準備し、具体的にどんな書類が必要なのかをリサーチしましょう。
副業の収入報告に必要な情報とは
副業の収入を税務署に報告する際には、必要な情報がいくつかあります。
その一つが、副業で得た収入の総額。
これは、副業での収入を把握しその金額を税務署に申告するために必要な情報です。
また、副業の種類や働いた期間なども重要な情報となります。

副業の詳細な情報は、税金の計算方法に影響を与えるため、正確に報告することが求められます。
さらに、副業の場合、経費が発生することもあります。
そのため、経費についても詳細に記録することが重要です。
経費については、その内容や金額を明確に記録し、必要に応じて税務署に提出する必要があります。
副業者自身で源泉徴収票を作成する方法とは
副業者が自身で源泉徴収票を作成するには、確定申告が必要となります。
この際には
- 青色申告:経理の基準を守ることで一定の税制優遇が受けられる
- 白色申告:記帳の義務がない代わりに基本的な控除のみの申告
の2種類から申告の方法を選びます。
このような申告を行うためには、副業からの収入と支出に関する詳細な記録が必要となります。
また、白色申告を行う際には、必要な証明書類の準備も求められます。
源泉徴収票を作成するためには
- 独立行政法人日本在宅ワーク協会が提供している「源泉徴収票作成ツール」
- 国税庁の電子申告・納税サービス「e-Tax」
などを利用すると便利です。
これらのシステムを利用することで、手間をかけずに確実に源泉徴収票を作成することができます。
源泉所得税を自己申告する方法
源泉所得税を自己申告するためには、毎年2月16日から3月15日までに国税庁への確定申告を行う必要があります。
確定申告とは、過去1年間の収入と経費、そしてそれらによる所得を計算し、自身で税金を算出、納付することです。
確定申告を行うためには
- 確定申告書
- 給与所得の源泉徴収票
- 所得税の控除に関する申告書
などの書類を用意します。
これらの書類は、税務署やコンビニエンスストアで入手することができます。
さらに、e-Taxを利用すれば、インターネットから確定申告を行うことができます。
この場合、必要な書類をスキャンしてアップロードし、所得や経費を入力することで申告を行うことができます。

コンビニエンスストアや銀行ATMから所得税を納付することもできます。
副業での源泉徴収票のもらい方とその重要性について

年々増加している副業。そこで気になるのが税金のことで、源泉徴収票が必要不可欠となります。
副業での源泉徴収票のもらい方など全体像を把握し、正確な税金の申告を行うための準備をしておきましょう。
副業で源泉徴収票をもらうタイミング
副業においての源泉徴収票の受け取りタイミングについて見ていきましょう。
多くの場合、主たる収入となる本業だけでなく、副業でも源泉徴収票は必要となります。
この源泉徴収票は何に使用するものなのか、何時何分に受け取るべきなのか詳細に触れていきます。
源泉徴収票は
企業や個人事業主が
- 従業員
- パート
- アルバイト
- 外注先
などに支払った報酬に対して源泉徴収した所得税額とその報酬額が記載された公式書類となります。
これは、毎年1月から12月までの所得税の支払い状況をまとめたもので、次の年の2月頃に発行されます。
副業で源泉徴収票をもらうタイミングは
- 副業先の企業や個人事業主から年末調整を行われる場合:その年の12月から翌年の1月にかけて受け取る
- 年末調整を行わない場合:確定申告の期間である2月16日から3月15日前後に手渡しされるか郵送される
源泉徴収票が手元にない場合は、副業先に問い合わせを行い、速やかに受け取るようにしましょう。
それが難しい場合や連絡がつかない場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。

住民税の申告は、通常は各市町村の役所で行うことができますので、忘れずに手続きを行いましょう。
副業税金対策はしっかりと行い、適切な税務処理を心がけましょう。
副業の種類別で源泉徴収票のもらい方

副業の形態によっても源泉徴収票のもらい方は異なります。
以下に各パターンを見ていきましょう。
フリーランスの場合のもらい方
フリーランスの人々は取引先との契約に基づき、報酬を受け取っています。
そのため、先方とのやり取りで源泉徴収票をもらいます。
ただし手順に抜け漏れがないよう注意が必要で、確認事項があれば積極的に問い合わせることが望ましいといえます。
パート・アルバイトの場合のもらい方
パートやアルバイトなど、雇用形態の副業では、主たる雇用と同じく職場から源泉徴収票をもらいます。
そのため、会社の規定に従って受け取ることとなります。
紛失や未受領等のトラブルを避けるため、早めに確認しましょう。
個人事業主の場合のもらい方
個人事業主もフリーランス同様、取引先から源泉徴収票をもらいます。
ただし、ここでは発注先との明確な契約基盤が重要で、特に発注先が法人の場合は契約書とともに源泉徴収票の交付も確認することが必要となります。
企業の社員としての副業の場合のもらい方
企業の社員として副業をしている場合も、主な職場と同じく、副業先での業務に対する源泉徴収票は当該企業からもらいます。
そのため、きちんとした手続きを踏むことで、確実に源泉徴収票を入手できます。
株式投資や不動産投資の場合のもらい方
株式投資や不動産投資から得た収益も、源泉徴収票が必要です。
- 株式の配当金
- 売買の利益
- 不動産の家賃収入
など、どのような収入でも、証券会社や不動産管理会社などからそれぞれ源泉徴収票をもらいましょう。
副業での源泉徴収票をもらえない場合の対処法

しかし、何らかの理由で源泉徴収票がもらえない状況に陥った場合、どのような対策が必要でしょうか。
もらえない場合の理由と問題点
源泉徴収票がもらえない理由はさまざまで
- 企業側の手違い
- 個人の管理ミス
といったケースが考えられます。
この源泉徴収票を所得税の申告時に見つかった脱税と見なされると、罰則対象となることから重大な問題となります。
源泉徴収票がもらえない場合の税務対策
源泉徴収票がもらえない場合、まずは副業先または取引先に対して再発行を求めるべきです。
企業によっては一定期間経過後には再発行が難しいケースもあるため、発行を確認できず不安がある場合には迅速な対応が求められます。
必要書類の代替となるもの
しかし、どうしても源泉徴収票が手に入らない場合でも、その他の証明書や書類を税務署に提出することで対応可能です。
たとえば
- 銀行振込の明細
- 売上の計算書
- 契約書
などがそれにあたります。
このように、新たに提出可能な書類を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

副業を始める際には、社会保険や税金など、法的な部分にも十分な配慮が必要です。
それらに対する理解と正確な手続きによって、副業での所得も正しく申告し、税務上の問題を避けることができるでしょう。
税務署への対応方法

副業者として税務署とのやり取りが必要となる場合や、なるべく手間を省きたいという方のために、税務署への対応方法についてご紹介します。
源泉徴収票なしの場合の税務署への説明
たとえば、報酬に対する源泉徴収が行われていない事情や、ソースが不鮮明な場合、どのように税務署に対して説明するのが最適でしょうか。
このようなケースでは、なるべく詳細な記録や証拠を用意し、その上で収入と経費を明確にして申告することが求められます。
自己申告の場合でも、誠意をもって対応すれば問題は少ないと言えます。
税務署からの通知や指導への対応方法は
税務署からの通知や指導があった場合、一般的には素直にその指示に従うことが求められます。
ただし
- 不明な点がある
- 指導内容に対して異議がある
上記の場合には税務相談窓口を利用することをおすすめします。
税務相談窓口を利用する方法
税務署には専門的な税務相談窓口が設けられており、税金に関する疑問や不明点などがある場合は、こちらで専門家に質問することが可能です。
また、より専門的なアドバイスを受けたい場合には、税理士への相談も視野に入れてみると良いでしょう。
副業経験者から学ぶ源泉徴収票のもらい方
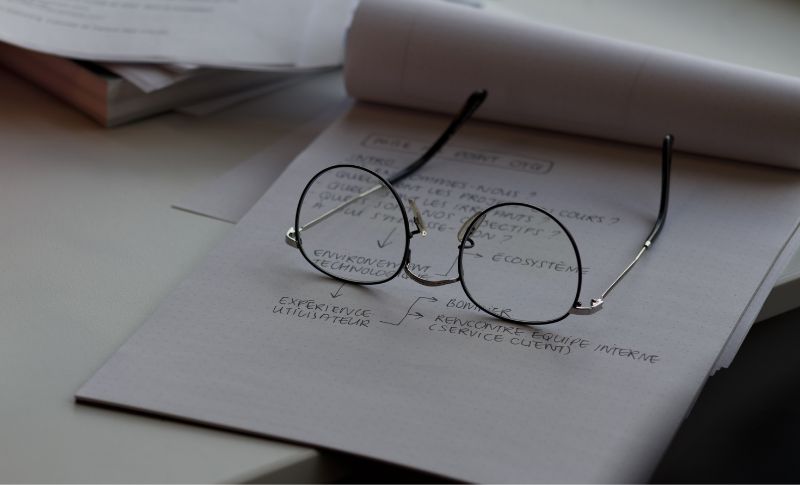
副業をする上で必要不可欠な知識の一つが源泉徴収票のもらい方です。
副業を長期間続けるためには、税金のやりとりが常に必要です。
税金の一部として源泉所得税は払われますが、その証明書である源泉徴収票をきちんともらうことが大切になります。
副業経験者の失敗談とその対策
副業を始めてみて、源泉徴収票をもらいそびれてしまう人もなかにはいます。
確定申告時に、どうにかして適切な額を申告しようとするものの、手元に必要な証明書がないというケースに陥ります。
そういった失敗談から私たちは、いかにして適切な税務処理をするかという重要性を理解できます。
具体的な失敗談としては
- 「副業元に源泉徴収票を請求し忘れた」
- 「請求自体はしたものの、適切な時期にもらうことが出来なかった」
- 「副業元から源泉徴収票が送られてきたものの、その管理を怠り、紛失してしまった」
などの例が挙げられます。
これらの失敗談から学ぶべきポイントは大きく二つあります。
源泉徴収票の請求は忘れずに行う
一つは、源泉徴収票の請求は忘れずに行うことです。
確定申告の前に源泉徴収票の存在を思い出すことが大切です。
副業をしている以上、税金の管理は自己責任であり、しっかりと確定申告を行うためには、源泉徴収票をもらうことが必須とも言えます。
源泉徴収票を適切に管理する
もう一つは、源泉徴収票を適切に管理することです。
源泉徴収票は、確定申告する際に必要となる大切な証明書です。
これを紛失してしまうと、税金を正しく申告できないだけでなく、トラブルの元になることもあります。
そのため、適切なところに保管し、確定申告時にすぐ取り出せるような環境を作ることが重要です。
実際の源泉徴収票のもらい方の事例
副業元が企業だった場合、年度末(12月または3月)に源泉徴収票をもらうことが一般的です。
副業元が個人事業主であるときには、副業者自身から源泉徴収票を請求することが必要になります。
例えば、個人事業主から副業報酬を得ていた場合、源泉徴収票はその個人事業主からもらうことになります。
しかし、個人事業主から直接源泉徴収票をもらう際には、ある一定の手続きを踏む必要があります。

具体的には、年度が終わる前に個人事業主に連絡をし、源泉徴収票をもらう意思表示を行います。
その上で、個人事業主と副業者との間で源泉徴収票の発行に関する合意がなされます。
その結果、源泉徴収票が発行され、副業者のもとへ送られます。
副業を長く続けるための税務の知識
副業を続けるためには、税務についての知識を持つことが重要です。
副業報酬から源泉所得税が引かれ、その証明として源泉徴収票をもらうわけですが、この過程を理解しているかどうかは、副業を長期間続けるうえで大切な要素となります。
税務の知識を持つことで、副業の収益を確実に自分のものにし、また次回の副業に活かせるのです。
税務知識の一部として、「所得税」と「消費税」の基礎知識が必須となります。
- 所得税:副業で得た収益に対して課される税金
- 消費税:副業で使った商品やサービスの金額に対して課される税金
これらの税金を適切に管理することで、副業を効率的に続けることが可能になります。
自分自身がどの税法に従って税金を計算し、納めるべきかを把握することも大切です。
日本には
- 所得税法
- 法人税法
上記の二つの税法が存在します。
個人が副業をする場合、大抵は「所得税法」に従って税金を計算し納めますが、個々のケースにより異なる場合もあります。
副業での源泉徴収票発行のためのコミュニケーション方法

副業を始める場合、懸念材料の一つとして挙がるのが源泉徴収票の取扱いです。
ここでは、副業者が源泉徴収票の発行を確実に受け取るためのコミュニケーション方法について詳しく説明します。
副業先とのコミュニケーションの取り方
副業者は、事業主である副業先と適切にコミュニケーションを取ることが肝心です。
源泉徴収票の発行に関しては、副業の開始時にその旨を確認し、年初には必ず発行を依頼するようにしましょう。
また
- 収入が変動する場合
- 副業の内容が変わる場合
上記の場合には、それをきちんと伝えて所得を正確に把握するための対策を講じることも重要です。
源泉徴収票の確認の頻度と方法
源泉徴収票の確認は副業者にとって重要な作業です。
その頻度としては少なくとも年1回、確定申告の前には確認することが必要です。
具体的な方法としては、副業先から送られてくる源泉徴収票を領収し、自身の収入と確認することが基本となります。

不明点があれば副業先や税務署、税理士などに確認しましょう。
副業先に対する源泉徴収票発行の要望の出し方
副業先に対して源泉徴収票の発行を要望する際は、まずはその必要性をしっかりと理解させましょう。
税金の計算や確定申告のために必要な書類であること、副業者自身の税金の納付を適正化する手段であると説明することが重要です。
- どの時期に発行してもらいたいのか
- どのように受け取りたいのか
など、具体的な要望も具体的に伝えましょう。
他方で副業先も自社の経理体制等により対応が難しい場合もあるため、柔軟に話し合うことも重要です。
副業税金問題の相談窓口とその活用法

副業を始めると、毎年の確定申告や所得税計算は避けて通ることができません。
また、場合によっては消費税を納める義務も生じます。
しかし税金の専門知識がない、どこに相談すればいいのか分からないと感じている方も多いはずです。
ここでは、副業税金問題に関する公的、民間の相談窓口とその活用法についてご紹介します。
公的機関による相談窓口
副業者が税金問題について相談可能な公的機関としては、まず最初に税務署が挙げられます。
税務署
税務署は各市町村に設けられており、月一度以上は開業届の受付や税金関係の相談センターの開設があります。
- 副業の収入計算
- 所得税
- 消費税
などの税金計算についてはもちろん、自己申告や確定申告についても具体的なアドバイスを受けることができます。
さらに、税務署のホームページではe-Taxの使い方や確定申告の手続き方法など、各種情報が公開されています。
自治体や商工組合などが主催するイベント
税務署以外にも、自治体や商工組合などが主催する税金相談会もオススメの窓口です。

これらのイベントでは、通常は料金がかかる税理士のアドバイスを無料で受けることができるケースが多く、副業に関する税金問題について一から十までアドバイスをもらえます。
民間企業による相談窓口
民間企業による相談窓口は、主に個別の相談に対して手厚い対応をしてくれる会計事務所や税理士事務所です。
所得税はもちろん、青色申告、白色申告、副業による所得控除の適用などについて詳細に対応してくれます。
専門家による具体的なアドバイスは
- 税金問題
- 副業経理一般
- 資金管理
- 法人税問題への対応
など、副業を続ける上での幅広いサポートにつながります。
さらに民間企業のなかには、オンラインでの相談サービスを提供しているところもあります。
- Web会議システムを利用した遠隔相談
- 質問メールに対する回答
など、利用者の生活スタイルや働き方に合わせたサービスを展開しています。
窓口を選ぶ上でのポイント
副業税金問題の相談窓口を選ぶときは、自身の生活環境や副業内容に合せて選ぶことが大切です。
公的機関であれば信頼性も高く、情報の質も確かです。
一方で誰でも気軽に相談するのは難しい場面もあります。
その点、民間企業であれば、具体的かつ個別の問題に対応してくれるメリットがあります。
費用を払うことできめ細かいサービスを受けられるという点で、多くの副業者にとって有効な選択肢となるでしょう。
ただし、費用も考慮に入れた上で選ぶ必要あります。
相談窓口の具体的な活用方法
相談窓口を活用するためには、まず自分自身で把握すべきことがあります。
それは直近の副業による
- 収入
- 経費
- 事業の状況
などです。
見当違いの情報を提供すると、誤ったアドバイスを受けてしまう可能性があります。
確定申告や所得税計算の前には、必要な書類を整理し、収入・経費の詳細を把握して準備しておきましょう。

分からないことや聞きたいことをリストアップしておくことも大切です。
副業の源泉徴収票がもらえない時についてのよくある質問

副業の源泉徴収票がもらえない時に疑問に感じることについて、一つ一つお答えしていきます。










必要な書類を揃えて確定申告の期限を絶対に守りましょう!

以上の情報を基に、「副業の源泉徴収票がないときの対策法!源泉徴収票のもらい方とは」について解説しました。
源泉徴収票は確定申告に欠かせない書類です。
しかし、副業先から源泉徴収票を受け取れない場合の対策が必要となる場合もあります。
対策法として、自ら必要な書類を揃え税金を計算し、正しく申告することが最も重要です。
税務署に問い合わせを行い自身で確定申告を行うだけでなく、税理士など専門家のアドバイスも活用するのも有効です。
この際、確定申告の期限を絶対に守るよう心掛けましょう。

期限を過ぎた場合の追加税や罰金を避けるためにも、この点を特に念頭に置くべきです。

 で
で