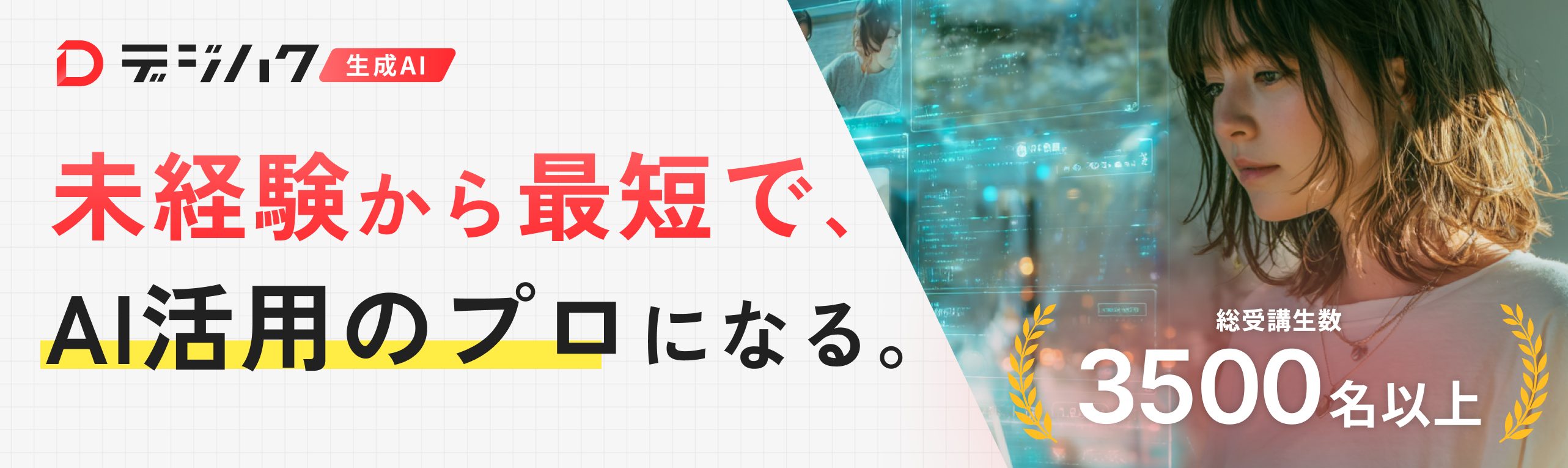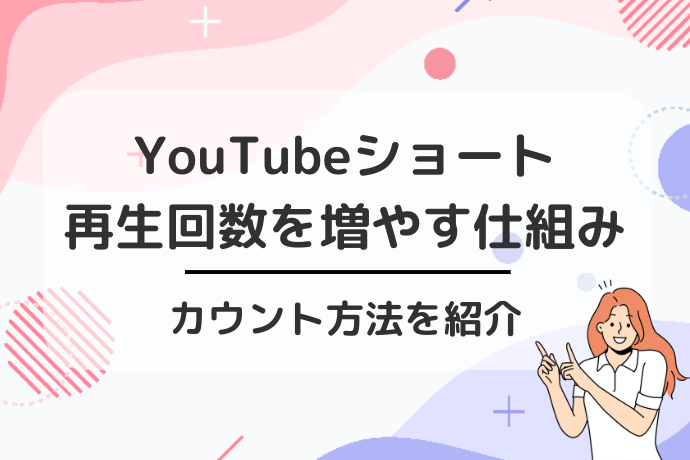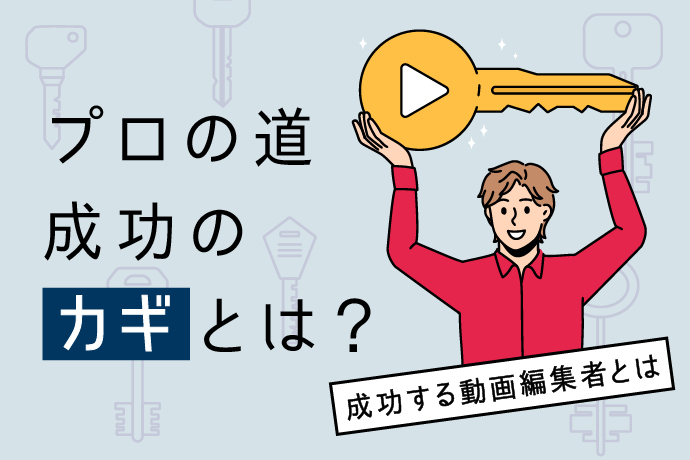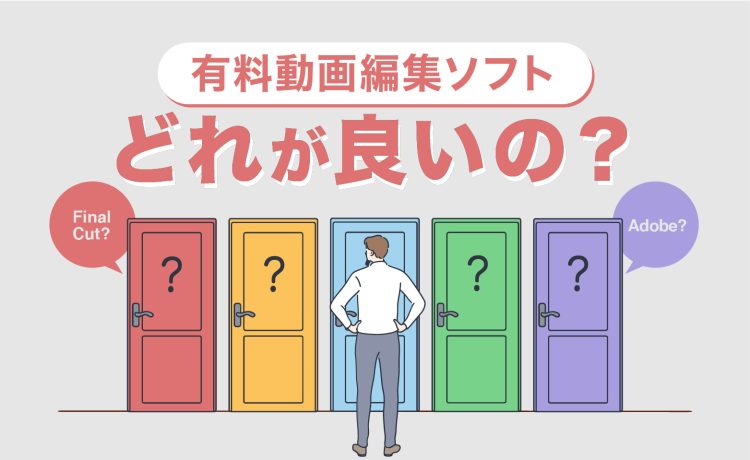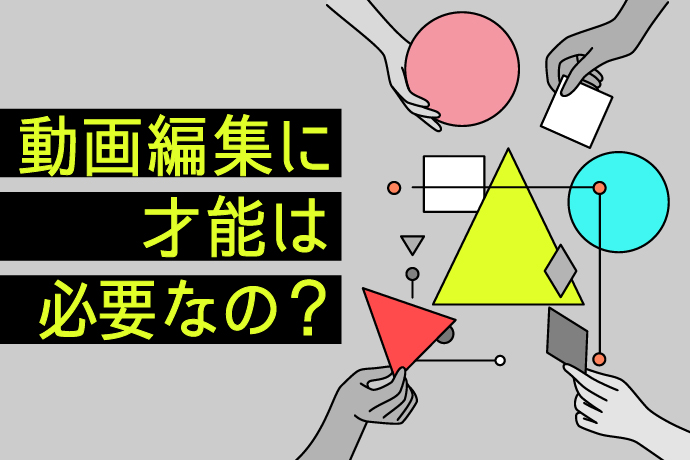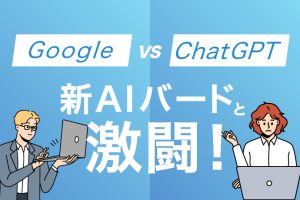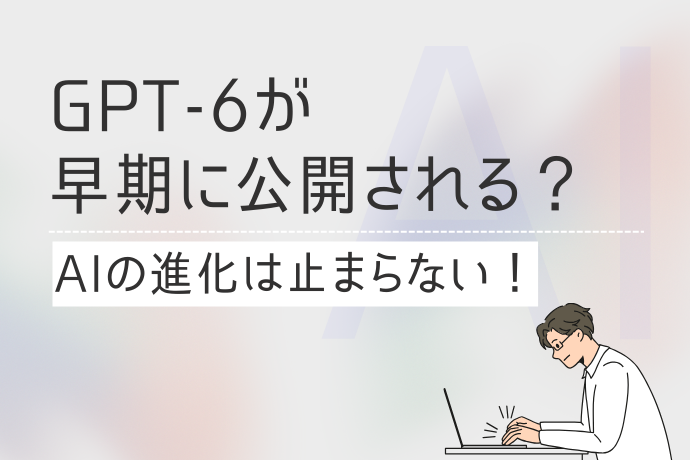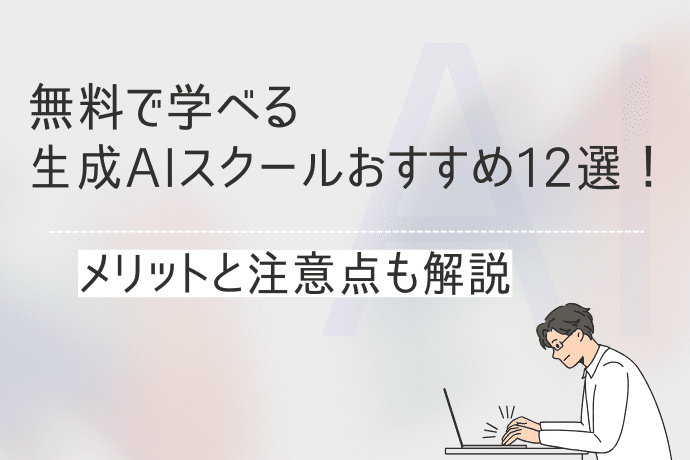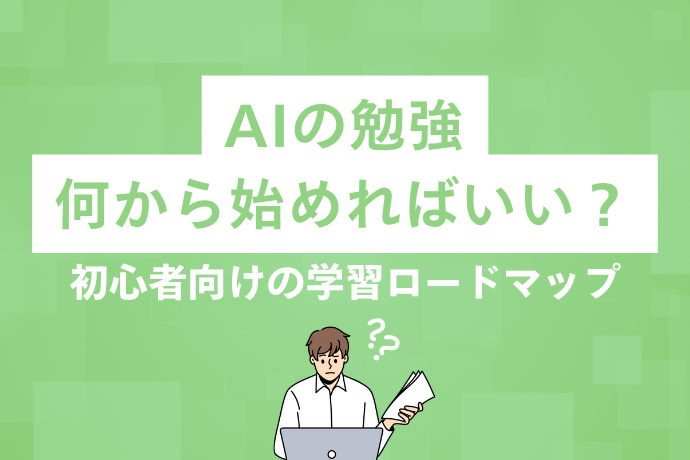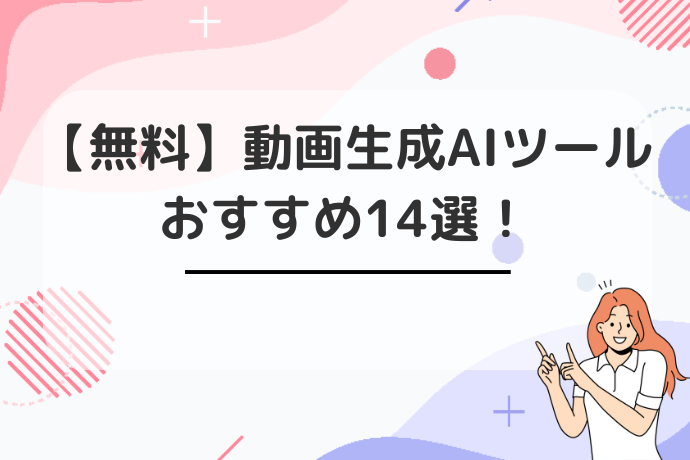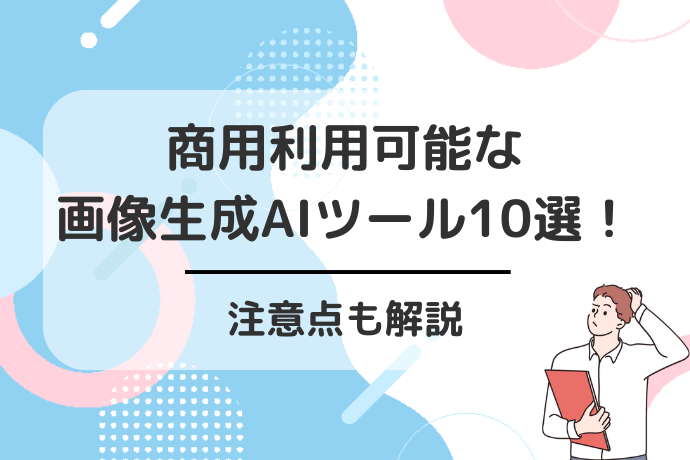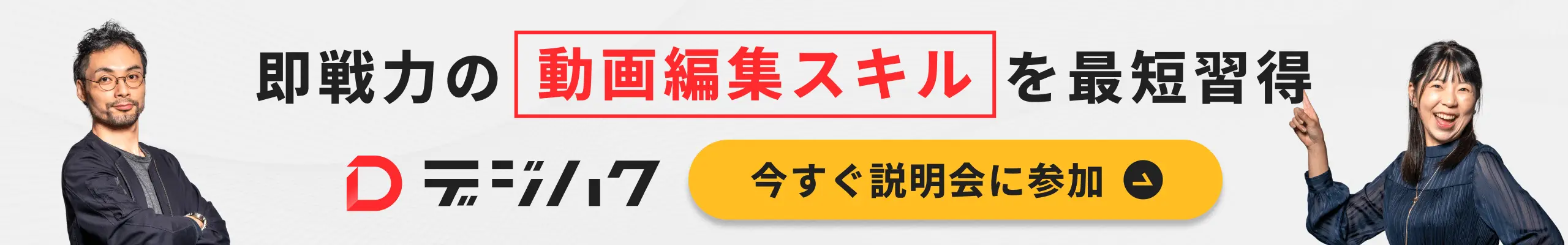近年、YouTubeショートはTikTokやInstagramリールに並ぶ注目の縦型動画フォーマットとして、多くのクリエイターや企業に活用されています。
しかし、「思ったより再生されない」「昨日まで1万再生だったのに、突然落ち込んだ」といった声も少なくありません。
実は、その裏にはYouTube独自のアルゴリズムと再生回数のカウント方法の仕組みが密接に関係しています。
この記事では、YouTubeショートのアルゴリズムの仕組みから、再生回数が伸び悩む原因、再生数を伸ばすための具体的な対策、さらには収益化や他SNSとの違いまで、徹底的に解説していきます。
YouTubeショートのアルゴリズムと再生回数カウントの仕組み
YouTubeショートは通常の動画と異なり、視聴者の行動データをリアルタイムで解析しながら表示するアルゴリズムが組み込まれています。
特に重要視されているのが、動画を最後まで見られたかどうか(視聴完了率)と、その後にユーザーが取った行動です。
例えば、動画を最後まで見たあとに「いいね」や「チャンネル登録」をすると、アルゴリズムは「この動画は有益だ」と判断し、他のユーザーにも積極的に表示します。
一方で、すぐにスワイプされてしまうとその動画の評価は下がり、再生数が伸びにくくなります。

このように、YouTubeショートでは「再生された数」そのものよりも「どう再生されたか」が重要であり、視聴者のエンゲージメントが表示頻度を大きく左右する仕組みになっています。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

最近変更されたショート動画の再生回数カウント方法は?
YouTubeは2023年以降、ショート動画の再生回数カウントの仕組みに一部変更を加えました。
従来は、ショート動画が1秒以上再生された時点でカウントされていましたが、現在は2秒以上の視聴を「再生」として認識するように変更されています。
これは、誤ってスワイプして再生された“意図しない視聴”を排除し、より正確にコンテンツの価値を判断するための施策です。
また、同じユーザーが短時間に繰り返し視聴した場合のカウントも、制限されるようになりました。
これにより、一部の“ブースト”行為が通用しにくくなり、より質の高いコンテンツが評価されやすい環境になっています。
そのため、過去と比べて再生回数の伸びが鈍化したように見えることもありますが、それは“質”を求めるアルゴリズムへと変化した結果とも言えるでしょう。
通常動画とショート動画の違い
YouTubeショートと通常動画(横長動画)では、視聴される目的やユーザーの行動、表示アルゴリズムの構造がまったく異なります。
- 尺(長さ):通常動画は数分〜数十分、ショート動画は60秒以内。
- 表示場所:通常動画は検索結果や関連動画欄に表示されるのに対し、ショート動画は「ショートフィード」に表示され、自動再生されながら縦スクロールで流れていきます。
- ユーザーの意識:通常動画は“見よう”と思って探して視聴されるのに対し、ショートは“流れてきたから見た”という受動的な視聴が多いのが特徴です。
この違いを理解せずに通常動画と同じ感覚でショートを作ると、思うように再生数が伸びない原因にもなります。

ショートでは、「最初の数秒で視聴者の心を掴む」ことが何より重要なのです。
YouTubeショートの再生回数が伸びない・急に減った時の原因
「昨日までは1万回以上再生されていたのに、今日はなぜか伸びない…」そんな経験をしたことはありませんか?
YouTubeショートでは、アルゴリズムの特性や視聴者の行動、コンテンツの内容によって再生数が大きく変動することがあります。
一度表示されなくなるとフィードに乗る機会が減り、再生回数は急落します。
しかし、原因を正しく理解して改善すれば、再び伸ばすことも十分に可能です。
再生数が落ち込んだときこそ、分析と修正のチャンスです。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

見落としがちな基本的な原因
意外にも、再生数が伸び悩む原因の多くは基本的な設定ミスや準備不足にあります。
たとえば次のようなものです。
- タイトルが魅力的でない
- 適切なハッシュタグが設定されていない
- ショートとして正しい形式(縦型・60秒以内)でアップされていない
- 投稿時間帯がズレていてターゲットに届いていない
特に投稿直後の初動が重要なYouTubeショートでは、最初の数時間のパフォーマンスで今後の表示頻度が左右されます。
基本設定を疎かにしていると、どんなに中身が良くても埋もれてしまうのです。
コンテンツの質と視聴者の行動パターンに隠された原因
もう一歩踏み込んで見てみると、コンテンツの内容そのものが原因になっているケースも多くあります。
特に重要なのが以下の2点です。
- 動画の冒頭数秒で興味を引けていない
- 最後まで視聴されていない(視聴維持率が低い)
視聴者は流し見している状態が多いため、「何か面白そう」と思わせる瞬間が冒頭にあるかどうかが命です。
さらに、動画の途中で離脱されると「最後まで見る価値がない」と判断され、アルゴリズム上の評価が下がります。
また、コメントやいいねなどのエンゲージメントが少ない動画も、評価されにくくなります。

これは単に「良い動画を作る」だけでなく「視聴者の行動を引き出す動画」を意識することが求められるということです。
アルゴリズムの評価と外部環境の変化が引き起こす現象
YouTubeのアルゴリズムは常にアップデートされており、季節・時間帯・トレンドなどの外部要因の影響も受けやすい仕組みになっています。
たとえば、ある時期に似たジャンルの動画が急増したり、YouTube側の仕様変更で表示ロジックが変わることがあります。
その影響で今まで好調だった動画が突然フィードに乗らなくなり、再生数が落ちることも珍しくありません。
また、視聴者の行動パターンも時期や曜日によって変化します。
たとえば学生が多く見る時間帯と、社会人が多く視聴する時間帯では反応の出方がまったく異なる場合があります。

つまり、再生回数の変動は「動画の良し悪し」だけではなく、「外的な要因」と「システム側の変化」にも左右されるという点を忘れてはいけません。
YouTubeショートの再生回数を増やす・伸ばすための方法
YouTubeショートで再生回数を伸ばすには、運や偶然ではなく「仕組みに沿った工夫と改善」が不可欠です。
アルゴリズムは、どの動画を拡散するかを非常にシビアに見極めています。
そこで重要になるのが
- 「最初の印象」
- 「視聴者の離脱を防ぐ工夫」
- 「動画の見た目や音質」
- 「時代やニーズに合ったテーマ選び」
これらのポイントを抑えることで、ショート動画の評価は確実に上がり、表示される頻度や再生数の増加へとつながります。
以下で、それぞれの要素を詳しく解説します。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

冒頭の「掴み」を最重視する
ショート動画で最も大切なのは冒頭の1〜2秒です。
視聴者はフィードを指一本で高速にスワイプしています。
そこで「この動画は面白そう」「続きを見たい」と思わせる強烈な一言、驚きの映像、違和感のあるシーンを入れることが重要です。
例えば、
- 驚きの事実をナレーションで冒頭に言う
- 非日常的な映像や表情を最初に入れる
- 「○○を知らないと損します」といった引きの強い言葉
などが効果的です。

「続きを見たくなる動機」を冒頭で作ることが、再生回数アップの第一歩です。
視聴維持率を最大化する編集術
再生されても、途中で離脱されてしまえばアルゴリズム上の評価は下がってしまいます。
視聴維持率(どれだけ最後まで見られたか)を上げる編集の工夫が求められます。
具体的なテクニックとしては
- テンポのよい編集:1カットあたり2〜3秒で変化を入れる
- 効果音・BGMでリズム感を演出
- テロップを画面に常に表示し、視覚的な退屈を防ぐ
- 話の構成を「結論 → 理由 → まとめ」と逆構成にする
視聴者に「先を見たい」と思わせる仕掛けをちりばめることで、最後まで視聴される動画に近づけます。
高画質・高音質を心がける
意外と見落とされがちですが、画質や音質が悪いだけで即スワイプされることも多々あります。
特にスマートフォンで見るショート動画では、映像のクリアさや声の聞き取りやすさが第一印象に直結します。
推奨されるポイントは
- 解像度720p以上で撮影・出力
- ノイズのないマイクで録音(スマホマイクに外付けマイクを検討)
- 明るさを確保した撮影環境を用意
- 編集時に音量のバランスを調整
“プロっぽさ”は視聴者の信頼感にもつながります。

スマホ一台でも、十分に高品質な動画を作ることは可能です。
トレンドを意識したコンテンツ作成
どれだけ動画の内容が良くても、今の流れに合っていないテーマでは再生されにくいのが現実です。
YouTubeショートでは特にトレンドの波に乗ることが、拡散の起爆剤になります。
取り入れる方法としては
- YouTubeのショートフィードや急上昇からトレンドをチェック
- TikTokやX(旧Twitter)など他SNSのバズりネタを活用
- 季節・時事ネタ・話題の人物や商品を絡める
トレンドネタは“検索される”のではなく、“自然に流れてくるもの”として拡散されることが多く、ショート動画との相性が非常に良いです。
魅力的な動画を制作したいならデジハクがおすすめ!

「どうしても再生回数が伸びない」「見栄えのする編集ができない」「独学では限界を感じている」
そんな方にぜひ検討してほしいのが、動画編集スクール『デジハク』です。
デジハクは、未経験からでも実践的なスキルを身につけられるオンライン動画編集スクールで、YouTubeショートをはじめとしたSNS動画に特化したカリキュラムが魅力です。
デジハクが選ばれる理由
- プロの編集技術を基礎から体系的に学べる
- YouTubeやTikTokなどの縦型動画にも対応した実践カリキュラム
- 現役クリエイターによるマンツーマンの添削・指導あり
- 自宅で完結できる完全オンライン対応
特に、ショート動画で重要な「テンポ感」「冒頭の掴み」「視聴維持率を高める編集」など、独学では感覚頼りになりがちなポイントを理論とプロの視点から丁寧に指導してくれるのが強みです。
また、受講生の中には未経験から数ヶ月で案件を獲得した方や、YouTubeのチャンネル登録者を大きく伸ばした方も多数。
副業や転職、個人のSNS発信においても即戦力となるスキルが習得できます。

「本気でショート動画で結果を出したい」「視聴者を惹きつける編集力を身につけたい」という方にとって、デジハクは非常に心強い選択肢です。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

YouTubeの仕組みに合わせた設定と運用
YouTubeショートで再生回数を伸ばすには、動画の中身だけでなく投稿前後の「設定」と「運用」が鍵になります。
アルゴリズムは、動画の内容だけでなくタイトル・ハッシュタグ・視聴者の反応・投稿タイミングなども総合的に評価して拡散するかどうかを決定します。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

魅力的なタイトル
YouTubeショートのタイトルは、検索には直接表示されにくい一方で、アルゴリズムが動画の内容を判断する重要な指標となります。
さらに、フィードに表示された際、クリック率にも影響します。
効果的なタイトルのポイント
- 具体的かつ簡潔に:「○○するたった1つの方法」「知らないと損」など明快な言葉で
- 感情を動かす表現を入れる:「爆笑」「驚愕」「意外すぎる」など
- 数字や限定感を使う:「3選」「10秒でわかる」「今だけ」
短くても“気になる”要素があると、視聴者の指は止まりやすくなります。
適切なハッシュタグ
ハッシュタグは、ショート動画の拡散力を支えるサポート要素です。
特に以下の3点が重要です。
- 「#shorts」は必須:YouTubeがショート動画として認識するために必要
- ジャンル特化のタグを使う:「#美容」「#子育て」「#ガジェット」など
- トレンド系や話題性のあるタグを加える:「#2025最新」「#バズった動画」など
関連性の高いタグを使うことでアルゴリズムが適切な視聴者に届けやすくなり、表示頻度が向上します。
投稿時間帯を調整する
投稿する時間帯によって、動画の初動は大きく変わります。
ショートは「フィードでどれだけ早く反応を得られるか」が重要なため、視聴者がアクティブな時間に投稿することが不可欠です。
参考になる時間帯
- 平日:18〜22時(仕事・学校帰り)
- 休日:10〜13時(起床後〜昼過ぎ)
- 学生向けコンテンツなら放課後の16〜19時台も◎
自分のターゲット層が最もYouTubeを使うタイミングを意識することで、再生回数の初速が上がりやすくなります。
動画内でエンゲージメントを促す
YouTubeショートでは、視聴者のアクション(エンゲージメント)がアルゴリズムに強く影響します。
動画の中で自然に「いいね」や「コメント」を促す工夫を入れましょう。
たとえば
- 「あなたはどっち派?」など2択形式でコメントを促す
- 「面白かったら“いいね”してね!」とナレーションやテロップで呼びかける
- 「続きが気になる人はフォローしてね」とチャンネル登録の動機を与える
エンゲージメントの多い動画は、アルゴリズムが「価値のある動画」と判断し、より多くの視聴者に届けられやすくなります。
他のSNSでの初期流入を促す
YouTubeショート単体では初動が弱い場合でも、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LINEなど他のSNSを活用して視聴者を流入させることで、最初の数時間の再生数を底上げできます。
おすすめの活用法
- TikTokとYouTubeショートを同時投稿(タイトルと音源は少し変える)
- Instagramストーリーズで「YouTubeに新作アップ!」と告知
- Xで短いテキスト付きの切り抜きとYouTubeリンクを投稿
外部流入によって初動が強まれば、YouTube側のアルゴリズムも加速して表示回数が伸びやすくなります。
データ分析とPDCAサイクルで継続的に行う
バズる動画は一瞬でも、再現性のある運用には分析と改善の積み重ねが必要です。
YouTube Studioのアナリティクスを使えば、ショートでも詳細なデータが確認できます。
注目すべきポイント
- 視聴維持率(どこで離脱されたか)
- インプレッション数とクリック率
- いいね数やコメント数の推移
これらをもとに、動画の構成やタイトル、投稿時間を見直し「投稿→分析→改善」のPDCAサイクルを回すことが、継続的な成長につながります。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

再生されやすいショートの作り方のポイント
YouTubeショートで再生数を伸ばすには、見た目の工夫・視聴体験の工夫・戦略的な編集が不可欠です。
アルゴリズムに評価されることはもちろん、視聴者の“指を止める”ための細かな工夫を積み重ねることで、ショートは大きな反応を生みます。
サムネイルを意識する
ショート動画では基本的に「サムネイルが自動表示される」ため、通常動画のように自由にデザインしたサムネイルを設定することはできません。
しかし、動画の冒頭1フレーム目がそのままサムネイルとして表示される場合があるため、最初のシーンが非常に重要です。
おすすめの対策
- 冒頭に大きめのテロップを配置する
- 印象的なシーンや表情でスタートさせる
- 色合いや構図を意識して「映える」絵作りを心がける
一目で「見てみたい」と思わせる画が用意できれば、ショートフィード上でも指が止まりやすくなります。
音声はすべて字幕をつける
YouTubeショートの視聴環境では、音声をオフにして見るユーザーが非常に多いという特徴があります。
通勤中やカフェなど、音が出せない環境でも内容が伝わるように、すべての音声には字幕をつけることが基本です。
ポイント
- 聞き取りやすい言葉をそのままテキスト化
- 1〜2行ずつ、画面を圧迫しないサイズで表示
- 話し方の抑揚に合わせてフォントや色を工夫するとより効果的

字幕を加えることで視聴者の離脱が減り、視聴維持率の向上=アルゴリズムからの高評価へとつながります。
切り抜き動画を活用する
再生されやすいショートを効率よく作る方法の一つが「切り抜き動画」の活用です。
元々のコンテンツ(ライブ配信、長尺動画、インタビューなど)から反応が良かった瞬間や印象的なセリフを短く編集して再投稿することで、手間を抑えながら再生回数を稼げる可能性があります。
切り抜き動画のメリット
- すでに評価されたコンテンツを再利用できる
- 「見たことある人」にも短く届け直せる
- シリーズ化すれば、チャンネル全体の再生数底上げにも貢献
特に「神回」「爆笑シーン」「感動の瞬間」など、感情が大きく動く部分をピックアップするのがポイントです。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

YouTubeショートの再生回数に関するよくある質問


再生されない原因を分析して、次回の改善に活かしましょう。
ただし、ガイドライン違反やチャンネルの方向性に合わない場合は削除してもOKです。


・登録者1,000人以上 & ショート動画1,000万再生(過去90日)
・通常のYouTubeパートナープログラムに参加
収益の目安は1万再生で数十〜数百円程度。
集客や認知目的で使うのが現実的です。


一方でTikTokは拡散力に優れ、特に若年層に強く、Instagramリールはフォロワーとのつながりやブランディング向きです。
それぞれのプラットフォームで特性が異なるため、目的に応じて使い分けるのが効果的です。


ただし、トレンドを捉えた動画やテンポの良い編集ができれば、1本で数万回以上再生されることも十分可能です。


動画内で自然に「続きが気になる方はチャンネル登録を」と促したり、長尺動画への導線を用意することも効果的です。
また、プロフィールやチャンネルの第一印象を整えておくことで、登録されやすくなります。
まとめ
YouTubeショートは、短い動画ながらも再生回数を伸ばすには戦略が必要なプラットフォームです。
アルゴリズムの特性や視聴者の行動パターンを理解し、冒頭の掴みや視聴維持率を意識した編集、高画質・高音質の動画制作がポイントになります。
また、タイトルやハッシュタグ、投稿時間帯の工夫、他SNSとの連携も重要です。
再生回数が伸び悩んだ時は焦らず原因を分析し、改善を重ねることで確実に結果は変わります。
さらに、YouTubeの仕組みに合わせて設定や運用を最適化し、データを活用してPDCAを回すことが成長の鍵です。

ショート動画はチャンネル登録者増加や収益化にもつながる強力なツールです。
\動画編集を学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ


 で
で