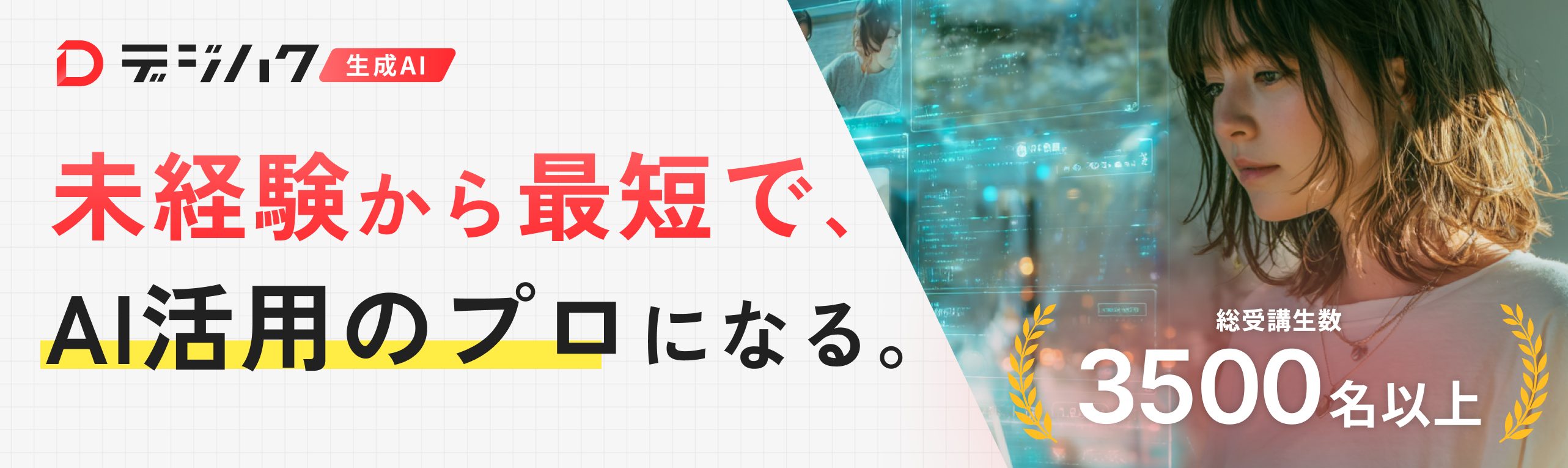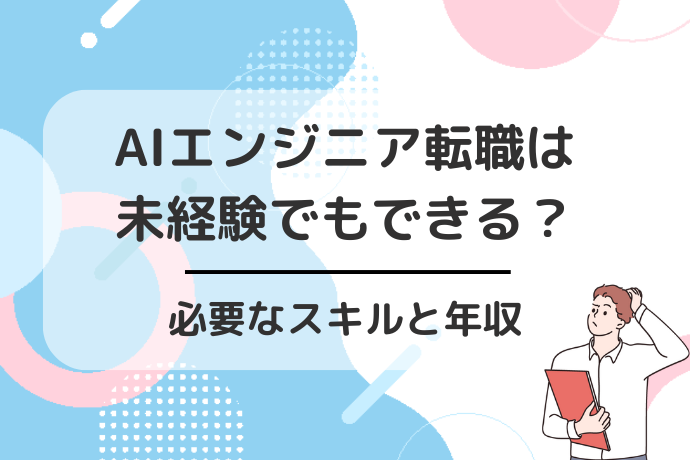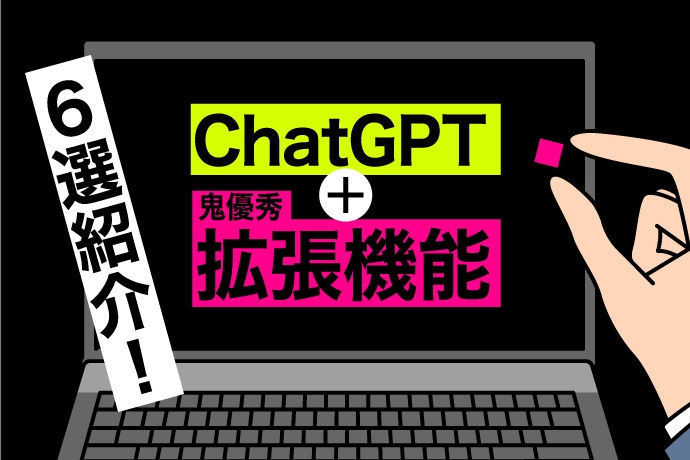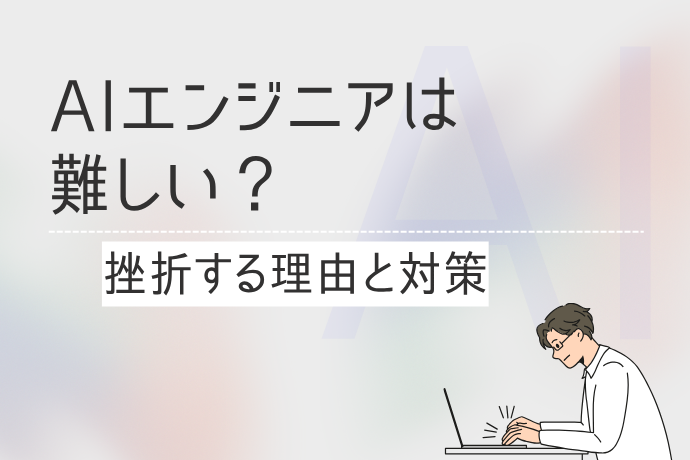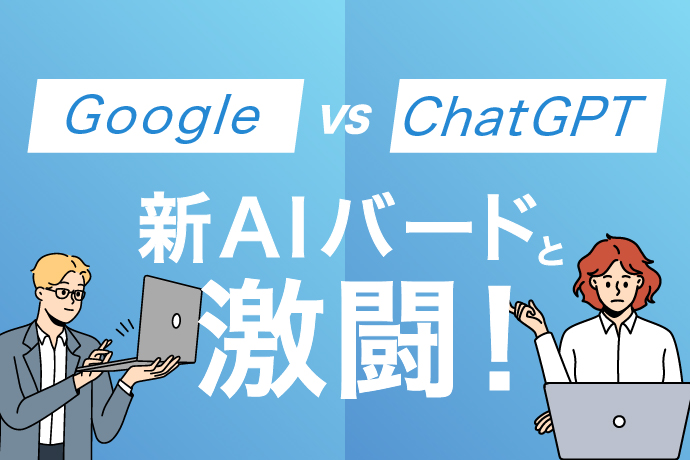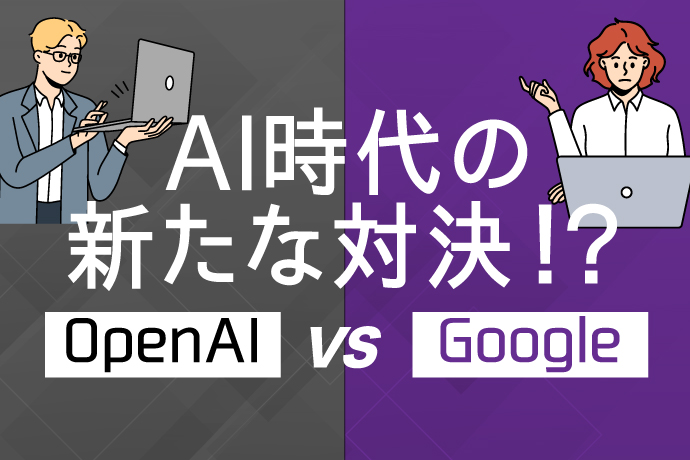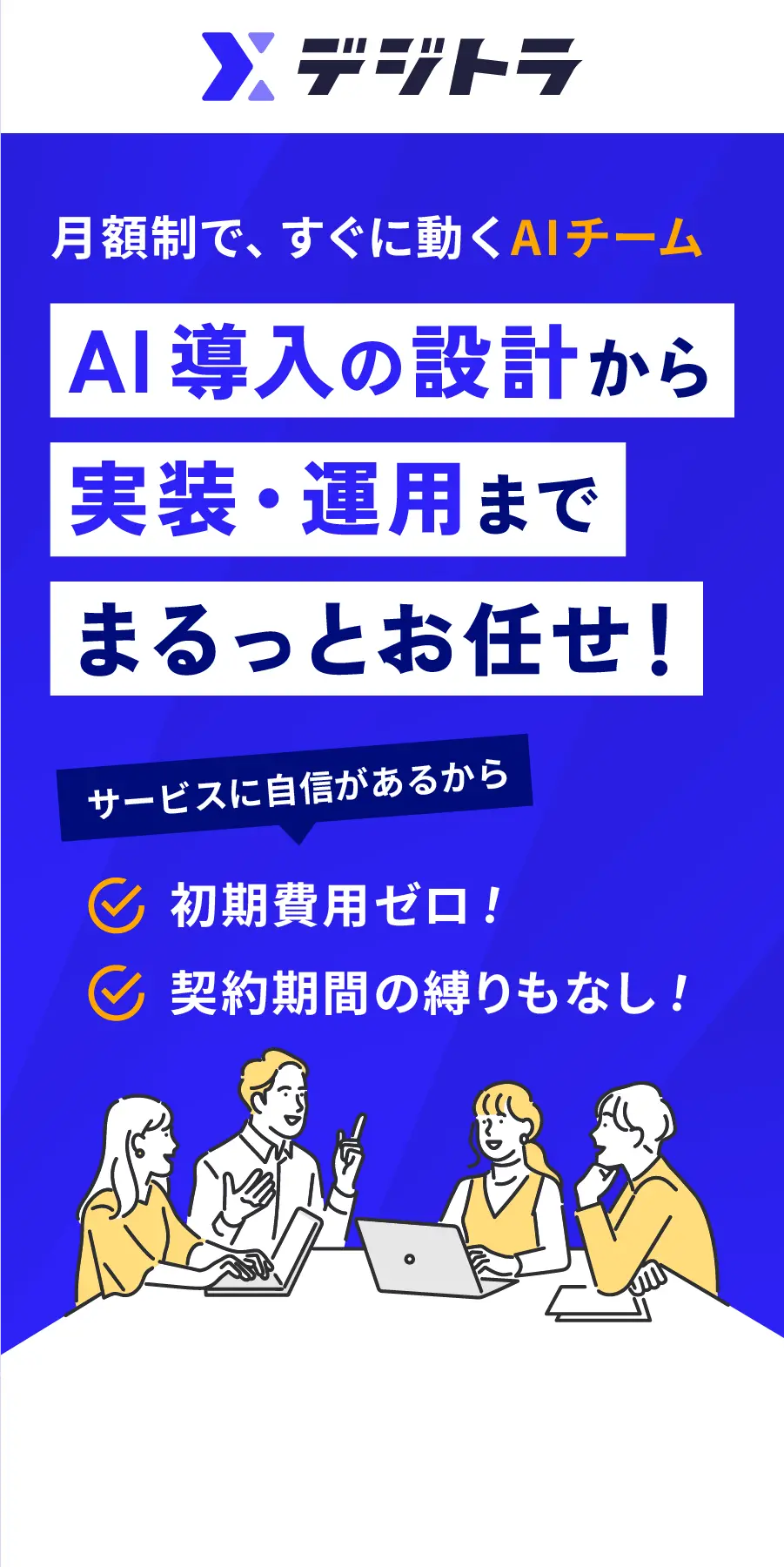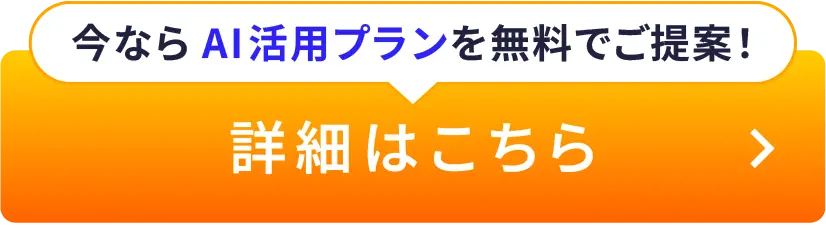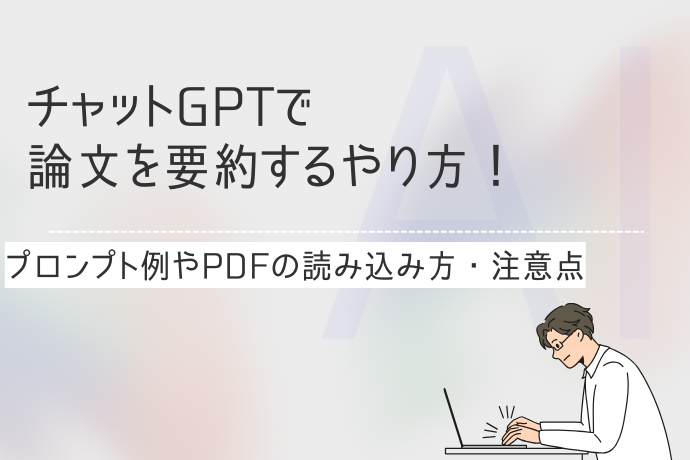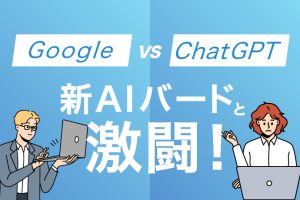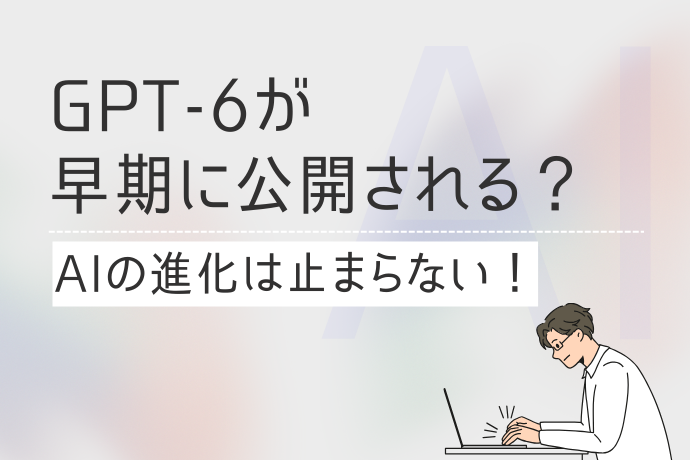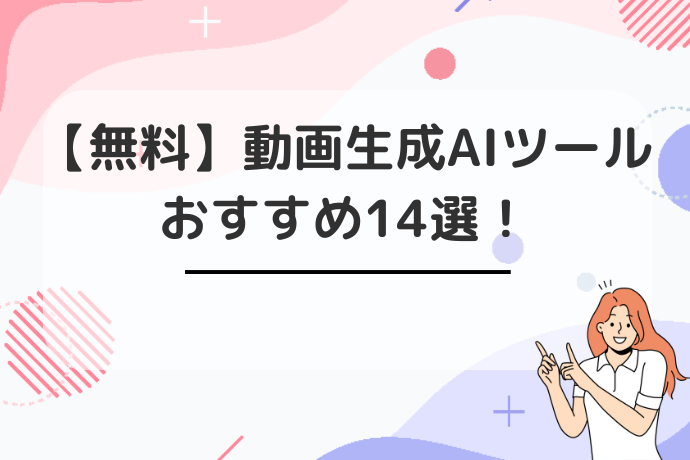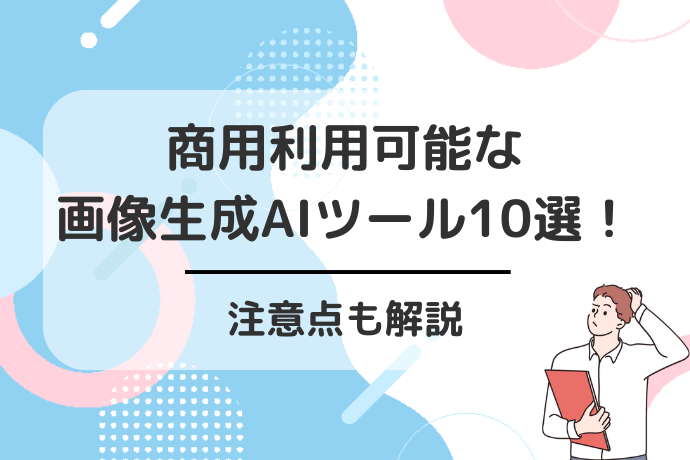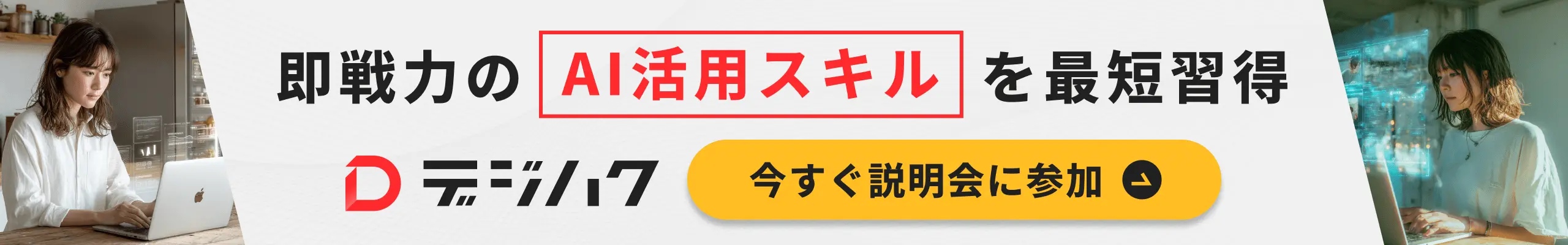近年、生成AIや機械学習といったテクノロジーの進化により「AIエンジニア」という職業が急速に注目を集めています。
多くの企業がAI人材の確保に力を入れており、需要は年々高まる一方です。
そんな中で「プログラミング未経験でもAIエンジニアになれるの?」「どうすれば転職できるの?」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
この記事では、未経験からAIエンジニアを目指す方に向けて、必要なスキルや資格、おすすめのスクール、転職の流れまで、わかりやすく解説していきます。
AIエンジニアはプログラミング未経験でもなれる?
結論から言うと、プログラミング未経験からでもAIエンジニアを目指すことは可能です。
実際に、異業種からの転職や、文系出身でAI分野に挑戦する人も増えています。
AIエンジニアというと、高度な数学やプログラミングスキルが必須というイメージが強いかもしれません。

しかし、現在では初学者向けにわかりやすく設計されたオンライン学習サービスやスクールが多数あり基礎から順を追って学べる環境が整っています。
特に最近では、ノーコードやローコードのツールも発展しており、すべてを一からプログラミングする必要がないケースも増えてきました。
また、AIエンジニアの中にも「開発」に特化したタイプと「AIの運用・データ分析」に強みを持つタイプなど、さまざまな役割があります。
とはいえ、最低限のプログラミング知識(Pythonなど)と数学的思考は必須です。
完全に知識ゼロのままでは厳しいですが、未経験から学び始めて十分にキャリアチェンジを目指せる職種だと言えるでしょう。

まずは小さなステップとして、Pythonの基礎やデータの扱い方から学び、少しずつAIの世界に慣れていくことをおすすめします。
未経験からAIエンジニアになるためのロードマップ
AIの基礎知識を身につける
AIや機械学習の理解には、プログラミングやデータ分析の基本が不可欠です。
入門書やオンライン講座、無料セミナーなどを活用して、簡単なデータ操作や分析ができるレベルを目指しましょう。
機械学習・生成AIの実践スキルを習得する
機械学習モデルの作成や評価方法、データ前処理、生成AIの活用方法などを学びます。
UdemyやCoursera、Google「AI for Everyone」などのオンライン講座を活用すると効率的です。
小規模な演習プロジェクトを通じて手を動かしながら理解を深めることが重要です。
ポートフォリオを作成する
例えば、データ分析レポート、画像生成AIを使った作品、簡単なAIアプリなどです。
GitHubやブログに成果物を公開することで転職時に自分のスキルを具体的にアピールできます。
資格や修了証で信頼性を高める
企業の採用担当者にとって、学習の証明は大きな安心材料になります。
転職活動・実務経験の積み上げ
未経験の場合は、学んだ知識やポートフォリオを活用して「問題解決力」や「学習意欲」をアピールすることが重要です。
実務経験を通してさらにスキルを磨き、AIエンジニアとして活躍できる環境に進みましょう。
未経験でもAIエンジニア転職を成功させる方法
未経験から転職を成功させるには、スキルの証明と実績作りが鍵です。
まず、ポートフォリオとして簡単なAIプロジェクトを作成し、実務で使えるスキルを示します。
次に、スクールやオンライン講座で学んだ知識を活用し、資格や修了証を取得することで信頼性を高めます。
また、転職活動では「学習意欲」と「問題解決力」をアピールすることも重要です。
面接では、未経験であってもAIを活用してどのように課題を解決できるかを具体例を交えて説明すると、企業側に好印象を与えられます。
さらに、インターンや副業で実務経験を積むことも、採用の可能性を大きく高める方法です。
AIエンジニアに必要なスキル
AIエンジニアを目指すなら、いくつかの大事なスキルを身につけておく必要があります。
ただ「プログラミングができればOK」というわけではなく、AIを動かすための知識やデータを扱う力、そして実際の現場で使える技術が求められます。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

1. プログラミングスキル(特にPython)
AI開発でよく使われるのが「Python(パイソン)」というプログラミング言語です。
使いやすくて、AIや機械学習に強いライブラリ(便利な機能のセット)がたくさんあります。
たとえば「TensorFlow」や「PyTorch」などは、AIを作るときに欠かせないツールです。
2. 数学と統計の基礎
「えっ、数学?」と思うかもしれませんが、実はAIの仕組みには数学が関わっています。
特に、線形代数や確率・統計の基本は知っておくと役に立ちます。
苦手でも、スクールなどでゆっくり学べば大丈夫です。
3. 機械学習・深層学習の知識
AIの中心的な技術がこの「機械学習」と「深層学習(ディープラーニング)」です。
たとえば、AIが画像を認識したり文章を作ったりするのは、これらの仕組みを使っています。
基本的な考え方や使い方をしっかり押さえておきましょう。
4. データを扱うスキル
AIはデータを使って学習します。
ぞのため「データを集めて、きれいに整える」作業もとても重要。エクセルのような操作に加えて、データベースやAPIの使い方も知っておくと仕事の幅が広がります。
5. クラウドや開発の知識
AIを実際に動かすには、クラウド(AWSやGCPなど)やアプリ開発の知識もあると便利です。
全部いっぺんに覚える必要はありませんが、スクールなどで少しずつ学べます。
6. コミュニケーション力も大事
AIエンジニアは一人で作業するだけでなく、他のエンジニアやビジネス担当と協力して仕事を進めます。
なので、相手の話を理解したり自分の考えをわかりやすく伝えたりする力も大切なんです。
つまり、AIエンジニアに必要なのは「プログラミング+数学+AIの知識+実践的な技術+コミュニケーション力」のバランス。

スクールなら、これらを順番に学んでいけるようになっているので、未経験からでも安心して始められます。
AIエンジニア転職に有利な資格はある?
AIエンジニアとしてのスキルを客観的に証明する手段として、資格取得は大いに役立ちます。
特に未経験から転職を目指す場合、知識や学習意欲をアピールする材料として評価されることが多いです。
以下は、AIエンジニア転職に役立つ代表的な資格です。
1. G検定(ジェネラリスト検定)
一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催。
AIの基礎知識や倫理、活用事例などを幅広く学べる検定で、未経験者にも人気があります。
2. E資格(エンジニア資格)
こちらもJDLA主催で、G検定よりも専門的な内容を扱います。
ディープラーニングの理論と実装力が問われるため、AIエンジニアとしての本格的な技術力をアピールできます。
3. Python3 エンジニア認定試験
Pythonの基本文法や応用力を測る試験で、AI開発の基礎であるPythonスキルの証明になります。
4. AWS 認定資格(例:AWS Certified Machine Learning)
クラウド環境でのAI構築に関わる知識を問う資格。AIとクラウドの両方を活用できる人材としての評価が高まります。
これらの資格は「必須」ではありませんが、履歴書や面接で説得力のある材料となります。

独学やスクール学習と並行して、資格取得を目指すのも一つの戦略です。
独学でAIエンジニアに転職できる?
独学でAIエンジニアに転職することは可能です。
実際に書籍やオンライン教材、YouTubeなどを活用してスキルを磨き、転職を実現した人もいます。
しかし、現実としてはかなりの努力と計画性が求められる道でもあります。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

独学でAIエンジニアを目指すメリット
- 費用を抑えられる:書籍や無料教材を使えば、コストをかけずに学べる。
- 自分のペースで学べる:ライフスタイルに合わせて学習スケジュールを組める。
- 自主的な学習能力がアピール材料に:独学で成果を出せば、やる気や継続力の証明になる。
ただし独学にはデメリットも
- 学習の順序がわかりにくい:何から始め、どう深めていくべきか迷いやすい。
- つまずいたときに相談できない:技術的なエラーや理論の理解で詰まりやすい。
- ポートフォリオが作りにくい:実務経験がないと、転職でアピールできる材料に欠ける。
AIエンジニアとしての転職には、スキルの「証明」と「実績」が鍵となります。
独学でも成果を出すには、学習だけでなく「自作のAIモデルを公開する」「GitHubでコードを発信する」「コンペティションに参加する」といったアウトプットも積極的に行うことが必要です。
また、独学で一定のレベルに達した後、転職サポートがあるスクールや転職エージェントを併用するのも効果的です。
独学は自由度が高い一方で、サポートがないことが大きな壁になります。

自分に合った学習方法を見極めながら、必要に応じて外部サービスも活用しましょう。
AIエンジニアに転職するためにはスクールに通うのが近道!
未経験からAIエンジニアを目指すなら、スクールに通うのがもっとも効率的な方法です。
AIやプログラミングの学習は範囲が広く、独学だと何から始めればいいのかわからず、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
その点、スクールでは実務に沿ったカリキュラムが組まれており、基礎から応用までを順序よく学べます。
わからないことがあっても講師やメンターにすぐ質問できるため、つまずいても安心です。
さらに、スクールでの学習を通じて、AIモデルやデータ分析などの実践的なポートフォリオを作成できるのも大きな強みです。
これは転職活動の際に、自分のスキルをアピールする材料になります。
多くのスクールでは転職サポートも行っており、履歴書の添削や面接対策、求人紹介など、転職まで一貫して支援してくれます。

費用はかかりますが、短期間で実務レベルのスキルを身につけられることを考えれば、十分に価値のある投資といえるでしょう。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

AIエンジニアを学べるおすすめのスクール
「AIエンジニアになりたいけど、どのスクールを選べばいいの?」そんな方のために、未経験でも安心して学べるAIエンジニア向けスクールを紹介します。
それぞれ特徴が違うので、自分に合ったスクール選びの参考にしてください!
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

DMM 生成AI CAMP

画像引用:DMM 生成AI CAMP
DMMが提供する「生成AI CAMP」は、ChatGPTや画像生成AIといった最新の生成AI技術に特化した学習プログラムです。
短期間で現場レベルのスキルを身につけることを目的としており、受講生はプロンプトエンジニアリングやAIツールの活用法を実践的に学べます。
さらに、現役エンジニアのサポートが受けられるため、未経験者でも安心して取り組める環境が整っています。
生成AIに興味があり、将来的にAIを使った業務やサービス開発に携わりたい人にはぴったりのスクールです。
SAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)

SAMURAI ENGINEERは、一人ひとりに合わせたオーダーメイドのカリキュラムが特徴のマンツーマン指導スクールです。
AI分野の学習だけでなく、プログラミングの基礎から応用までを幅広くカバーしており、個々の目標に合わせて柔軟に内容を調整してくれるのが魅力です。
また、学習後の転職・副業支援も手厚く、キャリアチェンジを考えている人にもおすすめです。
講師と密にコミュニケーションを取りながら、自分のペースで着実に学んでいきたい人に最適です。
Winスクール

画像引用:Winスクール
Winスクールは、全国に教室を持つ通学型のITスクールで、初心者でも安心してスタートできる丁寧な指導に定評があります。
AIや機械学習の入門から専門的な知識までを段階的に学べるカリキュラムが用意されており、教室での直接指導に加えて、オンラインでも受講可能です。
地方在住者や、対面での学びを重視する人にとっては特に魅力的な選択肢となります。
教室で仲間と一緒に学びたい人や質問をすぐに解決したい人におすすめです。
.Pro(ドットプロ)

画像引用:.Pro(ドットプロ)
.Pro(ドットプロ)は、少人数制での対面授業と実務重視のプロジェクト学習が特徴のスクールです。
受講生同士で交流しながら、チーム開発やプレゼンテーションなど実践的なスキルを身につけることができます。
AIエンジニアとして必要な知識を、より実務に近い形で学びたい人にはぴったりの環境です。
実際の仕事を想定した課題に取り組むため、卒業後の即戦力としての活躍が期待できます。
学びのモチベーションを保ちやすい、仲間とのつながりが欲しい人にも向いています。
TechAcademy(テックアカデミー)
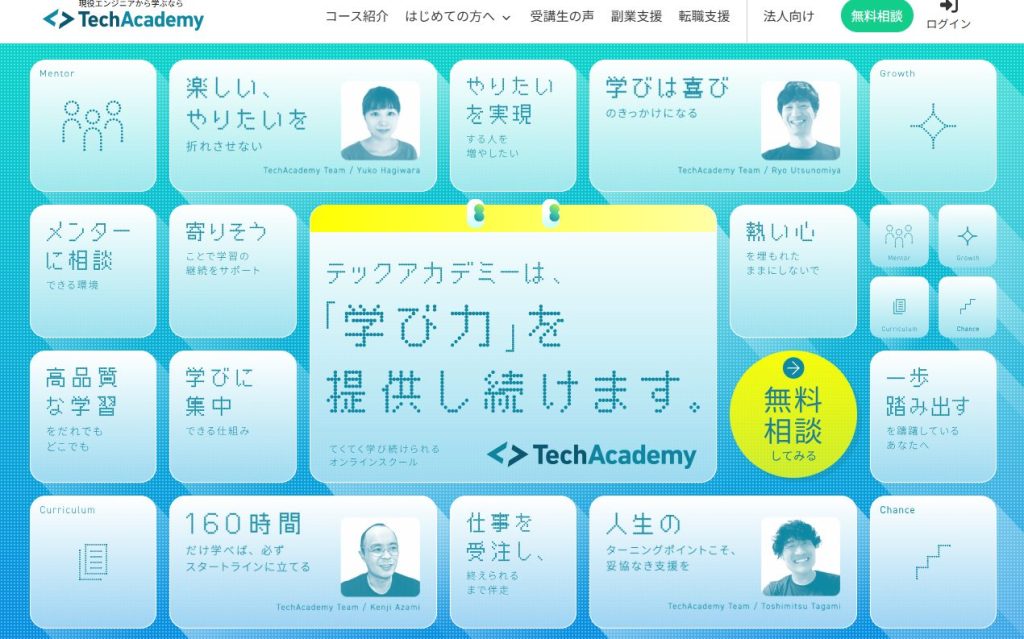
TechAcademyは、完全オンラインで学べる人気のプログラミングスクールで、忙しい社会人や地方在住の方でも柔軟に学べるのが魅力です。
AIコースでは、Pythonや機械学習、データサイエンスなど、現場で活用されている技術を体系的に学習できます。
週2回のメンタリングでは現役エンジニアが直接サポートしてくれるため、疑問点もすぐに解消できます。
オンライン学習を自分のペースで進めたい人や、仕事と両立してスキルを身につけたい人にぴったりです。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

AIエンジニアスクールの選び方7つのポイント
AIエンジニアスクールを選ぶ際は、目的やライフスタイルに合ったスクールを選ぶことが大切です。
以下の7つのポイントを基準に比較・検討することで、自分に最適なスクールを見つけやすくなります。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

1. 学習内容・カリキュラムの充実度を確認しよう
まず最も大事なのは「自分が身につけたいスキルが学べるか」です。
AIと一口に言っても
- 画像認識
- 自然言語処理
- 機械学習
- ディープラーニング
- 生成AI(ChatGPTのような技術)
など、多くの分野に分かれています。
スクールによってはPythonの基礎しか扱わない場合もあれば、実際のAI開発プロジェクトに近い演習まで行えるところもあります。
できれば、カリキュラム内容が「理論+実践」で構成されていて、AIモデルの構築やAPI活用、データ解析など、実務でも活かせる内容になっているかをチェックしましょう。
2. 自分に合った学習形式を選ぼう(オンライン・通学・ハイブリッド)
AIスクールには、オンライン完結型、教室通学型、その両方を組み合わせたハイブリッド型があります。
例えば、地方に住んでいる方や働きながら学ぶ人にはオンラインが向いていますし、手取り足取り教えてほしい人や対面でモチベーションを維持したい人は通学型が合うかもしれません。

オンラインでも「動画を見て自習するだけ」なのか、「現役エンジニアがマンツーマンでサポートしてくれる」形式なのかで、学習の質は大きく変わります。
3. サポート体制の手厚さは意外と重要
初心者にとって、つまずいたときのサポート体制はとても重要です。
質問したときにすぐ返事が返ってくるか、チャットだけでなくZoomなどでの個別指導があるか、学習の進捗を管理してくれる仕組みがあるかなどを確認しましょう。
特に独学でつまずいた経験のある人ほど「いつでも質問できる」「わからないところをその場で教えてくれる」環境は安心感につながります。
4. 就職・転職支援の内容はスクールごとに差がある
AIエンジニアとして就職・転職を目指す人にとっては、キャリア支援が充実しているかどうかも大きなポイントです。
スクールによっては
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 模擬面接
- 求人紹介
- ポートフォリオ制作のサポート
まで行ってくれるところがあります。
転職保証制度があるスクールでは、一定期間内に就職が決まらなければ受講料が返金されるケースもあります。
サポートの質と実績はしっかり確認しておきましょう。
5. 費用だけでなく、補助金や給付金もチェックしよう
AIスクールの費用はピンキリで5万円ほどで受けられるものもあれば、50万円を超えるプランもあります。
ただし、国の「専門実践教育訓練給付金」や「リスキリングを支援する補助金」などを活用すれば、最大70%程度の受講料が補助されることもあります。

スクールによっては、申請方法を丁寧に教えてくれたり、対象講座として認定されていたりするので金額だけでなく「最終的な自己負担額」で比べるのがポイントです。
6. 受講期間やコースの柔軟さも確認しよう
スクールのコースは、最短1ヶ月から半年・1年と幅があります。
「できるだけ短期間で学びたい」「仕事の合間にじっくり取り組みたい」など、自分のペースに合った学習スケジュールを選びましょう。
また、「平日の夜だけ受けられるコース」や「途中でレベルアップできるコース」など、柔軟性のあるスクールも増えています。
途中で挫折しないよう、無理のない学習期間かどうかも重要です。
7. 受講生の評判・口コミはリアルな判断材料
最後に、実際に受講した人の口コミや卒業後の進路は非常に参考になります。
SNSや口コミサイト、公式サイトの卒業生インタビューなどをチェックし「本当に学べたか」「転職できたか」「サポートが丁寧だったか」など、リアルな声に目を通しましょう。

悪い口コミが1つもないスクールは逆に怪しいので、ポジティブ・ネガティブ両方の意見を見たうえで判断するのがポイントです。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

AIエンジニア転職活動の流れ
スキルの習得
Python、機械学習、データ分析、数学の基礎などを学び、実務で使えるレベルを目指します。
独学やスクールを活用する方法があります。
ポートフォリオの作成
GitHubなどにコードを公開して、スキルの証明となるポートフォリオを準備しておくと、転職時のアピール材料になります。
応募書類の準備
未経験でも学習の過程や取り組んだ内容、ポートフォリオについてしっかりと記載することでやる気や能力を伝えることができます。
求人の検索・応募
AI未経験でも応募可能なポジションもあるので、条件を見極めてエントリーしましょう。
書類選考・面接対策
自身のポートフォリオの説明や、学んできた内容をわかりやすく話せるように練習しておくと安心です。
スクールの模擬面接を活用するのも効果的です。
内定・入社準備
入社前の学習課題が出ることもあるため、最後までスキルアップの意識を持って準備を進めることが大切です。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

AIエンジニアの年収はどれくらい?
AIエンジニアに転職すると、年収が大きく上がる可能性があります。
特にIT業界未経験の職種からの転職であれば、年収が100万円以上アップするケースも珍しくありません。
国内のAIエンジニアの平均年収は、おおよそ500万円〜800万円前後といわれています。
経験やスキル、企業の規模によっては、初年度から600万円以上のオファーが出ることもあります。
さらに、機械学習や深層学習に関する実務経験を積んでいけば、年収1,000万円以上を狙えるポジションも存在します。
また、AIエンジニアは人材不足が続いているため、転職市場では引く手あまたの状態です。
スキルを伸ばし続けることでより高待遇の企業へとキャリアアップしやすくなるのも、この職種の大きな魅力です。

ただし、未経験からスタートする場合は、最初の年収がそれほど高くないこともあります。とはいえ、AI分野は成長スピードが早く、1〜2年で年収アップを実現する人も多いため、長期的に見れば非常に将来性のある選択肢と言えるでしょう。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

AIエンジニアとして市場価値を高め続けるには?
AI技術は日々進化しているため、常に最新の知識を学び続けることが大切です。
論文やオンライン講座で新しい技術をキャッチアップし、実際のプロジェクトで経験を積むことが市場価値向上につながります。
また、自分の成果をGitHubやブログで発信することでスキルをアピールできます。
加えて、チームでのコミュニケーション能力も重要です。
AIエンジニアは多くの人と協力して仕事を進めるため、説明力や調整力が求められます。
資格取得や専門分野のスキルアップも、市場価値を高める手段の一つです。

こうした努力を続けることで、長く活躍できるAIエンジニアになれます。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

AIエンジニアの転職に関するよくある質問


働く企業や職場環境によって違いが大きいため、自分に合った職場を選ぶことが大切です。


特に人材不足のため、将来的にも安定した需要が見込まれます。


ただし若手に比べてキャリアチェンジのハードルは高いため、実務経験や資格、ポートフォリオを充実させることが成功のポイントになります。


また、複雑なデータやアルゴリズムの調整に時間がかかることもあります。


また、問題解決が好きで論理的思考が得意な人、チームでのコミュニケーションを大切にできる人もAIエンジニアに適しています。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ

まとめ
AIエンジニアは未経験からでも挑戦できる将来性の高い職種です。
必要なスキルや知識はスクールや独学で身につけることができますが、効率よく確実に習得するためには専門のスクールを利用するのが近道です。
転職活動では、スキルの証明となるポートフォリオの作成や、履歴書・面接対策が重要となります。
AIエンジニアの需要は今後も伸び続けるため、市場価値の高い人材になれば年収アップも期待できます。
年齢に関係なく、継続的に学び続ける意欲があれば転職は十分可能です。

変化の早い分野だからこそ、常に最新の技術をキャッチアップし実践経験を積むことが大切です。
\生成AIを学ぶならデジハク!/
デジハクの公式サイトへ


 で
で