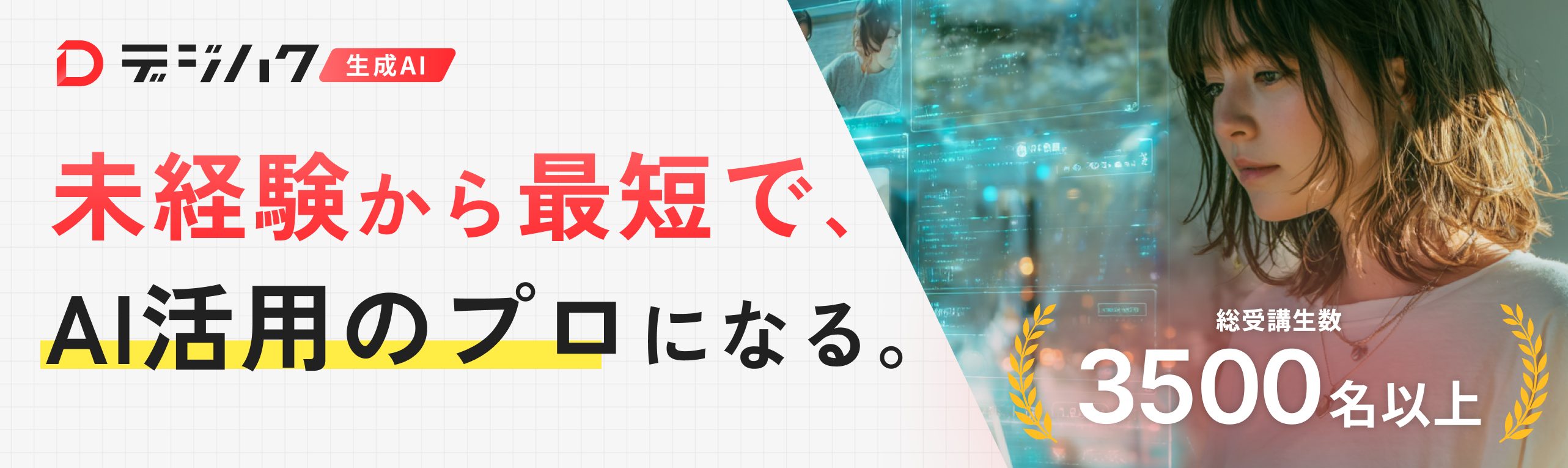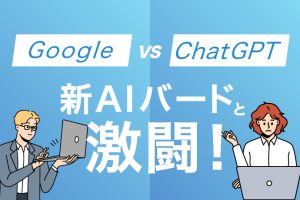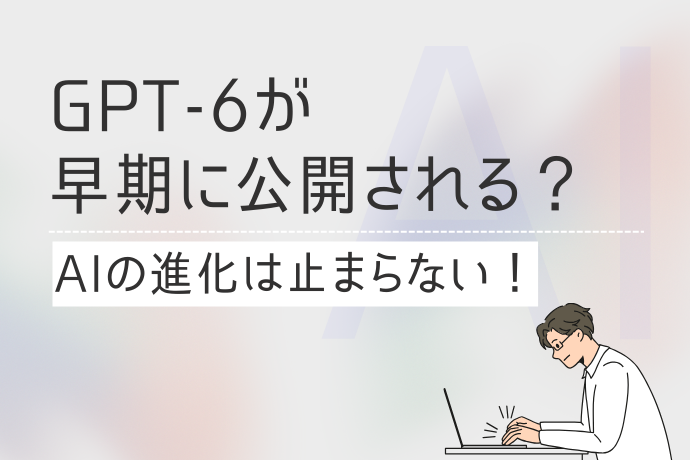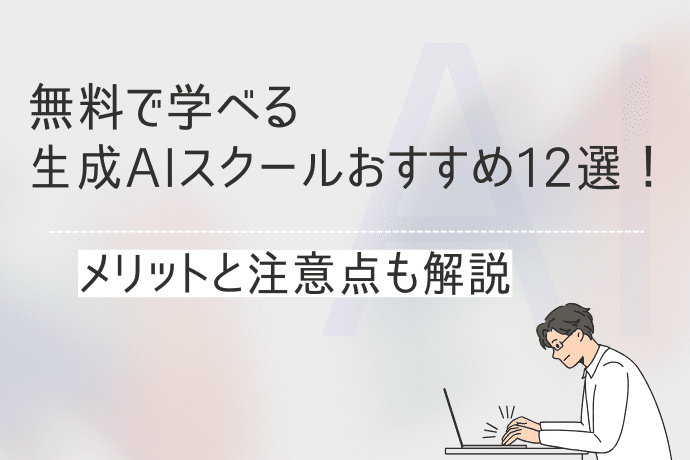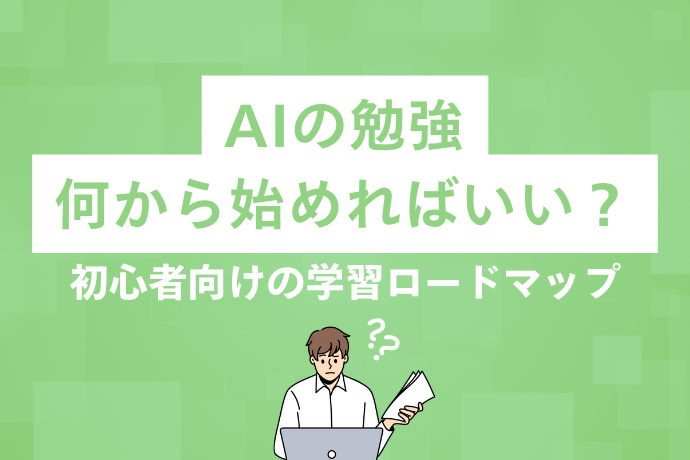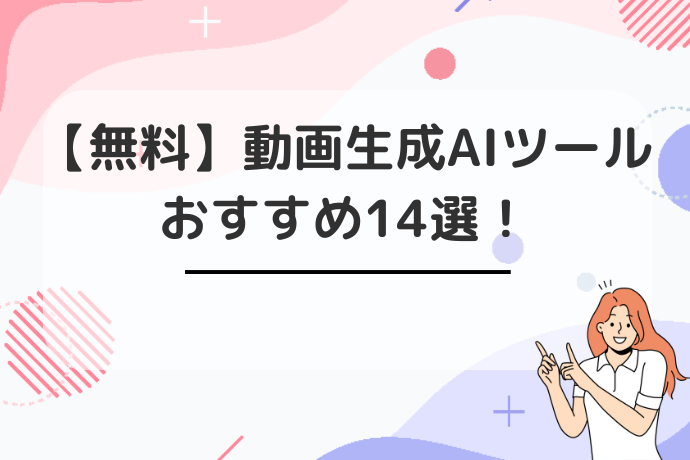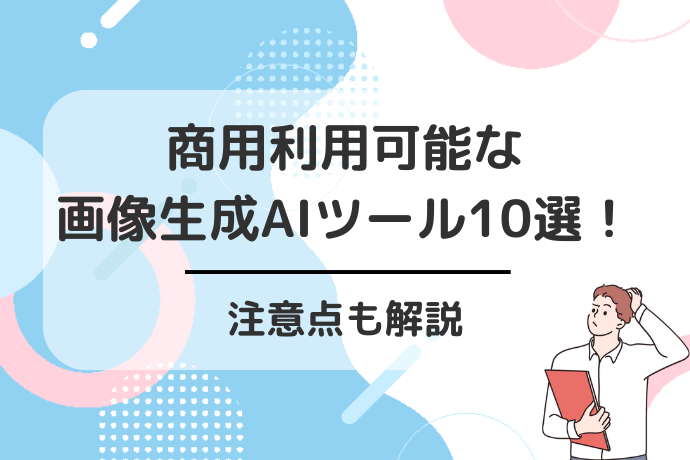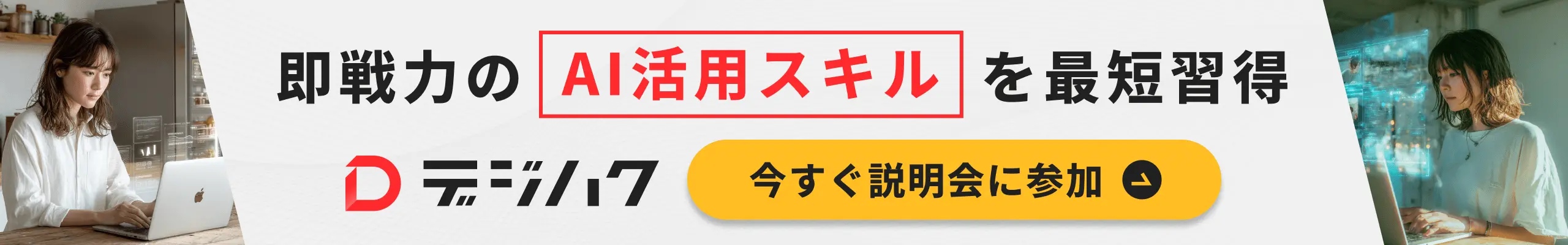この記事でわかること
- <マーケティングの基本>4P分析と4C分析の違い
- 4P分析と4C分析それぞれの意味
- マーケティングミックスとは
- 成功事例や分析のやり方
終身雇用の崩壊により、副業やフリーランスの活動が注目を集めています。
この社会の変化により、誰もが自ら事業を作る時代へと変わってきました。
この記事を読まれている方の中にも、副業やフリーランスとして働いていくことを検討されている方がいるのではないでしょうか。
そこで重要になるのが、マーケティングです。

マーケティングとは、顧客に商品やサービスを認知・購入してもらう方法や施策のことです。
マーケティングを知らないと、副業やフリーランスで活躍するのは難しいでしょう。
事業を始めるなら、自分自身で商品やサービスを販売する必要があるからです。
そこで本記事では、マーケティングの基本である4P分析・4C分析をわかりやすく解説します。
4P分析と4C分析との違いや活用方法と、記事後半では成功事例を交えてお伝えするため、これから副業やフリーランスの活動をする方には参考になるはずです。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
【マーケティングの基本】4P分析と4C分析は何が違う?

マーケティングの世界では基本中の基本の言葉「4P分析」と「4C分析」。
共にマーケティング戦略に必要なフレームワークです。
この二つの違いはズバリ、視点の違いです。
4P分析は、企業視点。
4C分析は、顧客視点。
まったく真逆とも言える視点から考えるマーケティング戦略、この2つの4Pと4Cの関係性は分析をする上で大変重要なものになってきます。
それでは、「4P分析」と「4C分析」それぞれの解説をしていきます。
マーケティングの基本・4P分析とは

マーケティングにおける4P分析とは、1960年代にアメリカのマーケティング学者によって提唱され、現代でもマーケティングの中心として活用されているフレームワークです。
企業が顧客に商品やサービスを購入してもらうために練る戦略の一つの手段として使用していきます。
4P分析の4Pとは、以下の単語の頭文字の4つのPを指しています。
- Product(商品・サービス)
- Price(価格)
- Place(流通・立地)
- Promotion(販売促進・広告)
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.Product(商品・サービス)
プロダクトとは、企業の自社商品や自社サービスのことです。
プロダクトの内容は企業によって変わります。
- ユニクロ→洋服
- マクドナルド→ハンバーガー
- メルカリ→フリマサービスアプリ
ここで言う“プロダクト”とは、商品のことだけではなく、商品のパッケージや品質、ブランド名、サービスや保証などの全てを指します。
プロダクトの段階では、商品やサービスが消費者のニーズをどのように満たしていくのかを考えていきます。
2.Price(価格)
4P分析で2番目に考えるのが価格です。
消費者にとって適正価格でサービスを提供できるかを検討し、企業に利益を残せるのかを考えていきます。
商品の価値に対してあまりにも高価だったり安価だったりすると、業績を伸ばすのが難しいでしょう。
価格設定を考えるときは市場に合った価格設定や、価格に値する価値を提供できるのかという点も重要で、価格によってターゲット層も決定します。
“Price(価格)”を決定するためには、競合の研究やニーズ、市場を徹底的に把握する必要があります。
3.Place(流通・立地)
Place(=流通・立地)では、どこでどのように商品やサービスを届けるか、ターゲット層に届くまでの販売経路を考えていきます。
- 海外から輸入するのか
- どの立地で出店するのか
- オンラインで販売するのか
多くの顧客に届けるなら販促ルートは複数あると良いでしょう。反対に、希少価値を出すなら販売箇所を絞ってみるなどの演出も必要です。
商品の流通経路では、輸入なのか国産なのか、販売の仕方は実店舗やオンライン販売など色々なルートで販売するのか、店舗の場所も都内なのか、郊外なのかを考えるのも大切です。
Place(=流通・立地)は、自社製品やサービスのイメージ戦略にも大きく影響する、重要なポイントとなります。
4.Promotion(販促活動)
Promotion(販促活動)では、商品やサービスが認知される方法を考えます。
販促活動は主に以下のような活動が挙げられます。
- ホームページを作る
- メールマガジンを発行する
- ポスターを作成する
- TVCMを制作する
- SNSを利用する
企業の広告費用には制限があるため、より具体的で効果的な戦略を考える必要があります。
プロモーションは、商品の売れ行きに直接的に影響するためより具体的な戦略が必要です。

プロモーションは、ターゲット層にコミットしたものを選択をすることが重要です。
マーケティングの基本・4C分析とは

4Pとは企業側のマーケティングの手法です。
それに対して、4Cは消費者側の目線に立ったマーケティングの考え方です。
顧客視点に立ち、マーケティングを実践するのは重要なこと。こちらでは4C分析について解説します。
4C分析の4Cとは、以下の単語の頭文字の4つのCを指しています。
- Customer Value(顧客価値)
- Cost(経費)
- Convenience(利便性)
- Communication(コミュニケーション
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.Customer Value(顧客価値)
Customer Value(顧客価値)とは、商品やサービスを利用した顧客が実際に感じる「価値」です。
顧客満足度とも言えるでしょう。
商品やサービスの使いやすさだけでなく、「その商品やサービスを利用すると楽しい気持ちになる」のような感情面も含まれます。
顧客価値を意識したプロダクト(商品・サービス)を提供し、満足度の高い価値を与えるための方法となります。
2.Cost(経費)
消費者にとってのコスト=経費とは、プロダクト(商品・サービス)を手に取るまでの時間や費用です。
購入する場所までの移動に使う交通費、時間のようなプロダクトに関わるまでの費用も含まれます。
企業目線だと、金銭的な費用に意識がいきがちですが、消費者目線では価格以外のコストを考えてみるのがおすすめです。
例えば、家事代行サービスなら「家事をする時間を他のことに充てる時間にしたい」という人達が利用します。
つまり、家事の手間だけでなく、家事をする時間にもコストがかかっているという感覚で顧客は経費を払っています。
顧客目線でコストを考えると、マーケティングのヒントが隠れています。
3.Convenience(利便性)
消費者にとってそのプロダクト(商品・サービス)は使いやすいか、始めやすいかは利便性に大きく影響します。
また、販促経路も利便性に直結します。
- オンライン販売
- 実店舗販売
オンライン販売であれば、家からでも外出先からでも、いつでもどこからでも購入できます。
実店舗なら、駅前や人通りの多い場所に店舗を構えていれば、多くの人が足を運びやすいでしょう。
また、オンライン販売の場合、ページ内での検索や決済のしやすさなども「Convenience(利便性)」に含まれます。
4.Communication(コミュニケーション)
オフライン、対面、イベント、SNSなどを利用してコミュニケーションが取れる仕組みを考えるのが重要です。
また、プロダクトによってはアフターサービスの対応の良さや質問・相談がしやすい環境も求められるでしょう。
以前は、顧客と企業のコミュニケーションツールには電話やメールなどしかありませんでしたが、最近はチャットでの対応をする企業も増えています。
チャットは、そのレスポンスの速さで顧客の満足度を非常に高めることができる、効果的なツールのひとつです。
このように、コミュニケーションの面からも安心して便利に商品やサービスを使っていただくように工夫していきます。
マーケティングミックスとは?

Marke TRUNKによると、マーケティングミックスとは、マーケティング戦略全体のなかで「実行戦略」と位置づけられると言われています。(引用:マーケティングミックス4Pとは|MarkeTRUNK)
マーケティングミックスとは簡単に言うと、主に4P分析と4C分析を組み合わせて、顧客と企業2つの目線からマーケティング戦略を立案するフレームワークの手法です。
重要なのは、マーケティングミックスの前に行う
STP分析です。
STP分析がしっかりと行われていないと、効果的なマーケティングミックスでの立案は難しくなってきます。
STP分析については、「マーケティングミックス成功事例」の後にご紹介しています。
4P分析・4C分析|マーケティングミックス成功事例

ここからは、有名企業が実践してきた4P分析の成功事例を解説します。
4P分析のマーケティングを取り入れるときの参考にしてみてください。
成功事例1.スターバックス
1つめは、スターバックスです。
世界中に32,000店舗あり、国内外問わず発展してきたスターバックスはどんな4P分析をしてきたのでしょうか。
- Pruduct(商品・サービス)
・コーヒー飲料のサービス
・マイボトルの対応
・新商品を継続的に提供 - Price(価格)
・1杯300〜500円で提供
・マイタンブラーを持ち込むとコーヒーを安く提供 - Place(流通)
・一般層ではなくビジネスマンをターゲットにした - Promotion(販売促進)
・広告・宣伝活動はせずに、口コミや店頭でのアプローチのみ
少食な日本人のために作られたショートサイズ、アメリカではベンティの上のサイズ、トレンタサイズがあるように、世界各国によって少しずつ違うプロダクトを提供しています。
コーヒーにしてはやや割高の価格ですが、スターバックスに来るお客さんは勉強をしたり仕事をしたり店員さんとコミュニケーションをしたりして過ごしています。
消費者はコーヒーだけではなく、その場所に価値を感じて料金を払っています。

これは、スターバックスのコンセプトでもある「家と職場に次ぐ、落ち着く第三の場所=サードプレイス」を演出した結果です。
また、価格は大きく変化させずに、マイタンブラーを持参すると、コーヒーの値段を安くするといった施策でリピーターを獲得してきました。
流通面ではスターバックスのターゲット層は高級志向なビジネスマンのため、価格を割高にして一号店を銀座に出店しました。
目立つ広告はせずに、口コミとPR活動のみでプロモーションを行ってきました。
先ほど解説した「サードプレイス」というアットホームなイメージを定着させたかった狙いがあります。
的確な4P分析の上でブランドを確立したスターバックスは、時代や顧客の変化に合わせた新たな戦略も始めています。
最近では定期的に新商品を発売して若年層の顧客も獲得する動きをしています。
ターゲット層に合わせてSNSをうまく活用したプロモーションが成功していますが、流行に敏感な若年層の売上が流動的でもスターバックスは揺るぐことはないでしょう。
なぜなら、ベースとして4P分析による戦略で獲得した当初のターゲット層の顧客を、しっかりと定着させているからです。

収益の安定化には、リピーターの確保、拡大が大変重要です。
成功事例2.吉野家
次は吉野家です。
吉野家は2020年までに60億円の赤字を抱えていました。
しかし、4P分析を取り入れたマーケティングを実施したところ、黒字化に成功。
営業利益を39倍にしてV字回復を見事達成しました。
吉野家のマーケティングはどんな方法だったのでしょうか。
- Product(商品・サービス)
・牛丼の小盛や超特盛のメニューを追加した
・RIZAP牛サラダ丼を販売開始 - Price(価格)
・ご飯のおかわり無料サービス
・おかずをダブルで付ける - Place(流通)
・テーブル席やソファ席を設置し家族や主婦層を獲得 - Promotion(販売促進)
・店頭にポスターを設置
当時の吉野家の顧客層は高齢者が多くなっていました。
そこで、少食の高齢者に向けて小盛のサービスを開始。
そして、既存の男性客には超特盛のオーダーができるようにして、既存客の満足度と高齢者のリピーターを獲得するマーケティングを施策しました。
また、価格に関してほとんど変更せず、ご飯のおかわり無料・おかずをダブルで付けるといったサービスでお得感を出して価格をキープしました。
元々、牛丼の価格は安いため当然の戦略でしょう。

吉野家のイメージと言えば、カウンターで男性が食べている印象・・。戦略変更し、顧客にどのような変化があったのでしょう。
吉野家は、テーブル席やソファ席を設置し、家族や主婦でも楽しめる外食へと変化しました。
そうすることで、今まで来なかった主婦層・家族層の獲得に成功します。
宣伝活動については、吉野家の立地条件は駅前にあり人通りが多いため、大きなポスターを設置して宣伝活動を行いました。
成功事例3.花王ヘルシア緑茶
体形が気になる方なら一度は飲んだことがある「花王ヘルシア緑茶」。
2003年に発売し、たった10ヶ月で約200億円の売上高を作った、大ヒット商品です。
花王ヘルシア緑茶のマーケティングはこのようなマーケティング戦略でした。
- Product(商品・サービス)
・厚生労働省からの特定保健用食品の認可獲得
・体脂肪燃焼効果のある高濃度茶カテキン配合を飲みやすく改良 - Price(価格)
・350mlで180円という高価格帯に設定 - Place(流通)
・販売当初、ターゲット層が買いやすいコンビニ限定 - Promotion(販売促進)
・コンビニ限定商品
・テレビ中心の広告
「花王ヘルシア緑茶」のターゲット層は、健康に気を使い始めた中高年のビジネスマン世代です。
お腹の脂肪が気になり始めた年代をターゲットに、厚生労働省から体脂肪燃焼効果のお墨付きをもらう事で、信頼性もUPしています。
少し高めの値段設定は、トクホ製品である付加価値と濃いカテキンで効果がありそうという2つの効果を演出するための価格設定とも言えます。
「安いものより、高いものの方が上質」と考える消費者心理もうまく捉えています。
Place(流通)の戦略として、コンビニ限定で販売していたのも効果的でした。
ターゲット層の行動パターンを分析したところ、手に取りやすい場所としてコンビニエンスストアが最適だったからです。
また、コンビニエンスストアでは、各社レジ横に陳列するなどの対策が取られました。

洗剤など日用品のイメージが強い花王でしたが、初めての飲料部門での大ヒットの裏には4P分析が大いに活用されていたというわけです。
4P分析・4C分析以外のフレームワークを簡単解説

4P分析・4C分析以外にも、マーケティング戦略を考える上で必要なフレームワークがあります。
良く使われる代表的なものを3つ、簡単にご紹介します。
- STP分析
- SWOT分析
- 3C分析
それぞれ解説していきます。
- Segmentation(セグメンテーション)
- Targeting(ターゲティング)
- Positioning(ポジショニング)
アメリカの経営学者フィリップ・コトラー氏によって提唱された手法であるSTP分析は、マーケティング戦略を考える上で一番始めに取り組むべき方法です。
STP分析の詳細は以下の通りです。
- 市場全体の分析:細分化、区分分けして分類する
- 狙うべき市場の選択:
- 自社の位置を決める
STP分析に加え、今後の市場などを予測していくことも忘れないでください。
SWOT分析
SWOT分析は、徹底的に自社の内部環境、外部環境の分析を行う時に使う手法です。
- Strength:強み
- Weakness:弱み
- Opportunity:機会
- Threat:脅威

SWOT分析ではプラス要因やマイナス要因を明確に把握することができる為、より具体的な戦略に落とし込むことができます。
3C分析
4C分析と似ていますが分析する対象が異なります。
3C分析は環境分析の為、今までのように顧客視点でも企業視点でもない立ち位置からの分析になります。
- Customer:市場・顧客
- Competitor:競合
- Company:自社
4P分析・4C分析を活かしたマーケティングのやり方

- <市場調査>STP分析
- <顧客行動分析>4C分析
- <実行戦略>4P分析・4C分析によるマーケティングミックス
<市場調査>STP分析
まずはSTP分析・3C分析・SWOT分析などのフレームワークを活用し、市場調査をします。
市場全体を把握し、競合調査や自社の立ち位置、狙うべき市場などを選択していきます。
<顧客行動分析>4C分析
顧客の行動を4C分析を使って行います。
より具体的に戦略を考える際には、ペルソナ設定やカスタマージャーニーマップを作成し、顧客の潜在的な行動心理までを分析するといいでしょう。
ターゲット層のニーズを最適化しておくことが重要です。
<実行戦略>4P分析・4C分析によるマーケティングミックス
市場や顧客行動で分析した結果に基づき、自社商品、自社サービスの具体的な実行戦略を練っていきます。
これがマーケティングミックスです。
複数の分析要素が必要になってきますが、色々な角度から分析した結果を活用することで、より綿密な戦略を立てる事や検討、解析が可能になります。

顧客のニーズや市場を見据えた戦略を策定するには欠かせない手法となっています。
マーケティングの基本|4P分析と4C分析を最大限に活かした戦略を立てることが必須!

4P分析・4C分析との違いなどを解説しました。
4P分析はいずれかがバラバラになると、整合性が取れず一気通貫したプロダクトにならなくなってしまいます。
そのためにも、明確な目的設定だけでなく、フレームワークを活用した具体的な戦略・戦術を考えていきましょう。
本記事が4P分析の参考になれば幸いです。
マーケティング用語を知りたい方はこちらの記事もおすすめ!

 で
で