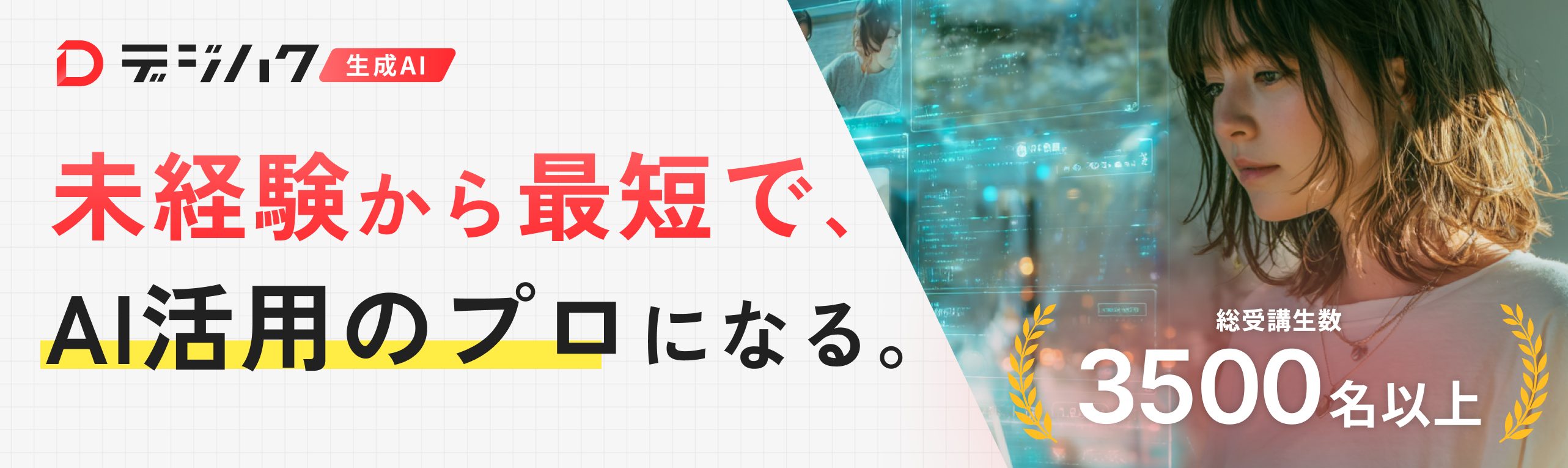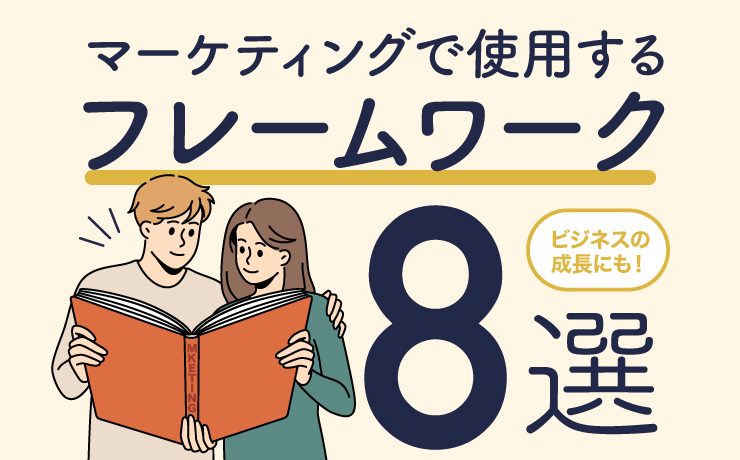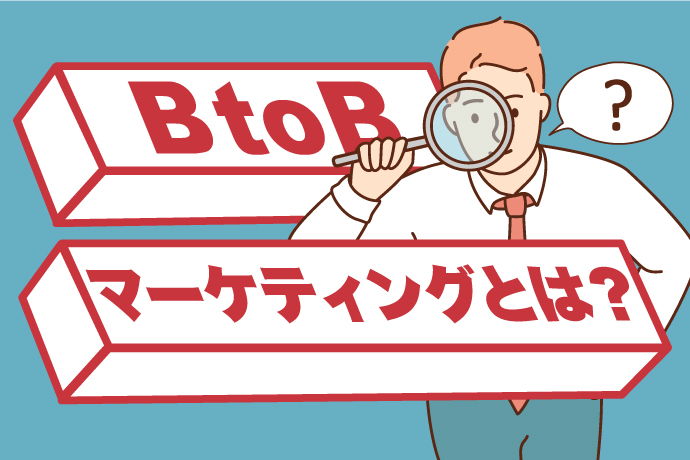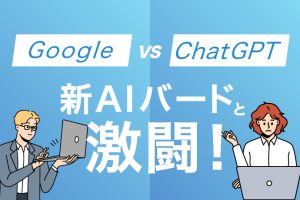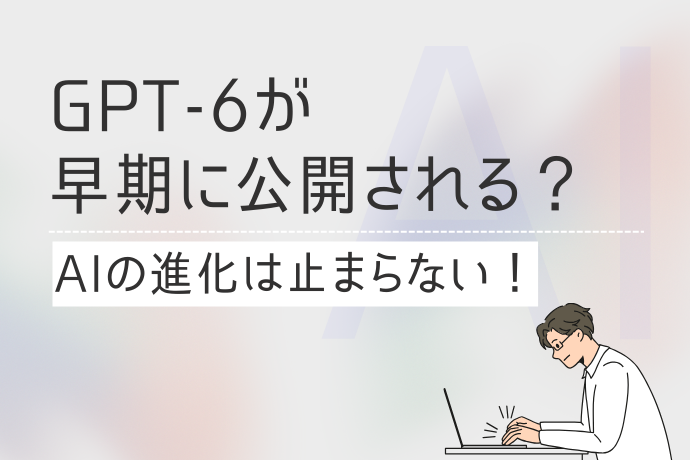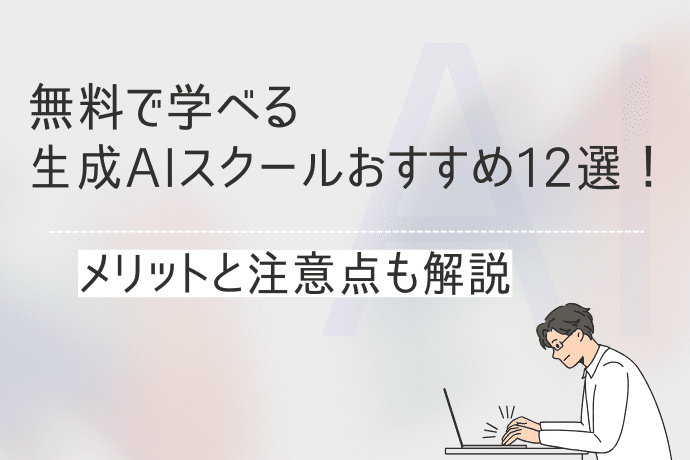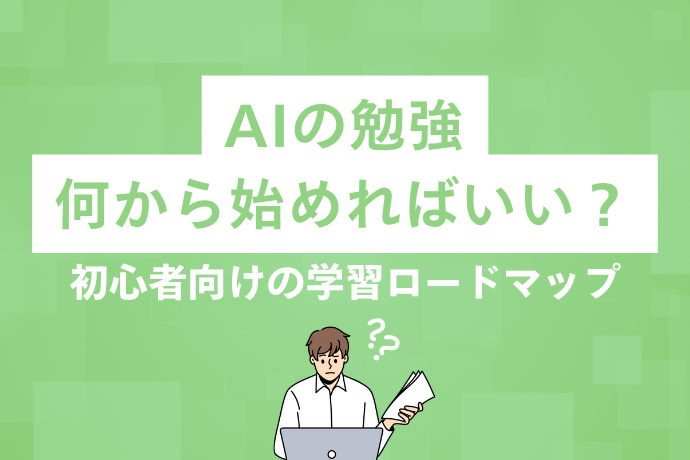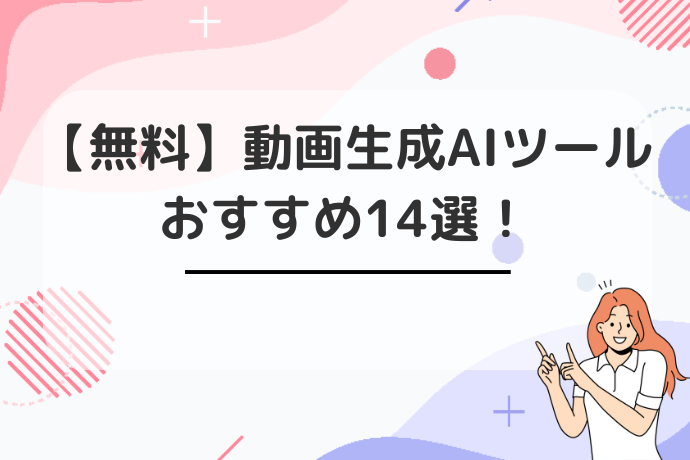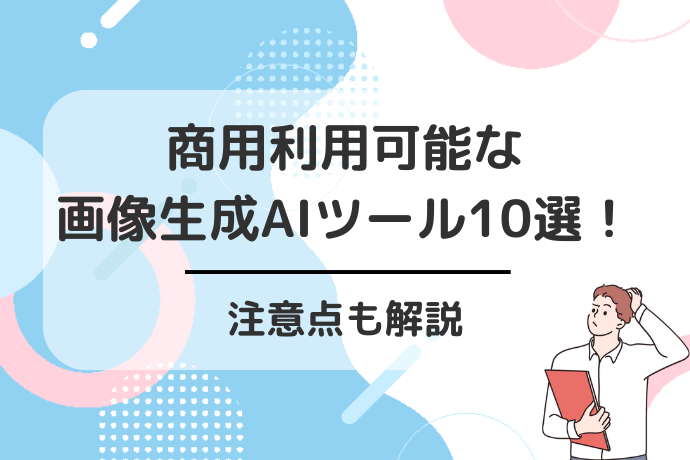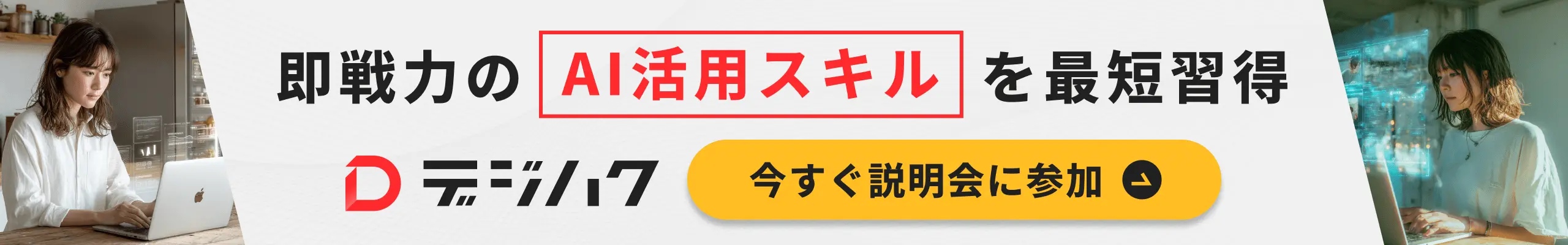この記事でわかること
- マーケティングのフレームワークを知りたい
- マーケティングフレームワークのメリットとデメリット
- カテゴリー別マーケティングのフレームワーク
マーケティングにはいくつかのフレームワークがあります。
マーケティングのフレームワークは、問題を整理し、正しい施策を行ううえでは必要ですが、種類が多くてわかりづらいです。
そこで本記事では、
- 顧客理解のフレームワーク
- 商品・サービス理解のフレームワーク
- アイデアをまとめるフレームワーク
上記3つのカテゴリーに分けてマーケティングのフレームワークを解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
マーケティングフレームワークとは?

フレームワークとは、問題解決をするための手法・手段です。
マーケティングのフレームワークがあることで、課題を抽出し解決に向けての分析などを行う枠組みを定めます。
マーケティングフレームワークの目的とは

マーケティングのフレームワークの目的とは、問題を整理し、正しい施策を行うためです。
論理的に考え方のレールを作ることができ、必要な情報選択を助けてくれます。
一方で、デメリットもあります。
ここからはメリットとデメリットについて、お話していきます。
マーケティングフレームワークのメリット
メリットとして
- 目標達成までの作業時間の短縮
- コミュニケーションが円滑になる
- 多くの人が開発に参加しやすくなる
- フリーランスでも仕事が取れる
などが挙げられます。
フレームワークに沿って話すことができるため、軸がズレずにスムーズに課題解決を目指すことができます。
マーケティングフレームワークのデメリット
デメリットとして
- 最適なフレームワークの判断が難しい
- 作成しただけで満足してしまう
- 思考が固定化されてしまう可能性がある
- コーティングスキルの向上が難しい
- アイデアが出にくくなる
マーケティングフレームワークを使用することでイメージが偏ってしまい、様々なアイデアを出すことが難しいことに繋がる可能性があります。
顧客視点の代表的なフレームワーク

一つ目は、顧客理解をするためのフレームワークを解説します。
具体的には下記のとおりです。
- 3C分析
- 4C分析
それぞれみていきましょう。
3C分析
3C分析とは、「Customer(市場・顧客)」、「Competitor(競合環境)」、「Company(自社環境)」の3つの頭文字を取ったマーケティングのフレームワークです。
3C分析では、市場・顧客、競合、自社の3つの視点からビジネスやマーケティングの問題点・成功理由を見つけていきます。
マーケティングの分析は膨大な情報があるため、3C分析を活用して、情報を整理し競合や自社を理解することで顧客満足度の高いビジネスを生み出せます。
4C分析
続いては4C分析です。
4C分析とは、「Customer Value(顧客価値)」、「Cost(顧客の費用・負担)」、「Convenience(顧客の利便性)」、「Communication(顧客との対話)」という4つの頭文字を取ったマーケティングの手法です。
顧客にとっての費用や負担とは、交通費のような商品やサービスを手に取るまでのコスト。
顧客の費用や負担まで分析することで、3C分析よりも深い顧客理解が可能です。

そのため、顧客満足度の高いマーケティング戦略を考えるうえで4C分析は重要です。
商品やサービス理解のデータ分析フレームワーク

続いては、商品・サービス理解のためのフレームワークを解説します。
具体的には下記のとおりです。
- 4P分析
- SWOT分析
- STP分析
- PEST分析
それぞれ具体的にみていきましょう。
4P分析
まずは4P分析です。
4P分析とは、「Product(製品)」、「Price(価格)」、「Place(流通)」、「Promotion(販売促進)」のそれぞれの頭文字を取ったマーケティング手法のことです。
4P分析を実践することで、企業の商品やサービス作りから販売するまでを分析できます。
企業によっては、担当者が別で配属されている場合がありますが、可能であれば同じ担当者の方が良いでしょう。
企業の商品作りから販売戦略まで一つ筋が通ったマーケティングができるからです。

4P分析は企業のマーケティングの根幹的な部分のため、上手くいけば業績がV次回復させることも可能です。
SWOT分析
SWOT分析とは、企業内の「Strength(強み)」、「Weakness(弱み)」と企業外の「Opportunity(機会)」、「Threat(脅威)」の頭文字を取ったマーケティング手法のことです。
自社商品の強みや弱みを分析し、社会という外部要因からどのように影響を受けるかを考え、今後の解決策に役立てていきます。
自社のブランド力をアップさせたり競合他社の分析や市場の流れを分析するためのツールです。

SWOT分析によって自社商品のポイントが見えてきたら、現状を分析するクロス分析を行うと、より具体的な戦略を作ることができるでしょう。
STP分析
STP分析とは、「Segmentation(市場細分化)」、「Targeting(狙うユーザーや市場)」、「Positioning(自社の存在価値)」の三つを分析するフレームワークです。
STP分析は、参入する市場を分析し、自社がサービスを提供する顧客にどのような価値を提供していくことが重要なのかを考える有名な手法です。
市場を細分化し、自社の強みを知ることでどのようにプロモーションしていくかが見えてきます。
STP分析をして、一足先に有利になる領域で利益を上げることを目指します。
PEST分析
PEST分析とは、「政治(Politics)」、「経済(Economy)」、「社会(Society)」、「技術(Technology)」の頭文字を取ったマーケティングのフレームワークです。
社会全体という大きな枠組みを析することで、外的な要因が自社のサービスにどのように影響するのかを明確にし、今後に必要な施策を考えていきます。
ビジネスをしていると、企業の内的な要因に目がいきがちですが、時には制御できない変数が動く可能性も考えるのが大事です。
アイデアをまとめるためのフレームワーク

次に解説するのは、アイデアをまとめるためのフレームワークです。
具体的には下記の2つです。
- MECE
- ロジックツリー
詳しくみていきましょう。
MECE
MECEは、Mutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの頭文字を取ったもので、「ミーシー」や「メーシー」などといわれています。
ターゲット分析や市場把握をする際に、モレやダブりがないかを確認するための手法です。
MECEを利用することで、同じような問題に気づけなかったり似た問題を解決していたりする事態を防ぎます。
問題を洗い出すときには、MECEは有効です。
また、MECEは物事を細分化・構造化するので、論理的思考が必要です。

マーケティング以外にもビジネスシーンで役立つため、覚えておく価値は高いでしょう。
ロジックツリー
ロジックツリーとは、さまざまな問題を細かく分岐させることで、原因や解決方法を見つけていく手法です。
ロジックツリーには下記のようにいくつかの種類があります。
- Whatツリー
- Whyツリー
- Howツリー
- KPIツリー
抱えている問題や解決する課題によって使い分けなければいけません。

どのような場面で使用するか解説します。
Whatツリー
Whatツリーは、課題の内容を分解し、選択肢の中から答えを見つけるロジックツリーです。
一つの話題に対して、複数の可能性が考えられるときに情報を整理するために使用します。
Whyツリー
Whyツリーでは、原因に対してのなぜそのような結果なのか、そしてそれはどのようにしていけば解決していけるかを明確にするめの手法です。
Howツリー
Howツリーは、問題解決の手法を明確化したいときに使用します。
どのような施策を行えば、効果的な結果が得られるかを決めていく際に役立つ方法です。
KPIツリー
KPI(Key Performance Indicator)ツリーとは、KGI(Key Goal Indicator) と呼ばれる企業が掲げている一番の目標までをどのようにして進んでいけば達成できるかを数値化してステップごとに見える化したものです。
フレームワークを使用するときに気を付けること

ここからは、フレームワークを活用する際の注意点を解説します。
フレームワークは手段であり目的になってしまってはいけません。
フレームワークを知っていると、つい使うことが目的になってしまいます。
しかし、マーケティングで実践する以上、成果につなげなくてはいけないため、色々なフレームワークを知っているのは良いですが、成果につながるフレームワークを使用する必要があります。

市場の状況や自社のリソースなどを考慮したフレームワークを使用することで、真の顧客満足度の高いマーケティングの施策が実行できるのではないでしょうか。
効果的なマーケティングを実践するためにフレームワークを知りましょう

マーケティングのフレームワークや効果を解説してきました。
ここまでに解説したマーケティングのフレームワークは以下です。
- 【顧客理解を深めるマーケティング】
3C分析
4C分析
4P分析 - 【商品・サービス理解のフレームワーク】
4P分析
SWOT分析
STP分析
PEST分析 - 【アイデアをまとめるためのフレームワーク】
MECE
ロジックツリー
マーケティングのフレームワークは多種多様です。
正しくフレームワークを活用して、顧客満足度の高い商品やサービスを実現できる手助けになれれば幸いです。

 で
で